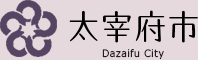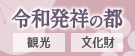本文
介護保険のしくみ
介護保険のしくみ
介護保険制度は、平成12年度からスタートした介護を社会全体で支えあう制度です。
40歳以上の人が被保険者となって介護保険料を納め、介護や支援が必要となったときに、認定をうけることによってサービスが利用できるようになります。
65歳以上の人を第1号被保険者、40歳から64歳までの医療保険に加入している人を第2号被保険者といいます。
必要な届出
次のような場合には届出をしてください。
- 他市町村から転入してきたとき、または他市町村に転出するとき
- 住所や氏名、世帯が変わったとき
- 被保険者本人が亡くなったとき
- 市外の介護保険施設等に入所(入居)して住所を異動したとき
新規の認定申請からサービス利用までの流れ
相談して申請してください
介護が必要と感じたときは、まず地域包括支援センターや市介護保険課にご相談ください。
本人または家族等が申請できます。市役所に来ることが困難な状態にあるとき等は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者に代行してもらうこともできます。
申請のときに必要となる書類は次のとおりです。
- 要介護・要支援認定申請書(介護保険課窓口にあります)
- 主治医(かかりつけ)の医療機関名、医師氏名を確認しておいてください
- 介護保険被保険者証(65歳以上の人)
- 40歳から64歳(第2号被保険者)の人は、「有効期限内の医療保険被保険者証」、「資格確認証」、「資格情報のお知らせ」の写しのいづれかが必要です。(窓口で「医療保険の資格情報画面」をスマートフォン等での提示により確認させていただくことも可能です。)
第2号被保険者で認定を受けることができるのは、加齢と関係があり、要支援・要介護状態の原因となる心身の障害を引き起こす病気(特定疾病16項目)と診断された場合に限ります。
特定疾病
☆がん ☆関節リウマチ ☆筋萎縮性側索硬化症 ☆後縦靭帯骨化症
☆骨折を伴う骨粗しょう症 ☆初老期における認知症
☆進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 ☆脊髄小脳変性症
☆脊柱管狭窄症 ☆早老症 ☆多系統萎縮症
☆糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 ☆脳血管疾患
☆閉塞性動脈硬化症 ☆慢性閉塞性肺疾患
☆両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
訪問認定調査を行います
申請により、認定調査員が自宅を訪問し、心身の状況などについて本人や家族から聞き取り調査を行います。
この調査は、全国共通の調査内容になります。
主治医意見書の作成を市が依頼します
認定申請書に記入された主治医に市から意見書の作成を依頼します。
介護度が判定されます
訪問認定調査と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で審査し、どのくらい介護が必要か判定して要支援1から要介護5の介護度が決定します。場合によっては非該当という判定もあります。
介護認定審査会は、筑紫地区5市(太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市)で共同設置している審査会です。
医療・保健・福祉の専門家で構成された審査会となっています。
認定結果を通知します
介護認定審査会で出た結果を通知します。
介護保険被保険者証に決定した介護度と有効期間が印字されていますので確認してください。
サービスを利用します
ケアマネジャーにサービス計画を作成依頼し、サービスを利用します。
利用者の負担
介護サービスを利用したら、かかった費用のうち利用者負担の割合分(前年の所得に応じて1割から3割)をサービス提供事業者に支払います。
施設系のサービスを利用した場合は、食費・部屋代など保険対象外のものは自己負担となります。
利用者負担の軽減制度
介護保険の利用者負担が高額になったとき
同じ月に利用した介護サービス費の利用者負担額の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が一定の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として払い戻されます。
介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき
介護保険と医療保険のの両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます(高額医療・高額介護合算制度)。
介護保険と医療保険のそれぞれの限度額を適用後、年間(8月から翌年7月)の利用者負担額を合算して、一定の限度額を超えたときは、申請により払い戻されます。
低所得者の施設利用時の食費・部屋代(居住費)の軽減
低所得者で一定の条件を満たせば、施設入所・短期入所(ショートステイ)利用時の利用者負担額が所得等に応じて軽減されます。