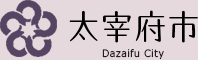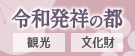本文
ひきこもりに関する相談・支援のご案内
ひきこもりについておはなし聴きます!
令和5年度より孤独・孤立対策の推進を図っており、また、令和6年度に実施した、「ひきこもり状態にある方に関する実態調査」にていただいたみなさまの声をもとに、
令和7年7月1日(火曜日)より「ひきこもりサポート事業」を開始します。
本事業において、相談窓口を開設し、専門の相談員がお話をお聞きしながら、さまざまなお悩みに寄り添いながらサポートします。
ひきこもりは特別なことではありません。誰にでもおこりうる状態、表現のひとつです。
自分だけ、家族だけではどうしていいか分からない、今の気持ちを誰かに聞いてほしいなど、まずは相談してみませんか。
太宰府市ひきこもりサポート事業のご案内 [PDFファイル/176KB]
また、ニュースレターTomoni (ver5) [PDFファイル/2.98MB]を発行しました。
こちらでは、家族のつどい・フリースペース等のご案内やひきこもりに対する理解のポイントなどをお知らせします。
市民向け講演会のお知らせ
2月13日(金)にひきこもり等に興味のある市民や家族を対象としたCafe de 「こもりびと」だざいふを開催します。
ひきこもりについての理解を深める良い機会ですので、ぜひご参加ください。詳細については、上記リンク先のページよりご確認ください。
相談窓口の開設
ひきこもりサポート事業にあわせ、生活支援課内に相談窓口を開設します。
ひきこもりのご本人やご家族からの相談に応じて助言を行うとともに、相談内容に応じ医療・教育・労働・福祉などの適切な関係機関との連携や市の就労準備支援事業につなぎます。
場所
太宰府市生活支援課(市役所1階 14番窓口)
※来るが難しい方については、自宅でお話を伺います。
相談日
火曜日・木曜日(祝日を除く) 午前8時30分~午後5時
※予約受付は、月曜日~金曜日まで、生活支援課(14番窓口)で行っています。
予約受付・お問い合わせ先
予約受付は、専門相談員へのお電話・メールや受付フォームなどからお申し込みください。
〇専門相談窓口(ひきこもり支援コーディネーター)
電話番号 090-4061-9081(直通)
メール tomoni★docomo.ne.jp
※メールアドレスは★を@へ置き換えてください。

〇太宰府市役所健康福祉部生活支援課
電話:092-921-2121(内線300)
専門相談員の紹介
相談員
太宰府市ひきこもり支援コーディネーター 小野(おの)
(社会福祉士、保護司、障がい児・者計画相談員)

好きなこと
食べること、楽しいことを考えること
自己紹介
「誰にも話せない」「どこに相談したらよいかわからない」そんな気持ちを抱えているご本人やご家族のために安心してお話しいただける場所をひらいています。
今すぐ何かを決めなくても大丈夫です。困っていることがはっきりしなくても構いません。
お話をするなかで少しづつ気持ちがほぐれていくようにそっと寄り添います。
ひとりで抱え込まず、どうぞお気軽にお立ちよりください。
いつでもお待ちしています。
ニュースレターTomoni
ニュースレターTomoniを発行しています。
こちらでは、ひきこもりに関する情報や家族のつどい・フリースペースなどをお知らせしています。
お時間のあるときにでもご覧ください。
【back number】
・Tomoni(ver.5) [PDFファイル/2.98MB]
・Tomoni(ver.4) [PDFファイル/2.98MB]
家族のつどいのお知らせ
ひきこもり状態にある方のご家族を対象に、ひきこもりについての理解や声掛けの工夫などを学びながら、日頃の悩みや気持ちを家族同士の交流や語らいを通して、不安や孤立感の軽減を図ることを目的に、家族のつどいを開催しています。
同じ悩みや気持ちを話すことで少し気が楽になればいいな、というようなものです。
あまり気を張らずに、どんなことでも話してみてください。
概要
原則、毎月1回 第2木曜日の14時~16時 開催(8月と3月は別日開催)
〇 場所:太宰府市内(下記の開催予定をご確認ください。)
※会場は変更となる場合がございます。
〇 参加費:無料
〇 定員:6名まで
〇 対象:ひきこもり状態にある方のご家族
〇 随時申込受付します。ご希望の方には、個別相談(要予約)も行います。
〇 内容については変更となる場合があります。
開催日時(令和7年度)
| 開催日 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 7月10日(木曜日)※開催終了 |
いきいき情報センター 2階 203室 (太宰府市五条3-1-1) |
初めまして会 |
| 8月28日(木曜日)※開催終了 |
新崎アパート (太宰府市五条4-11-15) |
茶話会 |
| 9月11日(木曜日)※開催終了 |
いきいき情報センター 2階 203室 (太宰府市五条3-1-1) |
社会資源のはなし |
| 10月9日(木曜日)※開催終了 |
いきいき情報センター2階 203室 (太宰府市五条3-1-1) |
茶話会 |
| 11月13日(木曜日)※開催終了 |
いきいき情報センター 2階 203室 (太宰府市五条3-1-1) |
こころのはなし |
| 12月11日(木曜日)※開催終了 |
いきいき情報センター 2階 201室 (太宰府市五条3-1-1) |
家族のはなし |
| 令和8年1月8日(木曜日)※開催終了 |
いきいき情報センター 2階 203室 (太宰府市五条3-1-1) |
セルフケアのはなし |
| 2月19日(木曜日) |
いきいき情報センター 2階 201室 (太宰府市五条3-1-1) |
茶話会 |
| 3月19日(木曜日) |
いきいき情報センター 2階 (太宰府市五条3-1-1) |
振り返り会 |
申し込み
次の受付フォームより申し込みください。

※お電話での申し込みも受け付けしております。
電話:092-921-2121(内線300)
フリースペースのお知らせ
ひきこもり状態にある方を対象に、家から一歩踏み出して、誰かと一緒に時間を過ごすことで自宅以外で安心して過ごせる居場所となることを目的に「フリースペース」を提供します。
ただいるだけでいい安心できる空間を提供します。
概要
原則、毎月1回 第4火曜日の14時~16時 開催(12月は別日開催)
〇 場所:太宰府市内(下記の開催予定をご確認ください。)
※会場は変更となる場合がございます。
〇 参加費:無料
〇 定員:6名まで
〇 対象:対人や社会との関わり方に悩んでいる本人
〇 随時申込受付します。ご希望の方には、個別相談(要予約)も行います。
〇 内容については変更となる場合があります。
開催日時(令和7年度)
| 開催日 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|
| 7月22日(火曜日)※開催終了 |
総合福祉センター 3階 研修室 |
映画鑑賞 |
| 8月26日(火曜日)※開催終了 |
いきいき情報センター 2階 209室 (太宰府市五条3-1-1) |
茶話会 |
| 9月18日(木曜日)※開催終了 |
プラム・カルコア太宰府 2階 研修室1 (太宰府市観世音寺1-3-1) |
読まない読書会 |
| 10月28日(火曜日)※開催終了 |
いきいき情報センター 2階 203室 (太宰府市五条3-1-1) |
パステルアート |
| 11月25日(火曜日)※開催終了 |
いきいき情報センター 2階 213室 (太宰府市五条3-1-1) |
コラージュ体験 |
| 12月23日(火曜日)※開催終了 |
いきいき情報センター 2階 209室 (太宰府市五条3-1-1) |
自分のことを知ろう |
| 令和8年1月20日(火曜日) |
いきいき情報センター 2階 208室 (太宰府市五条3-1-1) |
セルフケアのコツ |
| 2月24日(火曜日) |
総合福祉センター 3階 研修室 |
茶話会 |
| 3月24日(火曜日) |
いきいき情報センター 2階 (太宰府市五条3-1-1) |
自分史をつくろう |
申し込み
次の受付フォームより申し込みください。
※お電話での申し込みも受け付けしております。
電話:092-921-2121(内線300)
その他
福岡県ひきこもり地域支援センター<外部リンク>
福岡県でも相談受付、フリースペースの提供を行っています。
市内だと近すぎて相談しにくいといった方は、こちらもご活用ください。
ふくおかバーチャルさぽーとRoom<外部リンク>
福岡県にて、メタバースを活用した「ふくおかバーチャルさぽーとRoom」を開設しています。
こちらでは、アバターを使った交流会や就労体験、個別相談などを利用することができます。
※バーチャル居場所、バーチャル交流会は、「ふくおかバーチャルさぽーとRoom」の利用申し込みをされた方は、どなたでも利用できます。アバター個別相談、ジョブトレーニング(就労体験)等のご利用ご参加には、原則として、改めて県内の若者サポートステーション等福岡県内の対象となる支援機関への事前登録が必要です。
希望の方は、利用申し込みのうえ、太宰府市のひきこもり相談窓口までご連絡下さい。
令和7年度メタバース活用長期無業者就労支援事業を実施します!<外部リンク>
まちの保健室
若者の居場所づくりに取り組んでいる一般社団法人「ソーシャルワーク・オフィス福岡」(Swof)が、本市と連携しいきいき情報センターに「まちの保健室」を開設しています。
ここでは、相談員が常駐し、さまざまな相談ができます。こころや体の不調の相談だけでなく、なんでも悩みごとを話せる身近な居場所として、ぜひ気軽に立ち寄って、悩み事を相談してください。
ひきこもりとは
内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査」(令和4年度)では、全国で「ひきこもり状態」に該当した方は、15歳から64歳では、146万人と推計されています。およそ50人に1人程度の割合になり、身近な問題と言えます。
<対象となる方>
ひきこもり支援における対象者とは、社会的に孤立し、孤独を感じている状態にある人や、様々な生きづらさを抱えている状態の人となります。それぞれ一人ひとりの状況は違いますが、具体的には、
- 何らかの生きづらさを抱え生活上の困難を感じている状態にある
- 家族を含む他者との交流が限定的(希薄)な状態にある
- 支援を必要とする状態にある
本人やその家族(世帯)です。また、その状態にある期間は問いません。
(「ひきこもり支援ハンドブック~寄り添うための羅針盤~」より引用)
「ひきこもり」は病気の名前ではなく、状態を指す言葉です。「ひきこもり」の背景(原因)はさまざまです。
- 精神疾患が影響している場合
統合失調症、うつ病、強迫性障害、パニック障害などの病気が影響し、ひきこもりになることがあります。精神科医療機関での治療が必要です。 - 発達障がいが影響している場合
発達障がいの特性が影響し、ひきこもりになることがあります。発達障がいの特性にあわせた支援が必要です。 - 精神疾患や発達障がいが原因でない場合
この場合を「社会的ひきこもり」といいます。(上記の1、2の一部が含まれる場合もあります。)複数の原因や経過がいろいろあって、「社会的ひきこもり」にいたると考えられます。
原因が分からないと、「ひきこもり」から回復しないわけではありません。「ひきこもり」が、すぐに解決できる方法はありませんが、今できることを、少しずつ取り組んでいくことが大切です。
こんなことはありませんか?
- 人と会うのを嫌がる
- 家族との会話がない、顔を合わせない
- 無気力に見える
- 家族を責める
- 仕事についていないけど将来が不安
- このままでいいのかな
長年外に出ていない、近所のコンビニや趣味の用事などには出かけるが交遊がないなど、ひきこもりかどうかわからない場合もあるかもしれません。なぜひきこもっているのか、本人もわからない場合も多いのです。心の病の症状としてひきこもりが出現することもあります。
周囲からは、「楽をしている」「甘えている」など思われがちですが、ひきこもったことで人からの評価に過敏になったり、「自分はダメな人間だ」など苦しんでいる方が多いのです。
けれども、本人が「安心・安全」と思える環境でしっかり休むことができて、理解してくれる人がそばにいれば、回復に向かうことができるのです。
ひきこもり傾向チェック
ご自身や周りの方でひきこもりの傾向がないかチェックしてみませんか?
1ヵ月のひきこもり傾向チェック<外部リンク> (ひきこもり研究ラボ@九州大学の公式Webサイトより引用)
家族にできること
ひきこもりは、本人だけでなく家族にも様々な影響をもたらします。
家族がひきこもりについて正しく理解し、本人への適切な関わり方を実践していく方法を身につけることで解決の糸口がみえることもあります。
ひとりで抱え込まず、支援機関に相談しましょう。
本人の状態、家族の状況を整理し、どんな関わりができるか、第三者と一緒に考えていくことが大切です。
家族自身の生活を大切にしましょう。
家族が疲れて気持ちに余裕がなくなる、本人の行動を冷静に受け止めらず、イライラして口調がきつくなってしまうなど、本人との関 係が悪くなることがあります。そのためには、まずは「家族が元気になる」ことが大切です。
本人の「いいところ」「できていること」に目を向けてみましょう。
本人が働きたくても働けない理由の一つに、深刻なほど自信を失ってしまっている場合があります。
本人の「いいところ」「できているところ」に目を向け、「ありがとう」「うれしい」「助かったよ」など声かけすることで、本人の自信につながります