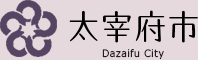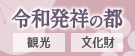本文
高額療養費
国民健康保険に加入する世帯でひと月に負担する医療費の金額は、年齢や所得に応じて、自己負担の上限が定められています。
注意:対象は保険適用分に限ります。
病院の窓口で支払った医療費が、下記の金額(自己負担限度額)を超えたときは、その超えた額が高額療養費として、世帯主に支給されます。(申請から支給までには3カ月以上かかります)
自己負担限度額の基本的な考えかた
- 暦月(月の1日から末日まで)ごとに計算します。
- 医療機関ごとに計算します。
- 同じ医療機関でも歯科がある場合、歯科は別計算します。
- 入院と通院は別計算します。
- 処方箋にもとづく薬局の自己負担は、病院の自己負担と合算して計算します。
- 入院時の食事代、保険対象外の治療や差額ベッド代等は含めません。
69歳までの人の自己負担限度額
| 所得区分 | 高額医療申請3回目まで (過去12カ月間で) |
高額医療申請4回目以降 (過去12カ月間で) |
|---|---|---|
| (ア) 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント | 140,100円 |
| (イ) 600万円超 901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント | 93,000円 |
| (ウ) 210万円超 600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント | 44,400円 |
| (エ) 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 |
| (オ) 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
所得とは、総所得金額等から基礎控除を差し引いた額のことです。
限度額適用認定証を支払の前にあらかじめ発行し、病院の窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。
限度額適用認定証を使用しても、世帯合算等によりさらに払い戻しになる場合があります。
入院時の食事代・差額ベッド代などは含めません。
世帯合算について
21,000円以上の自己負担が同じ月に2回以上ある場合、それぞれの自己負担を合算して自己負担限度額を超えた額が、高額療養費として支給されます。一人の方で2つ以上の病院にかかった場合、同じ世帯で違う人が病院にかかった場合のどちらでも合算の対象となります。
【高額医療費の計算例】 69歳以下の世帯
| 受診者 | 病院名・入院/外来 | 支払った医療費 | 合算 | 高額医療対象 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 夫 | A病院、入院 | 30,000円 | (a) | 可 | 30,000円 |
| 夫 | B病院、外来 | 10,000円 | 不可 | ||
| 妻 | C病院、外来 | 10,000円 | (b) | 可 | 10,000円 |
| 妻 | C病院の調剤薬局 | 15,000円 | (c) | 可 | 15,000円 |
| (d) | 計 | 55,000円 |
(a)30,000円+(b)10,000円+(c)15,000円=55,000円>35,400円(e)(自己負担限度額)
∴(d)55,000円-(e)35,400円=19,600円(支払われる高額療養費)
説明
(a)については、世帯合算の条件である21,000円を超えています。
(b)(c)については、それぞれ21,000円未満ですが、合計すると21,000円を超えます。(自己負担額の考え方5参照)
したがって、19,600円が高額療養費として、支払われます。
| 受診者 | 病院名・入院/外来 | 支払った医療費 | 合算 | 自己負担限度額 | 医療費総額 (保険適用分) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夫 | A病院、入院 | 300,000円 | (a) | 可 | 87,430円 | 1,000,000円 |
| 夫 | B病院、外来 | 2,100円 | 不可 | - | 7,000円 | |
| 妻 | D病院、外来 | 3,000円 | 不可 | - | 10,000円 |
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×0.01=87,430円(b)(自己負担限度額)
∴(a)300,000円(支払った医療費)-(b)87,430円=212,570円(支払われる高額療養費)
70歳から74歳までの人の自己負担限度額
| 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
|---|---|---|
|
現役並み3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント <多数回該当の場合 140,100円> |
|
|
現役並み2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000)×1パーセント <多数回該当の場合 93,000円> |
|
|
現役並み1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント <多数回該当の場合 44,400円> |
|
| 一般(※2) | 18,000円(※1) |
57,600円 <多数回該当の場合 44,400円> |
| 低所得者(※3) | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1(※4) | 8,000円 | 15,000円 |
まず、個人ごとに外来の限度額を適用し、その後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。現役並み所得者1、2、3の世帯及び一般の世帯は、過去12ヵ月以内に4回以上限度額に達した場合は4回目から多数回該当となり、限度額が下がります。
※1…8月~翌年7月の年間限度額は年間限度額144,000円
※2…現役並み所得者、低所得者1・2に該当しない人
※3…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人
※4…同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万6,700円で計算)を差し引いたときに0円となる人
【高額医療費の計算例】 70歳から74歳まで(一般課税世帯)
| 受診者 | 病院名・入院/外来 | 支払った医療費 | 外来+入院(世帯単位) | |
|---|---|---|---|---|
| 夫 | A病院、外来 | 3,000円 | (a) | 可 |
| 妻 | B病院、外来 | 13,000円 | (b) | 可 |
| 妻 | B病院、入院 | 57,600円 | (c) | 可 |
| 73,600円 | (d) | 高額医療費対象額 |
(a)3,000円+(b)13,000円+(c)57,600円=(d)73,600円>57,600円(e)(自己負担限度額)
∴(d)73,600円-(e)57,600円=16,000円(支払われる高額療養費)
| 受診者 | 病院名・入院/外来 | 支払った医療費 | 外来(個人単位) | |
|---|---|---|---|---|
| 夫 | A病院、外来 | 3,000円 | 不可 | |
| 妻 | B病院、外来 | 20,000円 | (a) | 可 |
| 20,000円 | (b) | 高額医療費対象額 |
(b)20,000円>(c)18,000円(自己負担限度額)
∴(b)20,000円-(c)18,000円=2,000円(支払われる高額療養費)
70歳から74歳の計算方法については、69歳以下の人のような合算条件はありませんので、保険適用分医療費を暦月ごとに加算し、自己負担限度額を超えた金額が高額医療費として支払われます。また、75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ2分の1となります。
限度額適用認定証
入院または、通院した時に「限度額適用認定証」を提示すると、同じ人が1つの医療機関窓口で支払うひと月の保険診療負担額が自己負担限度額までとなります。
また、住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、入院時の食事代についても減額されます。入院・外来で、ひと月の医療費が高額となる場合は、マイナ保険証または資格確認書をお持ちになり、交付申請を行ってください。発効期日は申請月の1日からとなります。
70歳から74歳までの所得区分が「一般」「現役並み所得者3」世帯の人はお持ちのマイナ保険証または資格確認書のみで病院等に受診します。
(限度額適用認定証は必要ありません)
オンライン資格確認ができる医療機関等では、マイナ保険証(または資格確認書)を提示し本人が情報提供に同意すれば、「限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が不要となります。
(引き続き、認定証の提示が必要な場合(住民非課税世帯の方が長期入院するとき等)があります。詳しくはお尋ねください。)
注意事項
- 事前に「限度額適用認定証」を申請しなかった場合や、病院に提示せずに通常の自己負担額を支払った場合でも、後から申請すれば高額療養費として払い戻されます。(病院に受診した日の翌日から2年以内の申請に限る)
- 限度額適用認定証は、加入している健康保険の種類で手続きをする窓口が異なりますので、太宰府市国民健康保険以外の保険(社会保険・建設国保・共済保険など)に加入している人は、加入している各健康保険の担当者にお尋ねください。
- 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
更新の実施
「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」は毎年8月1日に更新します。更新には手続きが必要です。なお、所得区分は住民税の課税状況によって変動する場合があります。
注意:国保税に納め忘れ(滞納)がある場合は更新することができない場合がありますので、ご注意ください。
外来年間合算
毎年8月1日から7月31日までの1年間にかかった外来の自己負担額を個人単位で合算し、年間上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給することで医療費の負担を軽減する制度です。70歳以上の方の高額療養費の月額の自己負担減限度額が引き上げられたことに伴い、年間を通して外来療養を受けている方の負担が増えないよう、新たに設けられました。
支給対象者
支給対象となられた場合(本市国保加入期間のみで外来の自己負担額が14万4千円を超えたことが分かる方)は、毎年12月から1月頃にご案内を世帯主の方へ送付します。
対象者:基準日時点での所得区分が「低所得1」、「低所得2」、「一般」世帯の方
基準日:毎年7月31日
計算期間:毎年8月1日から7月31日までの1年間
年間上限額:14万4千円
計算方法について
- 計算対象となる医療費は外来診療分のみです。
- 70歳以上の方の自己負担額を個人単位で合算します。
- 月ごとの高額療養費の支給を受けることができる場合は、自己負担額からその支給額を除きます。
- 計算期間内に他の医療保険(他市町村での国民健康保険も含む)から本市の国民健康保険に移られた場合は、以前加入されていた医療保険の窓口で自己負担額証明書の申請が必要です。
高額介護合算療養費制度
1年間に、病院で受診したときに支払った医療費と、介護サービスを受けたときに支払った介護サービス費の自己負担合計額が高額になり、限度額を超えた場合、申請により超えた分の払い戻しが受けられる制度です。
特定疾病療養受療証
高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に原因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担額は1カ月10,000円(人工透析を要する70歳未満の所得区分(ア)(イ)の人は20,000円)までとなります。