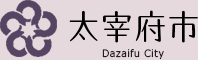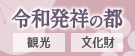本文
(受付終了)定額減税不足額給付金のお知らせ
下記給付金につきまして、申請期限となりましたので受付を終了しました。今後の受付はできませんのでご注意ください。
不足額給付
物価高騰による市民の負担増を踏まえ、令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした調整給付を支給しましたが、本来給付すべき額との差額等を不足額給付金として支給します。
太宰府市定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内 [PDFファイル/1.21MB]
対象者への書類はすでに発送していますが、対象者であっても書類が届かない場合があります。その場合、ご自身での申請書の提出が必要です。
詳しくは、「申請が必要な方」をご確認ください。
支給対象者
次の「不足額給付I(定額減税しきれず不足額が生じた方)」または「不足額給付II(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方)」に該当する方が対象です。
不足額給付I(定額減税しきれず不足額が生じた方)
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じる方。ただし、1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。
<給付対象となりうる方の例>
・ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、令和6年分推計所得税額(令和5年所得税額)>令和6年分推計所得税額(令和6年所得税額)となった方
・ 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分定額減税可能額(当初給付時)< 所得税分定額減税可能額(不足額給付時)となった方
・ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付II(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方)
「不足額給付I」とは別に、本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方については、個別に書類 の提示(申請)により、給付を支給できる場合があります。
以下のすべての要件を満たす方が支給となります。
・所得税額および個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外)
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない
<給付対象となりうる方の例>
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
支給額
支給額については、対象者によって金額が異なります。
※原則、対象者名義の金融機関の口座に振り込みます。
※通帳には「チョウセイキュウフキン」と印字されます。(令和6年度実施の定額減税調整給付金との関連のため今回の印字も同様としています。)
不足額給付I(定額減税しきれず不足額が生じた方)
「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額を給付します。
給付額算出方法
| 不足額給付額 | = |
本来給付すべき額 (※1万円単位で切り上げて算出) |
- |
令和6年度調整給付額 ※令和6年度調整給付受給の有無に |
|---|
「所得税分」の算出方法
| 定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数(注1)) |
- | 令和6年分所得税額 (定額減税前) |
= | 所得税分 (所得税分<0の場合は0) |
|---|
(注1)令和6年分所得税の扶養親族等の数は、令和6年12月31日時点の扶養状況で判断します。ただし、令和6年中における扶養親族等の死亡については、死亡の時の扶養状況で判断します。
「住民税分」の算出方法
| 定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数(注2)) |
- | 令和6年度個人住民税所得割額 (定額減税前) |
= | 住民税分 (住民税分<0の場合は0) |
|---|
(注2)令和6年度個人住民税の扶養親族等の数は、令和5年12月31日時点の扶養状況で判断します。なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(合計所得1000万円超かつ配偶者の合計所得が48万円以下の場合)については、令和7年度個人住民税所得割額から定額減税されます。
不足額給付II(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方)
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
※住民税所得割分または所得税分のいずれかのみ対象となる場合は3万円以内の個別の給付額となります。
支給時期
令和7年9月から順次支給
支給手続き
対象者には令和7年8月に書類を発送しています。
ただし、支給要件に該当する方のうち、下記< 3 申請書の提出が必要な方 >に該当する方は、ご自身での申請書の提出が必要となる場合があります。
※令和7年1月1日に太宰府市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日にお住まいの市区町村での給付となりますので、そちらでご確認ください。
1 「定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ」が届いた方(令和6年度当初調整給付を太宰府市から受給した方)
【令和7年8月8日に書類を発送しています。】
「定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ」に記載の振込先に支給しますので、原則手続きや申請は不要です。
振込口座の変更などを希望する場合には、令和7年8月22日(金)までに下記コールセンターにご連絡のうえ、以下の届出をご提出ください。
・支給口座登録等の届出(変更届) [PDFファイル/265KB]
2 「定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」が届いた方(支給対象者のうち、上記1に該当しない方)
【令和7年8月22日に書類を発送しています。】
「定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」の記載内容をご確認のうえ、振込口座など必要事項を記入し、添付書類と一緒に同封の返信用封筒にてご返送ください。
支給決定後に指定口座まで振り込みます。
確認書の提出期限:令和7年10月31日(金)まで
【お詫び】文言の訂正について
支給確認書の記載内容の誤りがございました。大変ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、次のとおり訂正いたしますので読み替えください。
〇1ページ目の誓約・同意事項欄
誤:添付している資料以外に収入を使用する書類はありません。
正:添付している資料以外に収入を証する書類はありません。
〇2ページ目の提出書類欄『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』
誤:※ 「(2)給付金の振込先口座の変更等」で3をチェックした場合のみ添付してください。
正:文言の削除
なお、支給確認書に該当する方は受取口座を確認できる書類の写しの提出は必須です。
3 申請が必要な方(「支給のお知らせ」や「確認書」が届かなかったが給付要件を満たす方)
支給対象者であっても、以下の場合など個人の状況によっては不足額給付の対象判定ができないため、「定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ」や「定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」が届かない場合があります。その場合は、ご自身で申請書を提出いただく必要があります。
- 不足額給付の対象者のうち、令和6年1月2日以降に太宰府市に転入された方
- 不足額給付の対象者のうち、市外にお住いの事業主の専従者となっている方
申請書については、以下よりダウンロードください。また、太宰府市定額減税補足給付金(不足額給付)窓口(太宰府市役所4階)でも配布しています。
申請書の提出期限:令和7年10月31日(金)まで
・(申請書の方向け)不足額給付のご案内 [PDFファイル/910KB]
【不足額給付I申請対象の方】
・不足額給付I型申請書(記入例) [PDFファイル/735KB]
【不足額給付II申請対象の方】
・不足額給付II型申請書 [PDFファイル/377KB]
・不足額給付II型申請書(記入例) [PDFファイル/677KB]
給付金をかたった詐欺には、ご注意ください
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
市役所や税務署などの官公庁から、電話やメール、サイトなどによりATM(現金自動預払機)の操作を依頼すること、給付のために手数料の振込みを求めること、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対ありません。
このような不審な電話やメール、郵便物等を受け取った場合は、警察相談専用電話(♯9110)にお電話いただくか、お近くの警察署などにご相談ください。
お問い合わせ
太宰府市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
電話:0570-550-255
受付時間:午前8時30分~午後5時(土日祝日を除く)
※書類の不備等でお電話をすることがあります。その際は、「092-921-2121(市役所代表電話)」または「092-408-5800」よりお電話いたします。
不足額給付についてのよくあるご質問
制度
Q1-1 「個人住民税を課税している自治体」と「住民登録している自治体」とが異なる場合は、不足額給付はどこから支給されますか
令和7年度個人住民税を課税している自治体から支給されます。
Q1-2 個人住民税が課税された後に住民登録を異動した場合は、不足額給付はどこから支給されますか
個人住民税は、原則として1月1日現在の住所地の自治体で課税され、その後に住民登録を異動しても課税する自治体は変わりません。
よって、令和7年度個人住民税が太宰府市で課税された方は、その後に住民登録を異動しても、不足額給付を支給する自治体は、太宰府市のままです。
Q1-3 個人住民税所得割とは何ですか
個人住民税には、広く均等に負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく所得割があります。
令和6年度個人住民税の定額減税は、所得割が課税された方が対象となり、所得割からのみ減税されました。
Q1-4 控除対象配偶者および扶養親族とは、誰のことですか
税法上の「扶養親族」となっている方です(16歳未満の年少扶養親族も含みます)。
※同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者のことを控除対象配偶者といいます。
※国外居住者は除きます。また、配偶者特別控除の適用を受ける配偶者は該当しません。
※青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている方および白色申告者の事業専従者の方は該当しません。
Q1-5 税法上の扶養人数(被扶養者数)の確認方法はありますか
個人住民税の通知書、源泉徴収票または確定申告書で、届出状況を確認することができます。
Q1-6 令和6年度個人住民税と令和6年分所得税の被扶養者の数が異なる場合は、どちらの扶養人数で定額減税可能額は計算しますか
個人住民税は令和5年12月31日時点、所得税は令和6年12月31日時点の扶養人数と、それぞれ時点が異なります。定額減税可能額は、どちらか一方の扶養人数を使用するのではなく、税種別ごとに各々の扶養人数を基に計算します。
Q1-7 不足額給付は、課税または差押をされることがありますか
不足額給付は課税されません。また、差押は禁止されています。
支給対象者
Q2-1 令和5年12月31日時点では親の扶養に入っていましたが、就職して令和6年分所得税が課税されました。不足額給付の対象になりますか。
令和5年は無収入だった場合でも令和6年分所得税が課税された場合は、所得税が定額減税の対象となります。また、減税しきれなかったときは、個人住民税分と合わせて、不足額給付の対象となります。
Q2-2 外国人は、不足額給付の対象となりますか
外国人か日本人かに関わらず、令和7年1月1日時点で国内居住者であれば、対象となる場合があります。
Q2-3 生活保護受給者は、不足額給付の対象となりますか
生活保護の受給の有無に関わらず、令和7年1月1日時点で国内居住者であれば、対象となる場合があります。
Q2-4 条例により令和6年度個人住民税が免除された場合は、不足額給付の対象となりますか
条例により令和6年度個人住民税が免除されている場合でも、令和7年1月1日時点で国内居住者であれば、対象となる場合があります。
Q2-5 源泉徴収票の摘要欄に控除外額が記載されていた場合は、不足額給付が支給されますか
令和6年度調整給付の対象でない場合、もしくは、控除外額が令和6年度調整給付の額を上回っている場合は、不足額給付の対象となることが見込まれます。
なお、複数か所からの収入がある場合には、全ての課税状況から総合的に判断する必要があります。
Q2-6 個人住民税と所得税のどちらか一方だけでも対象になると、不足額給付が支給されますか
どちらか一方だけでも対象になると、不足額給付が支給されます。
なお、令和6年度調整給付の対象だった場合は、個人住民税と所得税の控除不足額を合算して1万円単位に切り上げた額が、調整給付支給額を上回る場合に限り、不足額給付が支給されます。
Q2-7 非課税の者でも不足額給付を受けることができる場合があると聞きましたが、どのような場合ですか
定額減税や低所得世帯向け給付金のいずれも対象とならなかった方が対象です。詳細は、不足額給付IIをご確認ください。
Q2-8 令和6年中に子どもが生まれた場合は、対象になりますか。
所得税分については対象となりますが、個人住民税分については対象となりません。
※所得税分は、令和6年12月31日時点の状況で判断となりますが、個人住民税分は、令和5年12月31日時点の状況で判断するため
支給額
Q3-1 令和6年度調整給付の案内が届きましたが、申請を漏らしていました。未受給の令和6年度調整給付の分も合わせて不足額給付として受給できますか
未受給の令和6年度調整給付分を受給することはできません。
Q3-2 源泉徴収票に記載されている「控除外額」と支給金額が違います。
源泉徴収票の「控除外額」は、不足額給付の額を算出する際に用います。
ただし、「控除外額」に記載された金額と不足額給付額の額は必ずしも一致するものではありません。
<控除外額=不足額給付とならない例>
・令和6年に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」の対象となっていた場合
・源泉徴収票の記載以外にも収入がある場合 等
Q3-3 不足額給付(II型)の対象となっているが、扶養している家族の分の金額が入っていません。
不足額給付(II型)の対象となる方は、扶養親族の人数は算定に含まれません。
手続き
Q4-1 太宰府市から不足額給付対象者に送る書類は、いつ・どこに届きますか
令和7年8月下旬頃(詳細未定)に、個人住民税の納税通知書の送付先または住民登録している住所(※納税通知書の送付先を優先)に送付する予定です。
Q4-2 自身での申請書の提出が必要となる場合があるのはなぜですか
不足額給付は令和7年度個人住民税を課税している自治体から支給されますが、不足額給付算定には令和6年度個人住民税の課税情報が必要となります。そのため、令和6年度個人住民税が太宰府市以外の自治体から課税されている場合など、太宰府市で課税状況等を把握できない場合は、不足額給付の対象であるかの判定ができないため、ご自身での申請が必要となります。
定額減税、令和6年度調整給付について (注)令和6年度調整給付は終了しています
Q5-1 定額減税された額の確認方法はありますか
個人住民税の通知書、源泉徴収票または確定申告書で確認することができます。
Q5-2 源泉徴収票の摘要欄に記載されている控除済額や控除外額とは何ですか
控除済額とは、その収入に対する所得税から定額減税された金額です。控除外額とは、減税しきれなかった金額です。
Q5-3 源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか
源泉徴収票には、所得税の定額減税についてのみが記載されているためです。
個人住民税の定額減税については、令和6年度個人住民税の通知書をご確認ください(Q5-1参照)。
【定額減税可能額】
所得税………3万円×(本人+扶養親族数)
個人住民税…1万円×(本人+扶養親族数)
Q5-4 源泉徴収票の摘要欄に控除済額や控除外額が記載されていない場合は、どのようにして定額減税の状況など確認したらよいですか
ご自身で確認するためには、確定申告によって定額減税額を確定させる必要があります。詳しくは定額減税と確定申告(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。
Q5-5 令和6年度調整給付とは何ですか
令和6年度に実施した定額減税において、速やかな給付を目的に、「令和6年度個人住民税所得割額」と令和6年分所得税額が確定する令和6年12月31日を待たずに令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」から定額減税しきれないと見込まれる額を支給した給付金のことです。
Q5-6 令和6年度調整給付の支給額の確認方法はありますか
給付に際して送付した「調整給付の支給決定について(通知)」で確認することができます。
なお、令和6年度調整給付の対象でない方は、支給額0円です。
Q5-7 令和6年度に調整給付の支給を受けましたが、年末調整で全額減税されました。受給した調整給付は返納が必要ですか
令和6年度調整給付が過大に支給されていた場合でも返納は求めません。
Q5-8 大学生や専門学校生で一人暮らしの場合は、定額減税や令和6年度調整給付の対象となりますか
アルバイト収入などがあり、個人住民税所得割または所得税が課税された場合は、定額減税の対象となり、減税しきれないと見込まれたときは令和6年度に調整給付を支給しています。
なお、令和7年1月1日時点で国内居住者であれば、不足額給付の対象となる場合があります。
Q5-9 所得税や個人住民税の定額減税についての問合せ先はどこですか
それぞれ次のホームページでご確認ください。
・所得税の定額減税について…定額減税特設サイト(国税庁ホームページ)<外部リンク>
・個人住民税の定額減税について…令和6年度個人市民税(所得割)の定額減税(特別税額控除)について