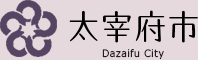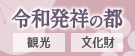本文
後期高齢者医療制度を紹介します
平成20年4月1日から「後期高齢者医療制度」がはじまりました。後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者の方々の心身の特性に応じた医療を提供するとともに、将来にわたって国民皆保険を堅持するため、その医療費を国民全体で支える制度です。
注意:マイナンバー導入に伴い、各種手続きに必要な本人確認等の書類が変更となっています。
詳しくは平成28年1月1日からマイナンバー記載に伴い必要になるマイナンバーの本人確認をご覧ください(PDF:48KB)
対象者
次の表のいずれかに該当する人は、それまで加入していた健康保険(国民健康保険、健康保険組合、共済組合など)から、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
| 対象となる人 | いつから | 手続き |
|---|---|---|
| 75歳以上の人すべて | 75歳の誕生日から | 手続きはありません。 誕生日の前月末に「後期高齢者医療資格確認書」を送付します。 |
| 65歳から74歳の人で、申請により広域連合が一定の障がいの状態(注意)にあると認めた人 | 認定日から | 市役所窓口での手続きが必要です |
注意:認定を受けられる障がいの程度
- 国民年金法等障害年金1・2級
- 身体障害手帳1・2・3級および4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級
- 療育手帳A(重度)
保険料
75歳以上の被保険者は個別に保険料を納めます。
これまで保険料を納付する義務が無かった会社の健康保険の被扶養者であった人や、国民健康保険の加入者で世帯主でなかった人も保険料を納めます。
※国民健康保険での口座振替の登録は引き継がれないため、口座振替を希望する人は新たに手続きが必要です。
保険料の計算方法
後期高齢者保険料は加入した月から保険料が計算されます。
保険料(最高80万円)=均等割額60,004円+所得割額(総所得金額等-基礎控除額)×所得割率11.83%
注意:おもな「基礎控除後の総所得金額等」の算定方法
- 給与所得の場合:(給与収入金額-給与所得控除額)-基礎控除額
- 公的年金所得の場合:(年金収入金額-公的年金等控除額)-基礎控除額
- その他の所得の場合:(収入金額-必要経費)-基礎控除額
基礎控除額とは、合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円ですが、2,400万円を超える場合は所得金額によって異なります。
保険料の納付方法
保険料の算定開始月は次のとおりです。
| 算定開始月 | 納付開始月 | 納付方法 | |
|---|---|---|---|
| 75歳年齢到達者 | 誕生月から算定 | 誕生月の翌月 | 納付書、翌年度4月または10月から年金差引 |
| 65歳から74歳の加入者 | 加入月から算定 | 加入月の翌月 | 納付書、翌年度4月または10月から年金差引 |
| 転入者 | 転入月から算定 | 転入月の翌月 | 納付書、翌年度4月または10月から年金差引 |
翌年度以降の保険料納付方法は次表のとおりです
| 特別徴収 (年金差引) |
年金を年額18万円以上受給されている人
|
|---|---|
| 普通徴収 (納付書または口座振替) |
上記以外の人 |
保険料の仮徴収(年金差引のみ)
保険料を年金差引で納めている人は、4月・6月・8月の差引額は保険料確定前のため、2月の差引額と同額を引落します。ただし、次に該当する人は差引をおこないません。
- 1月末までに「特別徴収の停止手続」を行った人
- 介護保険料との合計額が年金支給額の2分の1を超えた人
また、翌年度の保険料は10月・12月・2月の年金差引で精算を行います。
特別徴収から普通徴収(口座)への変更
年金差引で保険料を納めている人は申し出により口座振替に変更することができます。
注意:納付書払いへの希望変更はできません。
- 持ってくる物
- 希望する金融機関の預金通帳等
- 金融機関等の届出印
- 手続き場所
太宰府市役所 1階 国保年金課(6番)
保険料の軽減
世帯主(後期高齢者医療制度に加入・非加入問わず)および被保険者の「総所得金額の合計額」により均等割額が7割・5割・2割軽減されます。
注意:世帯の中に所得が不明な人(未申告者)がいる世帯は減額ができません。
| 均等割額の軽減割合 | 軽減後の均等割額(年額) | 同一世帯(注意1)内の被保険者及び世帯主の軽減対象所得金額(注意2)の合計額 |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 18,001円 |
【基礎控除額】43万円 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 5割軽減 | 30,002円 |
【基礎控除額43万円+30.5万円×被保険者数】 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 2割軽減 | 48,003円 |
【基礎控除額43万円+56万円×被保険者数】 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
注意1:同一世帯とは、4月1日時点の世帯(年度途中で75歳になる方、県外からの転入者、障害認定による加入者等はその時点)の世帯が基準となります。
注意2:「軽減対象所得金額」とは、基本的に総所得金額と同額ですが、満65歳以上の方の公的年金については、「公的年金収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円」となります。また、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
注意3:太字部分の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得【給与収入55万円超】または公的年金等に係る所得【公的年金等収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)】を有する場合に適用されます。
社会保険の被扶養者であった方の保険料の軽減
後期高齢者医療制度に加入される前日に、社会保険(協会けんぽ、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合)の被扶養者であった方は、保険料が軽減されます。
| 軽減割合 | 軽減後の保険料額(年額) |
|---|---|
| 所得割額:無し 均等割額:5割軽減 |
30,002円 |
注意1:保険料の軽減措置は、今後、段階的に見直されることがあります。
注意2:均等割額の7割軽減対象者は、7割軽減が優先されます。
注意3:後期高齢者医療保険加入後、2年間に限ります。