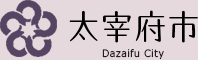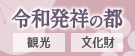本文
土地に対する課税
評価のしくみ
地目
地目は、宅地、田及び畑(あわせて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産の評価上の地目は、登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。宅地の評価は地価公示価格等の7割を目途に行います。
地目別の評価方法
宅地の評価方法(市街地宅地評価法の仕組みについて)
1.用途地区及び状況類似地域の区分
宅地の利用状況等に基づいて用途地区を区分し、その用途地区を、さらに状況が概ね類似する地域(状況類似地域)ごとに細区分します。
2.主要な街路の選定
状況類似地域ごとに、主要な街路を選定します。
3.標準宅地の選定
主要な街路に沿接する宅地の中から、標準宅地を選定します。
4.主要な街路の路線価の付設
選定された標準宅地について、地価公示価格等の7割を目途に適正な価格を求め、標準宅地に沿接する主要な街路に路線価を付設します。
5.その他の街路の路線価の付設
主要な街路から比準(街路の状況などを比較)して、その他の街路に、路線価を付設します。
6.各筆の評価
路線価を基礎として、固定資産評価基準に定められた画地計算法により、土地の奥行や間口その他形状などの個別要因を考慮に入れて、各筆の評価をします。
農地、山林の評価方法
原則として、宅地の場合と同様に、標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。ただし、市街化農地や農地転用許可を受けた農地などについては、状況が類似する宅地などの評価額を基準として求めた価格から、造成費を控除した価格によって評価します。
路線価等の公開
土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価を市役所税務課にて公開しています。(無料)
また、全国地価マップ<外部リンク>からもご確認いただけます。
路線価とは?
路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(間口、奥行、形状など)に応じて求められます。
注意: 固定資産評価に用いる路線価は固定資産税路線価であり、相続税路線価とは異なります。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要があることから、その面積の広さなどにより、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額(都市計画税は3分の1)とする特例措置があります。
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地になります。
その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額(都市計画税は3分の2)とする特例措置があります。
特例措置の対象となる住宅用地の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
| 家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
|---|---|---|---|
| イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
| ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
| ロ | ハ以外の併用住宅 | 2分の1以上 | 1.0 |
| ハ | 地上5階以上の準耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
| ハ | 地上5階以上の準耐火建築物である併用住宅 | 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
| ハ | 地上5階以上の準耐火建築物である併用住宅 | 4分の3以上 | 1.0 |
宅地の税額の求め方
住宅用地
固定資産税額は、次のとおり求められます。
課税標準額(注意1)×税率(1.4パーセント)=税額
(注意1)
評価額に6分の1又は3分の1を乗じた額(以下、Aとします。)
200平方メートル以下の小規模住宅用地は6分の1、200平方メートルを超えるその他の住宅用地は3分の1となります。
ただし、A(本来の課税標準額)が以下の額を超える場合には、以下の額が課税標準額となります。
前年度課税標準額+A×5パーセント
ただし、上記により計算した額がA×20パーセントを下回る場合には、A×20パーセントが課税標準額となります。
商業地等の宅地
固定資産税額は、次のとおり求められます。
課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額
ただし、評価額の70パーセントと比べて前年度課税標準額が以下の場合の土地については、以下の額が課税標準額となります。
- 前年度課税標準額が評価額の60パーセント以上70パーセント以下の場合、前年度課税標準額と同額に据え置きます。
- 前年度課税標準額が評価額の60パーセント未満の場合、前年度課税標準額+評価額×5パーセント
- 前年度課税標準額が評価額の70%を超える場合、評価額の70パーセント
宅地の税負担調整措置について
平成6年度の地方税法改正により、全国的にばらつきがあった宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格の7割を目途とする見直しが行われました。この評価替えによって税負担が急増しないようにするため、段階的に課税標準額を引き上げ、評価額に近づける措置をとりました。これを負担調整措置といいます。
個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示す値を負担水準といい、以下の式で求められます。
負担水準(パーセント)=前年度課税標準額÷今年度評価額×100