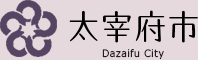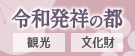本文
わたしたちの手でしあわせをひとつに第67集 インタビュー 矢ケ部紋可さん(読み上げ用)
矢ケ部 紋加さんインタビュー
バドミントンを始めたきっかけ
小学校1年生のときに、きこえない人のバドミントンクラブができて、参加したことがきっかけです。ろう(生まれた時から、または幼児期からきこえない人。主に手話を使用する人が多い)の先輩でデフリンピックに出場する方がいて、いつか自分もデフリンピックに出場したいと意識するようになりました。
環境の変化
今年(2024年)就職して、県外で生活しています。大学生のときは、練習時間の確保、体力面、指導者が少ないことの3つが課題でした。今は15時までの勤務なので練習時間の確保ができています。勤務後、すこし休んで夕方からの練習に向かうことができるので、気持ちにゆとりができました。また、コーチに指導してもらえることで自分の技術の向上につながっています。今の環境はとても充実しています。
日本代表になって変わったこと
高校2年生から日本代表に選ばれるようになりました。日本代表になってすぐにアジア大会があり出場しましたが、そのとき全試合負けてしまったんです。それが今までで一番悔しかった出来事です。しっかりがんばりたい、リベンジしたいと思ったその経験が、意識が変わったときだと思います。
海外へ行って感じた日本とのちがい
前回のデフリンピック(ブラジル大会)に出場したとき、ブラジルの方たちは、障がいがあることをプラスにとらえているように見えました。堂々としていて障がいがあるように見えません。日本では、自分たちは障がいがあるからと、すこし遠慮がちになる場面が多い気がします。
デフバドミントンの情報保障について
審判には手話通訳が横について通訳しています。また、ジェスチャーで審判が伝えてくれることもあります。手話ができる審判の方も半数くらいいます。試合のときは補聴器をはずして行うというルールがあり、練習の時から補聴器をはずしてプレーしています。反応がすこし遅れるので、ダブルスの時はペアの人とよくコミュニケーションをとるように気を付けています。また、視野を広げてよく見るようにしていて、視野を広げるためのビジョントレーニングを行っています。きこえない人はよく目を使うので視野を広げることは大事です。
お互いを知ろうとする気持ちを大切に
いま、手話を使う人が増えてきているなと感じています。先日デフバドミントンの大会があった時に、審判の方はきこえる方でしたが、手話を使ってくれました。また、飲食店に行った時も、お店の方が手話で「ありがとう」と言ってくれました。相手が歩み寄ってくれるということがうれしいです。
これからデフリンピックに向けて、もっと手話が広まって、障がいのありなしにかかわらずお互いが積極的にコミュニケーションをとろうとする気持ちを持てるようになるといいなと思います。
読んでいる方へ
関東に引っ越して、新しく知り合った方たちと話すときに、出身はどこ?と聞かれて「太宰府です」と答えると、「知ってる!」「いいところだよね!」とたくさん言われます。太宰府市出身であることを誇りに思って、これからも練習に励んで、みなさんに良い結果を報告できるようにしたいと思っています。
おまけ
太宰府のことでは食べ物の話題も盛り上がります。太宰府の食べ物で有名なのは梅ヶ枝餅や梅の実ひじきですね。あと、福岡の食べ物では時々うまかっちゃんが食べたくなります。関東では販売していないので、実家から送ってもらっています。
プロフィール
矢ケ部 紋可(やかべ あやか)さん
株式会社ゼンリンデータコム
第24回夏季デフリンピック バドミントン混合団体戦銀メダル、女子ダブルスベスト4