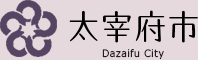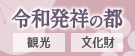本文
支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起
「特別法人支援団体」といった公的に存在するかのような名称をかたり、消費者に「80億円の支援金を給付する」旨のメールを送り、消費者が支援金の給付手続を進めると、支援金を受け取るためには3,000円の電子マネーカードの購入が必要などと説明され、これに応じて電子マネーを購入し事業者に送金するも、結局支援金を受け取ることができない、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、公的に存在するかのような名称をかたる事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成 21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
参考:消費者庁『支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起 [PDFファイル/2.17MB]』
1.本件で使用されていた名称等
今回の注意喚起の対象である本件事業者が使用した名称は、下表のとおりであり、その実体はいづれも不明です。
| 本件で使用された名称 |
| 特別法人支援団体 |
| 生活復興支援窓口 |
| NPO団体の支援機構 |
| 厚労省 |
(注)「特別法人支援団体」、「生活復興支援窓口」、「NPO団体の支援機構」という公的に存在するかのような名称は、架空又は実在の機関とは関係のない機関名です。「厚労省」とかたる事業者と、国の行政機関である厚生労働省とは関係がありません。
2.具体的な事例の内容
(1)公的に存在するかのような名称をかたって支援金を給付するといったメールが届きます。消費者が使用するスマートフォンに、突然、「特別法人支援団体」といった公的に存在するかのような名称をかたる機関から、下表のように、消費者に支援金が給付されるかのようなメールやSMS(ショートメッセージサービス)が送られてきます。
| 本件で使用された名称 | 支援給付金の説明事項 |
|---|---|
| 特別法人支援団体 | 特別法人支援団体で管理している口座に支援金(80億)が振り込まれました。こちらの支援金(80億)は本来、貴方様がお受取り頂く支援金(80億)となります |
| 生活復興支援窓口 |
【全国生活復興支援金】のご案内 全国生活復興支援金(LINE登録)はコチラ |
| NPO団体の支援機構 | 支援金(8,800万円+毎月50万円)の出金が許可されます!コレで最寄りのATMで感動の結果を見て頂くことになりますからね!本当におめでとうございます! |
| 厚労省 | 厚労省機密費による特例:特別支援の受取方法について |
(2)消費者が支援金の給付手続を進めていくと、本件事業者から支援金を受け取るためには手数料が必要などと説明されます。
(3)消費者は、手数料として電子マネーを購入して送金するも、更なる金銭の要求がされ、支援金は給付されません。
消費者は、支援金の給付を受けるため、手数料として3,000円の電子マネーを購入 し送金したところ、「1万円の追加払で支援金が受け取れる」 などと、追加送金を指示されます。
消費者が拒否していると「この支援金は、国がやっているもので安心である」 「間違いなく支援の受け取りができる」 などと、追加送金を求められます。
その後、本件事業者とやり取りを行うものの、追加払が要求されるのみで、結局、 支援金が給付されることはありませんでした。
消費者庁から皆様へのアドバイス
送金前に相談しましょう
送金してしまった後では取り戻すことは困難です。少しでも怪しいと感じたら、送金前に、一人で判断することなく、まずは家族や友人、同僚等に相談しましょう。
このほかに、消費者ホットライン「188(いやや!)」番や警察相談専用電話「#9110」番等の相談窓口に相談しましょう。
うまい話には裏があります。詐欺を疑いましょう
今回悪用されたものに限らず、公的機関等を名乗る者から、メールで突然「支援金が振り込まれました」、「支援金の受取は期間限定」などと支援金が給付されるかのようなうまい話があったとしても、そこには裏があります。
「支援金を受け取るにはまず〇〇円を支払ってください」は典型的な詐欺の手口です。
身に覚えがないメールには返信しない、メールに添付のURLにアクセスしないようにしましょう。
知らない差出人からのメールや、心当たりのないメールには安易に返信しないようにしましょう。
また、メールに添付のURLに安易にアクセスすると、偽サイト等に誘導され、個人情報や金銭をだまし取られる危険があるので無視をしましょう。
相手が信用できるかどうか事前に調べ「本物か?」と疑ってみましょう
まず冷静に相手の名前、会社名等をインターネットで検索することで、過去のトラブル事例や詐欺の報告が見つかることがあります。公式サイトや公的機関の情報を活用し、信頼できる相手かどうかを見極めることが、被害を未然に防ぐ第一歩です。疑うことも必要です。