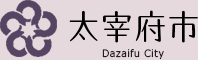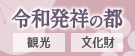本文
子宮頸がん予防(ヒトパピローマウイルス(HPV))ワクチン接種を行っています
子宮頸がん予防(ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防)ワクチン
定期接種の勧奨再開について
子宮頸がんの原因を予防する、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの予防接種について、平成25年6月から、厚生労働省の勧告に基づき、積極的な勧奨を差し控えていましたが、令和3年11月26日付け厚生労働省の通知により、積極的な勧奨を再開することになりました。
これは、国の検討部会において、HPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたためです。
接種を希望される場合は、保護者様とお子さんにてワクチンの有効性やリスク等を十分にご理解いただいたうえで接種してください。
子宮頸がんの現状
子宮頸がんは、高リスク型(発がん性)のヒトパピローマウイルス(HPV)が持続感染し、感染から数年~十数年の後に前癌病変の状態を経て発症すると考えられています。
ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染は、ほとんどが性的接触によるもので、ヒトパピローマウイルス(HPV)に感染すること自体は特別なことではなく、性交経験がある女性であれば誰でも感染する可能性がありますが、子宮頸がん発症にまで至るのは稀です。
子宮頸がんは、国内では年間約11,000人が発症し、年間約2,900人の死亡が報告されています。
子宮頸がんに対し私たちができることは、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン接種と子宮頸がん検診の受診の2つです。
HPVワクチンは100%がんを防ぐものではありません。20歳を過ぎたら定期的に子宮頸がん検診を受けることが大切です。
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防ワクチンの種類
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防ワクチンは、現在世界的に使用されていますが、国内で認可されている予防ワクチン(ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防ワクチン)は、3種類あります。国内外で子宮頸がん患者から最も多く検出されるHPV16、HPV18型に対する抗原を含む2価ワクチン(サーバリックス)と尖圭コンジローマや再発性呼吸器乳頭腫症の原因ともなるHPV6型、HPV11型も加えられた4価ワクチン(ガーダシル)、HPV31型、33型、45型、52型、58型も加えられた9価ワクチン(シルガード)があります。
定期接種の対象者
接種日現在、本市に住民票があり、高校1年生相当から小学校6年生(平成21年4月2日~平成26年4月1日生まれ)までの女子の方
標準的な接種時期:中学1年生相当(平成24年4月2日~平成25年4月1日生まれ)
| 相当学年・年齢 | 生年月日 |
|---|---|
| 小学6年生(12歳)相当 | 平成25年4月2日から平成26年4月1日生まれまで |
| 中学1年生(13歳)相当 | 平成24年4月2日から平成25年4月1日生まれまで |
| 中学2年生(14歳)相当 | 平成23年4月2日から平成24年4月1日生まれまで |
| 中学3年生(15歳)相当 | 平成22年4月2日から平成23年4月1日生まれまで |
| 高校1年生(16歳)相当 | 平成21年4月2日から平成22年4月1日生まれまで |
接種料金
公費につき無料(定期接種の対象者以外は任意接種となり有料です。)
接種回数と接種スケジュール
| ワクチン名 | 2価ワクチン(サーバリックス) | 4価ワクチン(ガーダシル) | 9価ワクチン(シルガード) | 9価ワクチン(シルガード) |
|---|---|---|---|---|
| 接種回数 | 3回 | 3回 | 2回(初回接種時の年齢が15歳未満) | 3回(初回接種時の年齢が15歳以上) |
|
標準的な接種間隔 |
1回目 2回目(1回目から1か月以上の間隔を空ける) 3回目(1回目から6か月以上の間隔を空ける) |
1回目 2回目(1回目から2か月以上の間隔を空ける) 3回目(1回目から6か月以上の間隔を空ける) |
1回目 2回目(1回目から6か月以上の間隔を空ける) ※但し、2回目の接種が1回目から5か月未満の場合は、3回目の接種が必要になります。 |
1回目 2回目(1回目から2か月以上の間隔を空ける) 3回目(1回目から6か月以上の間隔を空ける) |
|
上記の接種間隔をとれない場合 |
1か月以上の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて1回接種 |
1か月以上の間隔をおいて2回接種後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて1回接種 |
5か月以上の間隔をおいて2回接種 |
1回目から1か月以上の間隔をおいて2回目を接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種。 |
2価または4価ワクチンと9価ワクチンとの交互接種について
同じ種類のHPVワクチンで接種を完了することが原則となりますが、すでに2価あるいは4価ワクチンを用いて定期接種の一部を終了した者が残りの接種を行う場合には、適切な情報提供に基づき、医師と被接種者等がよく相談した上で、 9価ワクチンを選択しても差し支えないこととされています。
接種を受ける方法
事前に医療機関と連絡を取り、接種日等を相談のうえ予約してください。
医療機関へは母子健康手帳及び本人確認ができるもの(健康保険証等)をお持ちいただき接種を受けてください。
原則は保護者が同伴してください。
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を受けた方へ
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
救済制度
子宮頸がん予防ワクチンは、予防接種法に基づいた定期接種です。接種後に健康被害が発生した場合、予防接種法に基づく救済の対象になります。
「予防接種健康被害救済制度」(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
子宮頸がん検診について
20歳を過ぎたら、定期的に子宮頸がん検診を受けましょう。
ワクチン接種を受けた場合でも、免疫が不十分である場合や、ワクチンに含まれている型以外の型による子宮頸がんの可能性もあり得ますので、20歳を過ぎたら定期的に子宮頸がん検診を受けることが大切です。
参考
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症(子宮頸がんとヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン) 厚生労働省ホームページ<外部リンク>
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンQ&A 厚生労働省ホームページ<外部リンク>