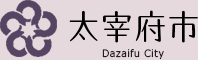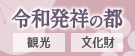本文
施政方針(平成31年第1回(3月)定例会・平成31年2月21日)
本日ここに、平成31年第1回定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては大変ご多用の中をご参集賜り、厚く御礼を申し上げます。
この定例会は、平成31年度の市政の根幹となります予算案をはじめ、主要施策並びに条例案をご審議いただく重要な議会ととらえております。
議案提案に先立ちまして、今後の市政運営に臨む私の所信の一端をご説明し、議員各位や市民の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。
昨年一月末に市長に就任してから一年が経過致しました。この間まずは本市の未曾有の混乱からの脱却を第一義と考え、議員各位、職員諸氏、市民の皆様との信頼関係を再構築するため私なりに腐心して参りました。その思い一心で、日々議会への対応や職員との協働、市民との交流に最大限努めて来たつもりでございます。お陰様でようやく所期の目的を達成しつつあり、またその過程においても肝いりの政策実現に向け一つ一つ着実に布石を打ち、本市のこれまでの在り方や課題、これからの可能性などを見極める努力も続けてきたところであります。
本年は特に平成納めの年であり、新たな元号が始まる節目の年でもあります。これまでの先人の功績に思いを致し、かつての混乱も一つの教訓として、迎えた本年を「新生太宰府元年!」と銘打ち、その名にふさわしい意欲的な市政運営を進めて参ります。また、3つの工程と7つのプランや第五次太宰府市総合計画後期基本計画などを基にしたこれまでの所信表明や施政方針、経営方針や予算編成方針をさらに深化・拡充し、斬新な歳入増加策や歳出削減策を創造し、市内外での積極的財政投資と地域の所得アップの好循環をもたらすような新たなビジョンにつなげていく、「実践と構想の年」に位置付けます。そのためにも、常に市民目線を心がけ、積極的に市民の声に耳を傾ける現場主義を徹底し、広域的視野と中長期的視点を常に持ち、前例にとらわれない自由な発想と創意工夫を促し、旺盛なチャレンジ精神を発揮できる、風通しの良い活力ある職場を心がけます。
そして早速「新生太宰府元年!」にふさわしい幸先良いニュースが次々と飛び込んでおります。元日には西鉄太宰府駅の27年ぶりのリニューアル式典が盛大に開催されました。本市の観光の玄関口としてお客様を更にもてなし、地域の活性化にも大いなる効果をもたらすものと期待されます。1月2日にはNHK「ブラタモリ×鶴瓶の家族に乾杯新春スペシャル」で本市が特集されました。全国各地で視聴され、多くの反響をいただいております。今後の更なる誘客や新たな観光手段の掘り起こしにも繋がると期待しております。1月24日には、古民家を活用した高級宿泊施設とレストランが太宰府天満宮周辺に本年夏頃にオープンするとの発表がありました。2月1日より大宰府政庁前に供用を開始したバス専用駐車場とも合わせ、本市の観光の回遊性を向上させ経済効果を高める起爆剤と致します。また、運営者は西鉄などが出資する本市に本社機能を持つ新会社で、その税収効果にも期待しております。この動きにおいて、本市と観光協定を結ぶ三井住友銀行に大きな役割を果たして頂いており、連携が機能してきた証左ともとらえております。1月25日には、第91回選抜高校野球大会の選考会において地元筑陽学園高校の夢の甲子園出場が決定致しました。昨秋の九州大会を制し、明治神宮野球大会でもベスト4に勝ち進むなど、本大会でのますますの活躍が期待されるところです。市としましても、選手の皆さんが伸び伸びとプレーできるよう最大限の支援を行って参ります。こうした追い風を生かし、本市の更なる発展に繋げて参ります。
さて、この度提案致します平成31年度当初予算案は、私にとりまして編成当初から手掛けた初めての予算案であります。まず予算編成に先駆け、新たなチャレンジとして「方針共有」「業務改善・スクラップ」「選択と集中」の三本の矢を掲げ、マネジメントサイクルを推進して参りました。まず「方針共有」として、市を取り巻く様々な課題に対し全庁一丸となって対応すべく、新たに掲げました経営方針・予算編成方針につきまして三役・部長・課長合同会議並びに係長・一般職員も対象にした自主研究の場で自ら語りかけ、共有を図りました。また、厳しい財政状況においてより少ない予算や定数でも運営できる体質に変えていくことができるよう、「業務改善・スクラップ」の推進を図ってきたところであります。さらに、7つのプランや第五次太宰府市総合計画後期基本計画などを基にして特出した重点事業と担当課が提案する新規事業、並びに既存事業を比較検討し、最少の経費で最大の効果が出せるよう「選択と集中」を図って参りました。じっくりと時間をかけてこのような手順を丁寧に踏み、市民の声、現場の思い、私のビジョンを可能な限り組み込み、予算を編成して参りました。
そうした過程を経て打ち出しました平成31年度における事業及び予算案の重点項目につきまして、順次概要をご説明申し上げます。
市民の声が届く、市民に声が伝わる市政を実現することで、太宰府の市民力を引き出し、活力ある地域を創生することを目的とする第1のプラン「市民参画の行政、街づくりで地域創生」に基づき、既に市長と語る会、ホームページやフェイスブックによるタイムリーな情報更新、市民の意見箱へのオープンかつスピーディーな回答などを実行に移して参りましたが、加えて「広報だざいふ」を1月号からリニューアルし、「くすの記」という私から市民の皆様への毎月メッセージを掲載し、太宰府にゆかりのある方々による「私のだざいふ」コーナーを新設するなど、市民の皆様によりダイレクトにメッセージが伝わるよう工夫を致しました。
また、新年に入り、庁舎前での職員による朝のあいさつ運動も始めました。我々市職員にとって市民お一人お一人がお客様であるという基本に立ち返るとともに、職場の活性化を図る取組です。そして、三役会議、経営会議を正式に訓令で規定し、より市民本位かつ迅速な意思決定にも努めております。年度末の繁忙期には、市民目線に基づき土曜開庁の拡大を予定しております。平成31年度は更なる広報機能強化を図るべく、総合的な広報戦略を策定し、秘書・広報体制の充実を図って参ります。また、従来の総合戦略会議を新たに太宰府の街づくりビジョン会議と位置付け、内外の幅広い人材を募り、中長期的視点や広域的視野を論点に自由闊達な意見交換を行って参ります。
次に、学問の神様にゆかりのある本市が、そのイメージにふさわしく次代を担う子どもたちとその保護者世代に夢と希望を与える先進的な教育、子育てを実現することで、若年層の自然増、社会増を実現することを目的とする第2のプラン「学問の神様にふさわしい教育、子育て」について述べます。
まずは、「基本教育の充実と先進教育への挑戦」として、子ども・学生未来会議の開催やSTEAM教育の推進、市を挙げた学力向上の取り組み、学校の働き方改革、ICT環境の段階的整備及び学校施設の大規模改造等に計画的に取り組むなど、児童生徒にとって学びがいがある、学びやすい学習環境の整備を図るべく努めて参りました。
次に、肝いりの「子ども・学生未来会議」ですが、未来の太宰府、そして日本、世界を担う子どもや学生が、自らの思いや提言を市長や議員の皆さん、市幹部という大人に対しても積極的に発言してもらうことで、早くから政治、行政への関心を高めてもらい、ふるさと太宰府を愛する気持ちを涵養するとともに、わが郷土、国家、世界をこれからどうすべきかを主体的に考えてもらいたいとの私の強い思いから、市内4中学校の生徒会の子どもたちを対象として開催致しました。これらの取組は初めての試みでもありましたが、議員各位のご協力も得て大きな成果がありましたので、さらに内容の充実を図りながら継続して参ります。
平成31年度は、「学力の更なる向上」を目指すため、ベテラン教員の教室に若手教員が1日留学して学ぶ「市内留学」や、学期末・年度末の復習週間の実施、文部科学省の学力調査官を招いた授業研修会など、本市がこれまで取り組んできた特色ある施策に加え、各学校にICT推進の中核教員を位置付け、ICT支援員の専門的な指導助言を受けながら研修会を実施することで、児童生徒の情報活用力を育成する取組を行って参ります。そのため、近隣他市に先駆け、学校へのICT支援員の派遣とICT環境の整備を、計画的・段階的に行う予定です。
併せて、子どもたちが将来世界に羽ばたくきっかけになるような理数系分野や情操分野の先進的な「STEAM教育」について、本年度に引き続き市内民間企業と連携して共同で推進を図り、子どもたちが、さらに視野や見識を広げる機会を提供して参ります。
次に、「キャリア教育の充実」ですが、本年度は「地域の子どもたちが地域で働く大人たちから学ぶ」ということを重視し、商工会のご協力の下、中学生が職場体験を行う際に活用してもらうよう、「職場体験リスト」を作成し各中学校へ提供致しました。今後も更なるマッチングに努めて参ります。
さらに、平成30年3月に本市が策定した「第2次太宰府市子ども読書活動推進計画」を受けて、太宰府市の小中学校の読書活動の活性化を図るために、本市独自の「太宰府市学校図書館基本指針」を策定致しました。平成31年度につきましては、本指針の周知を図るとともに、各小中学校に配置しております学校図書館司書や司書教諭等が、各小中学校で特色ある読書活動を推進することができるよう支援をして参ります。
次に、「特別支援教育」についてですが、平成30年4月に水城小学校と学業院中学校に通級指導教室を開設し、小学校5校、中学校2校で対象児童生徒が自校で学ぶことができるようになりました。平成31年度につきましては、新たに、太宰府東小学校に通級指導教室を開設する予定であり、児童生徒、保護者のニーズに合わせ、特別支援教育の充実を図って参ります。また、本市は近隣他市の中でも、多くの特別支援教育支援員を各小中学校に配置しており、児童生徒の個別の支援の充実を図って参りましたが、平成31年度も引き続き、配慮が必要な児童生徒の支援の充実を図ることで、共に学ぶ「インクルーシブ教育」の実現を目指して参ります。
次に、全国的に増加する「不登校児童生徒への支援」でありますが、本市では教育支援センターが、学校に登校することができない児童生徒に学習や体験活動の機会を提供したり、学校復帰や進路選択の支援を行ったりしています。成果として、多くの児童生徒が教育支援センターを居場所として、自分たちに合ったペースで学ぶ姿が見られるようになってきています。しかし、学校へも教育支援センターへも通うことができない児童生徒がまだまだ多く、本市の大きな教育課題となっております。そこで、平成31年度は、市内の大学と連携し、大学生とのマン・ツー・マンのかかわりによって大学を第3の居場所、学びの場所とする計画を大学と共に進めているところでございます。その他にも、大学との連携につきましては、大学の特性に合わせて、音楽の合唱指導や学習ボランティア、行事ボランティアを学校に招聘するなど、ますます連携強化を図ることで、学校の教育活動の充実を図って参ります。
次に、本年度から取り組んでおります学校の「働き方改革」についてであります。平成31年度につきましては、児童生徒を指導する教職員が心身ともに健康で児童生徒と向き合う時間やゆとりを持つことができるよう、学校閉庁日の拡大及び学校閉庁時間の設定、中学校部活動の市の指針の策定を行います。なお、中学校部活動については、各中学校のニーズに応じた外部指導者派遣事業を実施し、教職員の心理的、身体的負担の軽減を図って参ります。
さらに、これは全国的にも前例が少ないのですが、市内2小学校の水泳授業を民間に委託することで、児童生徒への効果的な水泳の技能獲得支援及び教職員の負担軽減を図ることにしております。併せて、小学校の夏季プール開放を中止し、市民プール利用券を配布するなど、前例にとらわれない自由な発想で効果的・効率的な市民サービスの実施を図って参ります。これらの事業につきましては、今後見込まれる学校プールの維持管理費用、施設改修費用等と比較して、かかる経費が少なく、この点についても大きなメリットであると認識しております。
最後に、「学校施設の整備」です。計画的な学校施設の大規模改造等を行うため、学校施設の整備構想案の検討を進め、国の補助など財源確保の基礎となる個別施設整備計画の早期策定を目指して参ります。さらにトイレの洋式化は、施設改修時期と合わせて実施すると経済的かつ効果的であるため、施設の老朽度などを考慮し、計画的に実施箇所を選定する必要があります。本年度は、太宰府西小学校屋内運動場大規模改造工事に合わせて実施し、平成31年度は太宰府東中学校の全面改修を計画しており、公共施設のトイレ洋式化を推進して参ります。
現在、小学生・中学生年代の生徒は転入超過となっており、保護者である教育世代も転入超過であることが想定されることから、この世代の社会増の実現が図られています。その一つの要因として、「基本教育の充実・先進教育への挑戦」が好循環を生み出している点が挙げられます。本市独自の特色ある取組を推進し教育施策の充実を図っていき、教育世代に対する「教育を受けるなら太宰府で」との認識に一歩ずつつなげてまいる所存であります。
次に、「大学・短大との連携」については、太宰府キャンパスネットワーク会議に加盟する市内の大学・短大がもつ知的・人的資源を活かすために、平成27年に連携協力に関する協定を締結し、年間四十数事業を実施しているところですが、更なる充実を図るために、情報を共有しながら共同で実施できる新たな連携事業を検討して参ります。また、小中学生向け事業として実施している小中学校サポート制度や留学生のゲストティーチャー派遣を継続して参ります。大学の空き教室の有効利用につきましては、大学・短大と協議し、地域社会の発展や人材育成に繋がる利用形態を模索して参ります。
「中学校給食」については、就学援助制度の導入や注文方法の改善などランチサービスの充実を図ることで喫食率の向上を図りつつ、中学校給食調査・研究委員会において、あらゆる角度から実施方式の検討や財源の検討を行って参りました。今後出来るだけ早く一定の方向性を打ち出せるよう、更なる検討を進めて参ります。また、小学校給食については、行事食をはじめ、友好都市・姉妹都市の郷土料理、世界の料理など、様々な献立の調査・研究を行い、子どもたちの実態や地域の歴史・文化を踏まえた太宰府らしい食育の推進を図って参りました。平成31年度は、更なる食材費の高騰や消費税上げなどの厳しい外部要因が予想されますが、小学校給食の質や量の維持を図るため、小学校給食会に対する食材費補助金を計上することに致しました。今後も本市の子どもたちの健全な成長を最大限サポートし、その無限の可能性を引き出すため全力を尽くして参ります。
次に「文化芸術の振興」については、太宰府市文化芸術振興基本指針(ルネサンス宣言)の具現化、市民が文化芸術に接する機会の創出を行います。太宰府市文化スポーツ振興財団や太宰府市文化協会と連携し、市民への文化芸術の振興をさらに進めるため、プラム・カルコア文化芸術振興事業や太宰府市文化スポーツ振興財団文化スポーツ振興事業として、プラム・カルコア太宰府市民ホールを使用した各種公演や市内の各地域・施設に出向いて教室等を開催するアウトリーチ形式の事業等を実施しており、今後も、文化芸術に関する体制の充実を図り、事業の推進を図って参ります。
「出産・子育てのサポート」については、既に都府楼保育園の増改築工事に着手し、小規模保育施設事業者を新たに一社選定するなど、待機児童解消に向けて積極的に取り組んでおります。今後も「第二期太宰府市子ども・子育て支援事業計画」の策定を通じて、就学前児童の人口減少と潜在的ニーズの増加とを勘案しつつ、将来の需要を見据えた最適な定員確保の方策を検討致します。そのような中、現状は待機児童の大半が0、1、2歳児であるため、平成31年度も引き続き小規模保育施設を1園公募し、特に待機の多い3歳未満児の待機児童の解消を図って参ります。同時に既存施設については増改築などに合わせて、事業者と協議しつつ定員の更なる増加を図って参ります。また、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して、総合的相談支援を提供する「子育て世代包括支援センター」について組織体制と施設の見直し等の調査研究を行います。
「学童保育の充実と児童活動の応援」については、市内17か所の学童保育所で既に保育を実施しておりますが、入所対象を6年生までに拡大したことや、保護者の働き方の多様化に伴うニーズの高まりにより、近年入所希望者が増加傾向にあり、引き続き現在の運営形態を実施しつつも、利用児童の動向を注視しながら教室の不足等が予期される場合においては、迅速に当該小学校とも協議を進め、利用者の受入等を進めて参ります。平成31年度は国分小学校において支援教室や通級教室の不足が生じ、現在空き教室を利用している学童保育所の利用について調整が必要になったところでしたが、市長部局と教育委員会が組織横断的に対応し国分小学校と協議を行った結果、学校での授業及び学童保育のいずれにも支障をきたさぬよう調整し、将来の需要を見据えた学童保育所整備に係る基本設計費を最小限の経費で計上しております。今後も中長期的視点を常に持ちながら、利用児童の動向を注視し教室の不足等が予期される場合においては、当該学校とも協議を進め、児童の受入を行うと同時に、前例にとらわれない自由な発想を駆使して、歳出削減策に取り組んで参ります。
組織横断的に徹底した行政改革による歳出削減、太宰府の底力を活かした成長戦略による自主財源の増加を同時に成し遂げ、本市の活力を増大させていくことを目的とする第3のプラン「徹底した行革と超成長戦略で財政再建」に基づき、中長期視点に立って本年度から様々な取組をスタートさせています。
まず、「職員の人材育成」として、三役と職員との意見交換や平成31年度職員採用に向けた事前説明会を開催するなど、新たに人材育成や人材確保に取り組んで参りました。また、庁内関係課会議を設けて、年度末繁忙期の土曜開庁拡大について検討するなど、庁内連携やチーム力の強化も図ってきたところです。人材育成基本方針の改訂については、職員で構成する策定委員会を定期的に開催し、併せて、職員の意見を幅広く吸い上げながら、本年7月の策定に向けて進めて参ります。この他、国や他自治体との人事交流を積極的に行うとともに、民間企業との人事交流の可能性も探って参ります。
「市政運営経費の見直し」については、歳入増加策としてふるさと納税に注力して参りました。昨年11月には、従来のさとふるに追加して、ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税のポータルサイトも開設し露出度の拡大を図り、平成30年末の段階で平成29年度実績を超えている状況であります。そして、今般、返礼品の発掘、開発業務を大胆に実施し、太宰府のネームバリューを活かして大幅な収入増を目指すべく「THE DAZAIFU プロジェクト」をスタート致しました。昨今ふるさと納税は本来の趣旨を逸脱し過度な返礼品競争に走りすぎているきらいがあり、総務省もその是正に乗り出しました。本市としてはルールの適正化が図られる今こそチャンスであるととらえ、太宰府らしい返礼品を改めて市内外に広く募り、積極的にノミネートしていこうと考えております。具体的には、太宰府市の花でもあります梅をテーマに、梅の実はもちろんのこと、梅の花や梅の形、梅の香りをもちいた梅酒や甘酒、ドリンク、お菓子などを積極的にラインナップします。次に、1月2日に放送された「ブラタモリ×鶴瓶の家族に乾杯新春スペシャル」で紹介された様々な名所旧跡を専門の解説員付きで「ブラタモリコース」として商品化し、太宰府ならではのコト消費として提供して参ります。また、学問の街として知られるイメージを生かし、太宰府天満宮との緊密な連携はもちろんのこと、5つある大学・短大や特色ある高校、企業などともタイアップするなど様々なグッズや教材、飲食物などを開発して参ります。これに加え、本市出身やゆかりのある方などをターゲットに積極的なクラウドファンディングも仕掛けて参ります。今後の展開につきましては、4月を目途に事業者説明会を開催し、その後積極的に営業活動も行い、秋には新作発表会を実施した上で、年末のかき入れ時に万全の態勢で臨む所存でございます。
歳出削減については、まず予算編成方針において「各事業に対して、国・県等のあらゆる補助メニューを積極的に活用し、最少の経費で最大の効果をあげることに努めるとともに、事業の継続性や必要性を再度根本から見直すなど、職員ひとりひとりが自らの問題として行財政に対しての危機意識を高めることが求められる」と私から職員に直接呼びかけ、その意識の徹底を促しました。そうした意識のもと、入札制度については競争性をさらに高める試行をおこなって参りましたが、引き続き試行を重ね、どのような制度が望ましいのか、不断の検討、見直しを行って参ります。また、市全体での出費を抑えつつ災害に強い街づくりを行うため、水道会計が行う水道施設の耐震化について国庫補助金や一般会計出資債を活用しております。公共施設再編計画については、モデルプランとして主要公共施設の半分を占めている学校施設の整備構想案の策定を進めており、他の公共施設についても検討し策定を図って参ります。また、国が示す「インフラ長寿命化基本計画」及び「文部科学省インフラ長寿命化計画」に基づき、施設の老朽化と財政状況の悪化の中で、安全なスポーツ施設を持続的に提供し 市民の皆様が身近にスポーツに親しむことのできる環境を整備できるよう「スポーツ施設個別計画」を策定して参ります。併せて「スポーツ推進計画」も策定し、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、スポーツの機運を高めて参ります。さらには、指定管理者と協議しながらとびうめアリーナの更なる有効活用を進めて参ります。今後も、あらゆる歳出について聖域なく不断の見直しを行い、積極的にその効率化に努めて参ります。
「地場みやげ産業の振興」については、1次産業としての農業、2次産業としての製造業、3次産業としての小売業等の事業を結び付け新たな付加価値を生み出すために、農業経営者、JA筑紫、商工会、福岡農業高校など多様な主体による協議の場である(仮称)太宰府市産業推進協議会を立ち上げます。その協議を通じて、ふるさと納税にも出品できる太宰府グルメ、新たな地場みやげなどの発掘、開発を進め、さらに既存商品の磨き上げなどを行い、本市の新たな収入源実現を図って参ります。
「大宰府政庁復元プロジェクト」については、皆様も「太宰府市民政庁まつり」でご覧になられたかと思いますが、まずは政庁跡VRコンテンツ利用促進事業を展開し、西の都VRを大宰府展示館にて公開しております。また、大宰府史跡発掘50年記念行事について、共催・後援企画に参加するなど、文化遺産をより身近に感じてもらえるよう進めて参りました。そのような中、再来年度が大宰府跡と水城跡が我が国最初の史跡に指定されて100年の節目の年に当たります。その節目の年に、私が副会長を務めております全国史跡整備市町村協議会の大会の本市開催誘致に向け働きかけを強めております。実現に至れば、悠久の歴史を紐解く一大記念イベントの企画を進めるとともに、単にイベント開催で終わらせることなく、史跡活用の為の大幅な規制緩和や維持整備費用負担への相応の補助など国・県に対する大胆な提言をこの機会に強く打ち出して参ります。それによって、更なる観光客確保や経済効果の上昇を可能にし、史跡関係自治体の財政を充実・安定させる方策を追求して参ります。まずは、平成30年12月補正予算において水城跡整備事業費及び大宰府跡等整備事業費を計上し、前倒しで整備を進めているところであります。平成31年度は、古代の外交の窓口として重要な施設であった客館を現代の太宰府観光の入口として活用するため、外国使節が滞在した大型建物跡等について費用対効果を見極めながら平面復元を行うとともに、文化庁の枠にとらわれず、国土交通省事業である歴史的風致維持向上計画と連携し、展望空間や防災機能を持たせた施設などを設置することで、観光のみならず市民の皆さまの便益を図る史跡公園化を進めて参ります。また、今後は市全体の一体的な史跡整備・再整備を図っていくうえで改正文化財保護法の新制度等を積極的に活用し、維持費出費型から歳入創出型への更なる転換を図って参ります。
「産業の創生」については、現在商工会と連携して優秀な人材が市内で活躍、創業できるよう環境づくりを行っており、ホームページにおいても市内創業事例を公開するなど創業に対する機運を高めているところです。今後は創業を考えている方々が情報交換できるような施設も必要であるため、市内の大学施設や空家等が有効活用できるような取り組みも併せて検討して参ります。また、商工会において産業競争力強化法に基づき開催している特定創業支援事業「創業塾」についても、参加者が定員を超えるなど年々そのニーズが増えてきております。そこで、創業塾修了者や商工会の創業者向け個別経営指導を受け実際市内にて創業する方に対し、事業開始時に必要となる費用の一部を平成31年度から新たに補助することにより、意欲ある起業家の事業支援や新たなビジネススタイルの実現など様々なビジネスプランを力強く支援し、新たな産業創出や更なる雇用の確保を目指して参ります。
その他、「計画的なまちづくりの推進」については、都市計画審議会において立地適正化計画、空家等対策協議会において空家対策計画策定に向け協議を進めて参りました。平成31年度中には立地適正化計画及び空家対策計画を策定し、持続可能な都市を目指すと共に、重要拠点や住宅地等市街化が望ましい地域は土地利用の誘導を行うため、太宰府固有の歴史と自然豊かな景観に配慮しつつも、国・県と積極的に協議を行い、前例にとらわれない区域区分の見直しや用途地域の見直しの可能性を追求して参ります。特に、マミーズが撤退しました西鉄五条駅周辺については出来るだけ速やかに用途地域等の見直しの検討を行い、新たなる発展を目指して参ります。また、佐野東地区等についても同様の検討を行って参ります。
次に、圧倒的知名度を活かしながら広い視野で近隣自治体との連携を密にし、その中核として自ら発展するとともに周囲にも好影響を与える役目を果たすことを目的とする第4のプラン「積極的広域連携による大太宰府構想」について述べます。
「バス路線の利便性・収益性向上」でありますが、まず、マミーズの閉店により廃止となった「マミーズ・まほろば号」の代替交通手段として、東観世区への地域線運行の計画を急いでおります。コミュニティバス「まほろば号」の運行については、市長と語る会などで要望を受けた路線延長についても可能な限り柔軟かつスピーディーに検討を続けて参ります。また、運行データの分析を行い、効率性向上を念頭に置いたダイヤ改正も計画しております。更には、市域を超えた運行についても事業者と協議を行うとともに、福岡県地方創生市町村圏域会議等で協議、情報収集しながら、積極的に可能性を追求して参ります。なお、本年度立ち上げました地域公共交通活性化協議会におきまして、持続可能な公共交通網の構築に向けた検討につきましても並行して行って参ります。
「観光連携による回遊性向上」については、県物産振興会と連携した札幌、横浜等での観光宣伝、国、福岡市、鹿島市、壱岐市と連携した中国富裕層向けプロモーション事業等を実施しています。また、西鉄及び沿線7自治体による共同プロモーション「西鉄で巡る沿線プチTRIP」も実施しております。本年度中に観光推進基本計画を策定し、近隣とも積極的に観光連携を進めることで本市内外の回遊性を高め、観光客の更なる誘客と宿泊や飲食、買い物などを通じた全体としての消費単価の向上を目指して参ります。具体的には、平成31年度から九州国立博物館を中心に九州歴史資料館、福岡県、商工会、観光協会、太宰府天満宮と共に実行委員会を組織し、文化財等の地域資源を活用して太宰府の魅力を国内外に発信し、地域経済、地域社会の活性化を図る事業を展開して参ります。また、日本遺産を活用した観光ガイド等を含めた地場観光産業を創出すべく、市内関係者及び市外のノウハウを持つ事業者とのマッチングを進め、3年後のビジネス化を目指して協議を継続して参ります。また、太宰府天満宮周辺において古民家を活用した宿泊飲食施設の話も進んでおり、これを機に更なる本市での回遊性向上による観光客の滞在時間延長を目指し、宿泊者向けの体験メニューの充実を推進して参ります。さらに、2月1日に無料での供用を開始しました大宰府政庁前のバス専用駐車場につきましては、同じく本市観光の回遊性向上を目指すものでございますが、今般、財源確保を図るため4月から有料化すべく本議会に条例案を提案しております。議員各位におかれましては、歳入創出型の史跡地活用を図っていくための方策として、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。
「交通大動脈計画の立案」についても、将来的に更なる人の往来と交通渋滞解消が両立されるよう可能性を追求するために、あらたな交通モード等の可能性等の調査研究を行い、中長期的な交通大動脈計画策定に向け引き続き準備を進めて参ります。その前段として、地域公共交通活性化協議会等で議論し、周辺自治体とも連携した広域的交通体系やまちづくりの議論を進めて参ります。
本市において渋滞問題は喫緊の課題の一つでありますが、道路整備などハード面での対応には多大なお金や時間を要します。そこで発想を転換し、環境に負荷をかけず、比較的短期間で渋滞解消を実現することを目的とする第5のプラン「環境重視の逆転の発想で渋滞解消」に基づいて、総合交通計画協議会及び地域公共交通活性化協議会を開催し、協議を行っております。昨年11月には総合体育館周辺・西鉄天神大牟田線周辺地域の交通実態調査及び天満宮周辺地域の通過交通調査を実施いたしました。
「渋滞解消」については、ロードプライシングも視野に入れた交通誘導施策やパークアンドライドやシェアサイクルの活用など本市にとって最善の方策を検討して参ります。まずは道路網の計画である「総合交通計画」及び公共交通網の計画である「地域公共交通網形成計画」の平成31年度中の策定に向け、人の移動動向を分析する等追加調査を実施し、持続可能な公共交通網の構築のため施策の検討を行って参ります。
「市道の整備・管理」については、地元要望の多い舗装の傷みが激しい道路、通学路などの改修や修繕を行うと同時に、側溝蓋設置計画に基づき、梅香苑、東ヶ丘、梅ヶ丘、松川でいち早く側溝蓋設置を実施しました。また、限られた財源の中で効果的に地元要望に応え、進捗の透明性を図ることができるよう、本年度、何度も見直しを図りながら生活道路や通学路の10年間の道路改修計画の策定を行いました。平成31年度は、舗装の個別施設計画を策定し、補助事業や起債事業の対象となる路線を増やすことで、少しでも多くの自治会要望に対応して参ります。また、自治会との協議により必要に応じて計画の見直しを行い、安全かつ快適に道路を通行できるよう整備して参ります。併せて、市内を縦横断する国道・県道の維持管理や整備についても、引き続き強く要望して参ります。
本市の高齢者も人口の4分の1を超え、高齢者福祉の更なる充実を図ることが求められています。しかしながら財政的限界もあり、公的支援に過度に依存しない民間主導の方式も活用していかなければなりません。そうした認識のもと取り入れた第6のプラン「民間の知恵を生かした高齢者福祉」に基づいて、地域の多様な主体が定期的に情報を共有し、連携・協働により新たな地域づくりを進める場である協議体の設置について、関係者間のネットワーク作りを推進しております。まずは、各中学校区を単位とする第2層において、太宰府東中校区をモデルとして実施しております。また、私の肝いりの市民本位の政策の一つでもあります福祉や高齢者に関する困りごと悩み事について、こちらから地域に出向いて対応する出張相談会を社会福祉協議会と連携して実施しました。その他、イベント等に合わせて相談ブースの開設を行うなどアウトリーチ型の相談体制を進めることで、高齢者やその家族等にとって相談しやすい環境づくりに努めてきたところであります。
「地域包括支援センターの相談体制の充実」については、地域包括支援センターの機能強化を図るべく、平成31年度中に地域包括支援センターの支所を1か所増設し、市域の西側を担当圏域と致します。同時に東側が担当圏域となる既存の地域包括支援センターには、本所としての統括機能を持たせ、支所との役割分担及び連携の強化を通じて効果的かつ効率的な運営体制を構築して参ります。その際、支所の開設を契機として、地域包括支援センターの更なる利活用を図るため徹底した周知活動を行って参ります。その他、十分な専門職の配置・運営体制のもと、地域ケア会議や協議体等の活動を通して多様な主体との連携を図りつつ、高齢者の視点に立った、よりきめ細かな対応に努めて参ります。
「障がい者福祉の推進」については、心身に重度の障がいのある方の日常生活の利便と社会活動の範囲の拡大を図ることを目的に、タクシーの初乗り運賃を助成しております。現在年間48枚交付していますが、平成31年度から更なる充実を図るため、交付枚数を年間60枚に拡大致します。
「健康づくりの推進」につきましては、現在策定をしております「健康増進計画・食育推進計画」「自殺対策計画」に沿って、親と子の健康支援、生活習慣病の発症・重症化予防、高齢者の健康づくり、心の健康づくりなどライフステージに応じた健康づくりと相談窓口の周知等の環境整備を行い、市民の健康増進と食育の推進に努めます。また、妊娠を希望される女性とそのご家族等を対象とした「風しんの任意予防接種」と、児童福祉施設に勤務する職員を対象とした「麻しんの任意予防接種」についての費用の助成を行い、先天性風しん症候群の予防と麻しんの乳幼児への感染の予防に取り組んでいますが、更に、風しんの予防接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性を対象とした「風しんの抗体検査」と「風しんの定期予防接種」を国の動向に合わせて開始する予定としております。
市民の安心安全の確保こそ行政の最大の使命との思いのもと、災害対策や防災に万全を期すことを目的とする第7のプラン「自衛隊と連携した市民の安心安全」に基づき、あらゆる事態への備えと対応に取り組んで参ります。本市においても豪雨災害、地震災害が懸念されるなか、自衛隊などの助言をいただきながら、昨年7月豪雨災害をはじめ市内外の過去の災害を参考に、起こりうるあらゆる災害状況を網羅した豪雨災害シミュレーションを完成させます。さらに東西に2つの活断層があり、発生可能性が高い地震災害のシミュレーションにつきましても、被災想定の十分な検討をしつつ完成に向け取り組んで参ります。そうした過程を通じ、想定する被害に対しての被災者ニーズや市の対応、関係機関の協力内容を仮定し、体制づくりや訓練に役立てて参ります。また、不足や不備が生じる対応分野の洗い出しを行い、その補完として民間団体との協定も進めて参ります。
本年度は、物資供給、災害情報の提供手段分野などにおいて複数の物資販売会社やテレビ局などと意欲的に災害協定を締結して参りました。今後は、人的資源が必要な救援物資の集積、分別分野や被災者の生活確保のためのみなし仮設住宅の確保などについても、積極的に民間団体との協定締結を進めて参ります。
また、NPO法人やボランティア団体との災害の協力体制についてでありますが、本年度障がい者団体などと要配慮者の災害時の対応の協議を行い、防災関係の団体からは7月豪雨の際ボランティア協力やご助言をいただきました。今後は、関係した団体との協力体制を更に深めていくとともに、避難が長期化した場合の避難所の衛生管理や被災者へのケアなど専門性を要する分野に取り組まれているNPO法人やボランティア団体に対する情報収集や協力体制づくりに努めて参ります。
その他、本年度は農林水産省の国庫補助を活用し、ため池の耐震診断調査を6か所並びに危険度調査を2か所実施しました。また、県営河川の「御笠川」「鷺田川」「大佐野川」等につきましては、氾濫を防ぐ効果がある堆積土砂の浚渫、河川内に自生した樹木の伐採等を実施いただいており、引き続き要望して参ります。
次に、「安全な消費生活の推進」については、市民の皆様の消費生活に関する様々なトラブルの相談窓口として太宰府市消費生活センターを開設しております。今後とも相談を受ける相談員の研修等を重ね、資質向上を図るとともに、市民の皆様への出前講座や市広報及び街頭での啓発を行って参ります。また、昨年度、防犯、地域コミュニティ、高齢者、青少年を所管する庁内関係課で組織した「消費者安全確保地域連絡会議」において消費者トラブルに関する情報共有、連携を図り、消費生活上のトラブルの未然防止につなげて参ります。
次に、第五次太宰府市総合計画後期基本計画に基づく施策の一つである「社会保障の適正な運営」の「国民健康保険の健全な運営」につきましては、少子化、高齢化が進む中、本年度から持続可能な社会保障制度を維持していくための国保制度改革が行われております。本市の「国民健康保険事業特別会計」の決算につきましては、慢性的に赤字が続き、繰り上げ充用や平成29年度決算までに累計10億円の一般会計からの赤字補てんのための「法定外繰入」を実施して参りましたが、現在でもその累積赤字は一部残っており、今なお厳しい状況となっております。平成28年度以降、少しずつ国保税率改定を行い、状況の改善を図ってきたところでありますが、年々伸びる医療費、社会全体の高齢者数の増加などを考えますと、国保保険者としての本市を取り巻く環境は今後もますます厳しくなると考えられます。このようなことから、これまでの議会でご説明申し上げましたように、制度改革前の累積赤字を解消するため、一般会計からの「法定外繰入」を、今回の補正予算として計上させていただいております。その後につきましては、被保険者の負担感の観点はもちろんですが、特別会計の基本である「独立採算」の観点に立った国保運営をしていく必要があると考えております。本年度につきましてもそうでありましたが、平成31年度につきましても引き続きこの考え方に立ちまして国保運営に努めて参ります。大変厳しい判断でありますが、本市財政への影響を極力抑え、将来にツケを回さないための税率改定を提案させていただいております。何卒、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
「ごみの減量」につきましては、ごみの排出量の約9割を占める可燃ごみを減量し、ごみ処理にかかる費用をいかに削減していくかが大きな課題であることから、「~もう一歩進もう~ごみ減量72 000人プロジェクト」として、各家庭や事業所の皆様のご協力を得ながら、様々な施策を実施して参ります。まず、本年度実施の可燃ごみ組成調査で得たデータを基に、平成31年度はごみ減量のための啓発冊子を世帯に配布し、この中で啓発のポイントとなる、ごみ種ごとの処理方法の案内、暮らしの中で使える「水切り、食べ切り、使い切り」の生ごみ減量アイデア等を提供し、発生の抑制を図って参ります。また、紙ごみについては、近年減少傾向にあります古紙回収量を増加させる取組みとして、資源回収の期間・世帯数に応じて全自治会に交付しておりました「古紙回収システム推進補助金」を廃止するとともに、資源回収をしている団体に対し、回収量に応じて交付しております「古紙等資源再利用事業奨励金」について、現在1キログラムにつき7円であるところを8円に増額し、紙ごみ減量・リサイクルを更に強化して参ります。その他、中国におけるプラスチック類の輸入禁止措置等の影響により、リサイクル品としての価値が低くなっている廃ペットボトルの品質を向上し、売却益の増収に資するための分別業務委託料を計上するなど、常に社会経済情勢の変化に対応し、費用対効果を図りながら、前例にとらわれない自由な発想で効果的・効率的な市民サービスの実施を図って参ります。
次に、「国際交流・友好都市交流の推進」であります。「国際交流活動の推進」につきましては、これまでと同様に太宰府市国際交流協会と連携しながら市民の国際交流を推進するとともに、本市で暮らす外国人の方々が安心・安全・快適に暮らせるための支援に努めて参ります。
「姉妹・友好都市交流の推進」につきましては、職員の派遣を続ける多賀城市を始め私自身も積極的に現地に出向き交流に努めて参りましたが、自治体同士の交流に加え市民・団体間における交流の更なる活性化を図っていくことも必要であると考えております。こうした観点から、平成31年度は姉妹都市である韓国扶餘郡で開催される百済文化祭に出演する市内文化団体の派遣を検討しております。また、平成27年の友好都市承継締結から5年を迎える大分県中津市の自然・文化遺産を巡る市民訪問団を結成し交流する取り組みや、中津市で実施するジュニアリーダーズクラブによる市内小学生の野外活動を支援して参ります。
次に、「人権政策」についてであります。人権政策は全ての施策を推進するにあたり基礎となるものであります。本市では、「人権尊重のまちづくり推進基本指針」と「実施計画」に基づき、人権尊重の視点に立った総合的な人権行政を進めているところであります。平成31年度は、「部落差別解消推進法」や「障害者差別解消法」並びに「ヘイトスピーチ解消法」、いわゆる人権三法の成立など社会情勢の変化に即して現行の「人権尊重のまちづくり推進基本指針」を見直した上、新たな指針に基づく実施計画を策定し、更に積極的に課題の解決を図って参りたいと思います。また、家庭、職場、学校、地域などあらゆる分野を通じて人権尊重の理念を普及し、理解を深めていただくよう、教育及び啓発を学校教育とも連携を図りながら推進して参ります。
次に「男女共同参画の推進」についてであります。平成30年5月に「政治分野における男女共同参画推進法」が新たに公布・施行されるなど、男女共同参画実現の要請は更に高まっております。私自身、その時代の要請にいち早く応える意味でも、最初の人事として三役の一角に女性の樋田教育長を任命致しました。また、新人採用においても男女比にこだわらず意欲ある女性を積極的に採用し、人事においても積極登用を心がけております。今後も引き続き審議会等における女性委員の積極登用を進めて参ります。また、昨年度に策定した「第2次太宰府市男女共同参画後期プラン」に基づき、固定的な性別役割分担意識の解消、ワーク・ライフ・バランスの推進、配偶者等からの暴力の根絶、女性の活躍推進などに取り組み、社会のあらゆる分野において男女が共に参画し、責任と喜びを分かち合い、性別に関わらず個人の能力と個性が発揮できるまちづくりを進めて参ります。
「情報の共有化と活用」につきましては、社会保障・税番号制度の施行など地方公共団体を取り巻くICT環境は劇的に変化しております。このような国の施策や動向、市民を取り巻く環境の変化などを踏まえた上で、オープンデータをはじめ、データを活用した新事業・新サービスの創出等に向けて取組みを進めております。一方、情報セキュリティ分野では、官公庁の情報漏えい、特に民間企業等ではサイバー攻撃による機密情報の窃取等の被害が頻発していることから、安心・安全なICT環境の実現に向けて取り組んで参ります。また、行政資料・地域資料等研究事業の中枢である「公文書館」では、歴史的価値がある行政文書の収集及び市史編さん時から収集してきた地域資料の管理を行うとともに、市民への行政出前講座や展示、「広報だざいふ」への公文書館だよりの連載、レファレンスサービスなどを通して、その研究成果を還元しており来館者数も昨年度より増加傾向にあります。今後はさらに市民利用の促進を図るため、文書目録の整備等を図って参ります。
以上、平成31年度の重点事業と予算案を7つのプランと第五次太宰府市総合計画後期基本計画に沿って詳細にご説明して参りましたが、全体を見渡しますと概ね、かねてより私が訴えて参りました「超成長戦略」や「生活支援戦略」、「徹底した歳出削減策」などを通じ市内外での「積極的財政投資」と「地域の所得アップ」の好循環をもたらすべく「選択と集中」を図った内容となっております。その結果として、未来を担う子ども・学生や子育て世代、意欲ある起業家、公的支援を必要とする高齢者、障がい者など「人」への投資が必然的に拡大し、「土木費」などハード面の予算は一時的に縮減した上で、今後透明性を持って計画的に推進していくようなかたちに致しました。総じて、平成31年度予算案を「だざいふ未来投資予算」と銘打ち、本市の輝かしい未来へと力強く繋げて行く決意であります。
このように、職員諸氏と長きに亘り議論を重ね、前例にとらわれない自由な発想と旺盛なチャレンジ精神を掛け声に編成して参りました平成31年度施政方針と当初予算案ではありますが、課題はまだまだ山積していることも改めて認識致しました。一言でいえば、市民の多様なニーズに十分かつ機動的に応え、本市の更なる発展に向け積極的に投資を続けていく為に必要な歳出要求と本市の歳入能力に慢性的な開きがあるということです。
分析致しますと、「歴史とみどり豊かな文化のまち」の名にふさわしく、本市には実に約16%を占める史跡地が存在し、学校法人や宗教法人、公共施設なども数多く存在します。このため、住環境は良好で観光資源も豊富ですが、その一方で近隣市と比べても法人事業者や人口が増加する余地は小さく、それにまつわる税収も伸び悩んでおります。
更に、高齢者人口は増え続け、高齢化率も近隣市と比べても高い状態にあります。また、出生者数が減少していると同時に、出生者数より死亡者数が多い自然減の状況が発生しております。さらに、就学前の児童につきましては転入者数より転出者数が多い社会減の状況が続いていることから、保護者である働き盛りの子育て世代も転出超過となっている可能性があります。
また、大宰府政庁跡や水城跡、観世音寺、戒壇院などの名所旧跡が随所にあり、全国的な知名度がありながらも、観光客は太宰府天満宮や九州国立博物館一帯に集中しがちで、滞在時間が2、3時間に留まり、観光消費単価は高いとは言えない状況です。一方で、慢性的な交通渋滞が長年市民を悩ませております。
これらの状況が本市の経済に与える影響でありますが、住民一人当たりの地方税額や地域経済循環率は全国の自治体と比較しても決して高いとは言えず、国内の経済状況や本市の本来持つ底力からすれば、経済が十分に循環しているとは言い難い状況であります。
税目別に現年課税分を見ると、個人市民税は平成29年度末調定額が前年度から減少しており、今後働き手の世代が減少していくことによりこの傾向が大きくなることも想定されます。固定資産税については、住宅地、商業地とも地価は一定程度上昇しているものの、前述の本市の特性などから慢性的に調定額は低く留まっております。法人市民税は、納税義務者数は一定数増加しているものの、こちらも調定額は相対的に低い状況です。
一方、歳出については、総合体育館整備事業の償還開始による公債費の増加、消防組合の機器更新事業や環境施設組合の建屋更新事業など一部事務組合への負担金の増加、サービス利用者の増加に伴う社会福祉事業での扶助費の大幅増などから、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、近年悪化の一途をたどっております。
今後も、社会保障費や扶助費の増加は避けて通れず、待機児童の解消に向けた子育て支援の充実、高齢者支援の充実など、社会的な課題も多い状況です。また、小・中学校をはじめ老朽化した公共施設の維持・更新に多額の費用が見込まれ、今以上に歳出要求が高まることが予測されます。
以上のように、本市の財政運営は今後更に厳しさを増す可能性が高く、渋滞問題など根深い課題も山積しており、解決に向けてはまだまだやるべきことが数多くございます。この度の平成31年度施政方針と予算案は、こうした課題の解決に向け確かな一歩を踏み出すものであり、まずは来年度こうした方針を着実に実践して参ります。
その上で、慢性的な歳入不足を補うため、人口増加策、特に働き盛りの子育て世代の社会増や未来を担う子どもたちの自然増を促す施策、企業を誘致し新たな産業を育成する施策、回遊性を高め経済効果を上昇させる観光政策・文化財活用策、都市としての飛躍的発展を可能にする交通政策・まちづくりビジョン、ふるさと納税制度をフルに活用した施策などの斬新な歳入増加策を創り上げなければなりません。
また、各事業に対して、国・県等のあらゆる補助メニューを積極的に活用し、「最少の経費で最大の効果をあげる」ことに努めることや、事業の継続性や必要性を不断に見直すことはもちろんのこと、補助金や公的利用料の見直し、入札改革、公共施設の再編など聖域なき行財政改革プランも必要です。
こうしたいわゆる「だざいふ版歳出入一体改革」についても、常に市民目線を心がけ、積極的に市民の声に耳を傾ける現場主義を徹底し、広域的視野と中長期的視点を持ちながら、前例にとらわれない自由な発想と創意工夫、旺盛なチャレンジ精神を駆使して構想し、市民の多様なニーズに十分かつ機動的に応え、本市の更なる発展に向け積極的に投資を続けられる、持続可能な未来志向の市政に転換して参ります。
結びに改めて申し上げます。平成の集大成となり新たな御代を迎える節目の来年度を「新生太宰府元年!」と位置付け、課題解決に向けた確かな一歩となる平成31年度施政方針と予算案を着実に実践しながらも、本市の未来を切り開く新たな改革プランを意欲的に構想していく「実践と構想」の一年にして参ります。
その為には、議員各位のご理解とご協力が不可欠であります。どうか、私の意とするところをお汲み取りいただき、予算案をはじめとする全議案に対し、慎重なるご審議のうえ、ご賛同賜りますよう重ねてお願い申し上げ、私の施政方針と致します。
平成31年2月21日
太宰府市長 楠田 大蔵