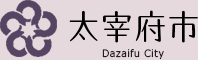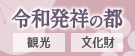本文
施政方針(令和7年第1回(3月)定例会・令和7年2月26日)
本日ここに、令和7年第1回定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては大変ご多用の中をご参集賜り、厚く御礼を申し上げます。
この定例会は、令和7年度の当初予算案をはじめ主要施策及び条例案などをご審議いただくだけでなく、私にとりまして2期目最終年度の集大成、総仕上げとなるひと際重要な議会ととらえております。議員各位や市民皆さまの一層のご理解とご協力を心からお願い申し上げるものであります。
さて、先月1月28日で市長就任7年が経過しました。思えば私が就任した7年余り前は、当時はまだ珍しかったトップの不信任が全会一致で成立し議会も解散され、副市長も教育長も不在という本市未曽有の混乱期でありました。
そこから、議会、市役所、市民の皆さまと一緒に一歩ずつ改革を進め、その間も令和フィーバーやコロナ禍、猛暑記録などへの予期せぬ対応も余儀なくされましたが、着実に混乱からの脱却、市政再建、日本を代表する都へと成長を成し遂げてきたとの自負があります。
市税やふるさと納税も着実に増加を重ね、これまでの外部調査でも住みよさランキングで九州沖縄1位、ブランド総合研究所の魅力度ランキングでは過去最高の全国37位、大東建託(株)の自治体ブランドランキングでは全国48位といずれも上位を占めるなど各種施策の成果が着実に評価されています。
確かに日本遺産の候補地への移行は不本意ではありますが、古より我が国の政治行政、外交防衛、文化交易などの要衝であり、大陸からの窓口であった西の都に留まらぬ「令和の都だざいふ」としての誇りは全く色あせておらず、その後も多くの観光客参拝客の方々にお越しいただいております。
加えて、昨年待望の中学校給食がスタートしたこともあり出生数は全国的に珍しく一時的に増加に転じ、人口流入も流出を大幅に上回って2年連続社会増を達成しました。それを裏付けるように本市は全国65(22位)しかない自立持続可能性自治体に選ばれ、生産年齢人口割合も増加傾向となっています。
そうしたなか、令和7年度の当初予算案は、楠田市政二期目最終年度の集大成・総仕上げとして、第2期総合戦略の4つの構想・戦略とそれに基づく二期目公約に加え本年度新たに位置付けた市政積年のもしくは社会先進的な課題の解決に向けた5つの最重点事項(3つの柱と2つの底流)を有機的に組み合わせた「好循環を次代につなぐ集大成予算」と銘打ちました。
恒常的な少子化対策や高齢者福祉などに加え物価高騰や人件費増など歳出圧力がさらに高まる中、順調に増加してきた市税やふるさと納税などによる歳入増や積み上げてきた各種基金、削減してきた市債も活用し、歳出の積極的効率化も行いつつ、市民の幅広いニーズに応え課題解決に資する予算確保に最大限努めました。
その結果、予算規模は337億円余と昨年を12.4%上回る過去最高となり、この8年で約100億円増加しました。市税も同じく約10億円増加し、ふるさと納税も財源の一定割合を占めるまでになりました。出生数も一時的に増加し、社会増も2年連続達成するなど好結果も出ています。この好循環を次代に着実につなぎます。
それでは、令和7年度予算案について、予算説明資料では総合戦略4つの構想・戦略ごとでも分類しておりますが、事業自体は共通しておりますので重複を避け、本年度から新たに位置付けた市政積年のもしくは社会先進的な課題の解決に踏み出すための最重点5項目をもとに説明して参ります。
加えて、その重点5項目をさらに本市が特に力を入れて取り組むべき3つの柱とその全てにおいて共通して意識をすべき2つの底流に分け、よりわかりやすくパッケージごとに説明いたします。これらを有機的に組み合わせることでより効果的、機動的に市政を前に進めることが出来ると考えています。
まず1項目め 一つ目の柱であります「危機管理の徹底強化」についてです。
これからの時代は常に災害や犯罪などの危機があると認識し、最近横行する闇バイト犯罪や日本一の猛暑、大規模な自然災害などから市民や観光客参拝客などの生命財産を守るための体制の整備、訓練及び情報発信などを徹底強化していくことを目指し、約22億円を計上しております。
その中でもまず「闇バイト対策をはじめとした防犯力向上パッケージ」を設定し、約1億円を計上しております。
考えてみてください。年老いた両親が闇バイトに短絡的に応じたどこの誰ともわからないならず者に有無を言わせず惨殺される姿を。私は絶対許すことはできません。もちろん応募する側の事情も認識はしておりそれはそれで対策を考えなければなりませんが、まずは本市の特に高齢世帯の方々の防犯対策を急がなければなりません。
そこでまず、「住宅等防犯対策事業」についてです。
闇バイトなどから市民の生命財産を何としても守るため、住宅等の防犯対策に要する費用の助成を新たに行い、犯罪の抑止力強化を図って参ります。
次に「地域見守りカメラの増設」についてです。
犯罪や事故等の予防を目的とした地域見守りカメラを計画的に設置し、安心安全な「見守る」まちづくりを推進して参ります。
次に「防犯体制の強化」についてです。
引き続き防犯専門官を配置するとともに外部専門家も活用し、防犯講座を行うなど防犯対策を推進して参ります。
その他にも、公共施設LED化の推進などの予算も活用して参ります。
2つ目の「日本一の猛暑のまち対応パッケージ」には約9億円を計上しております。令和6年度に猛暑日連続40日通算62日といずれも国内の歴代最多記録を大幅に更新し、本市が日本一の猛暑のまちとなり、これからは猛暑のまちに対応した事業や観光施策に取り組んでいくことが重要です。
具体的にはまず、「小中学校屋内運動場空調設備整備事業」についてです。
日本一の猛暑のまちとなった本市では猛暑の体育館で子どもたちの命に危機が及ぶことすら危惧されます。児童生徒が安心安全な学校生活を送ることができるよう、また避難所としての環境改善を図るため、令和7年度中の出来るだけ早い時期に小学校6校及び中学校3校の屋内運動場に空調設備を整備して参ります。
次に「日本一の猛暑のまちへの対応」についてです。
市民や観光客参拝客の生命を災害級の暑さから守るため、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の増加はもちろん天満宮参道でのミストシャワー設備の設置などの熱中症対策を行い猛暑対策先進都市を目指して参ります。また、公共施設の空調の更新についても併せて進めて参ります。
次に「地球温暖化対策の推進」についてです。
ゼロカーボンシティの実現をさらに進め、戸建住宅用再生可能エネルギー発電等設備等の助成を継続して行って参ります。さらに、市役所公用車にも電気自動車を導入します。また、市民お一人おひとりの生命健康を守るため、特に気候変動の影響を受けやすい高齢者に対しエアコン購入費用の助成を新たに開始します。
次に「日本一の猛暑のまちを生かした観光施策展開」についてです。
「日本一の猛暑のまち」を好機と捉え観光資源として情報発信するとともに、猛暑でも楽しめるスイーツや「涼」をテーマにしたイベントなどを開催し、楽しみながら暑さに負けない観光施策展開を進めて参ります。
その他にも、夏休みプール開放事業やごみ減量の推進などの予算も活用して参ります。
3つ目の「地震災害をはじめとした災害対応パッケージ」には約11億円を計上しております。地震をはじめ大規模な自然災害はいつ発生するか分からないため、日ごろから訓練などを通して備える必要があります。加えて、国際観光都市である本市として観光客及び参拝者の生命財産を守るための危機管理にも取り組むことが大切です。
具体的にはまず、「観光・参拝危機管理マニュアルの策定」についてです。
人口の100倍を超える観光客参拝客等が訪れる本市において災害発生時に市民や観光客等の生命を守るとともに、災害発生後の市内観光産業の早期回復や事業継続に向けた支援等を行うための観光・参拝危機管理マニュアルの策定を進めて参ります。
次に「地震災害対応訓練」についてです。
大規模災害が発生した際に新しい公共の視点を持って市民や自治会、民間企業、来訪者等が的確な対応をとることができるようより実践に即した訓練を目指します。また、自衛隊、消防、警察などの関係機関と連携を図り、防災体制の強化に取り組んで参ります。
次に「防災備蓄機能の強化」についてです。
能登半島地震の教訓から、大規模な災害が発生した場合は女性や高齢者、乳幼児、外国人など様々な人が避難することが想定されることから、それぞれの状況に配慮した対応ができるよう備蓄品の計画的な購入及び発動発電機等の購入を行って参ります。
次に「常備消防の管理運営」についてです。
太宰府市及び筑紫野市で構成される筑紫野太宰府消防組合消防本部の管理者を令和5年度から本市市長側も輪番で務めるように変更され、より一層管轄する地域の安心安全を守るため消防・救急・自然災害等への対応が迅速に行えるよう取り組んでいますが、負担の増加が今後の課題となってきます。
その他にも、消防団活動支援事業、防災体制の強化、道路冠水対策の推進、木造戸建て住宅性能向上改修等促進事業、ブロック塀等撤去促進事業、ため池の防災対策推進などの予算も活用して参ります。
4つ目の「現代危機への対応パッケージ」には約1億円を計上しております。特に子どもたちが犠牲となる道路交通混雑や飲酒運転による交通事故が増加しており、市民の尊い命を守ることが大切です。また、宅地開発等による里山の減少で頻発する鳥獣被害への対応も重要です。
具体的にはまず、「通学路交通安全対策の推進」についてです。
防護柵設置のハード対策や交通規制・交通教育のソフト対策などを行い、登下校時における児童生徒の安全の確保にさらに強力に取り組んで参ります。
次に「自転車用ヘルメット着用の啓発推進」についてです。
令和5年より着用が努力義務化された自転車用ヘルメットについて、特に子どもたちの命を守るため着用の重要性周知に取り組んで参ります。
その他にも、飲酒運転撲滅運動の推進、鳥獣被害防止対策の推進などの予算も活用して参ります。
次は2項目め 2つ目の柱であります「子どもまんなかの施策展開」についてです。
子どもを令和の都だざいふの宝としてまんなかに位置付け、絶対的にその命を守り、すくすくのびのびと成長できるよう、更なる居場所や出番づくりなど子ども施策を推進していきます。また、このことにより出生数や子育て世代の増加を促し、本市の自立持続可能性をさらに高めていくことを目指し、約40億円を計上しております。
その中でもまず「子どもまんなかパッケージ」を設定し、約33億円を計上しております。令和の都だざいふの宝である子どもたちが地域や学校などで安心して健やかに過ごすことができるよう支援していきます。
その中核は、やはり日本一の猛暑のまちパッケージでも掲げた「小中学校屋内運動場空調設備整備事業」です。出来る限り暑くなる夏前に設置できるよう急いで参ります。
次に「全世代交流フリースペースの活用推進」についてです。
いきいき情報センター1階の全世代交流フリースペースは、多くの学生に自習スペースとして利用されるなど賑わいをみせています。令和7年度は自習スペースの拡張を行うとともに、eスポーツ体験会の開催など全世代の交流ができる場所としてフリースペースの有効活用を図って参ります。
次に「公園遊具等の設置・整備」についてです。
ブランコをはじめ公園遊具等の設置・整備についてニーズが高まるなか、さらに積極的に実施するとともに、子どもたちや自治会などのニーズを把握するための調査を行って参ります。
次に「子ども医療費助成の拡充」についてです。
子育てにかかる経済的負担軽減策として、子ども医療費の助成をあらゆる世代で充実させるとともに、令和6年度に開始した高校生世代までの医療費の助成に加え、新たに中学生の通院への助成を拡充し、子どもの保健の向上と福祉の増進を図って参ります。
次に「学業院中学校施設整備事業」についてです。
学業院中学校の管理棟、教室棟、屋内運動場については、施設の老朽化や教室不足等に対応するため改築や長寿命化等の施設整備を実施し、教育環境の向上を図って参ります。その際、歳出入一体改革の視点を持って、民間プール等を活用した水泳授業委託によって使用しなくなる屋外プールを解体しスペースを有効活用して参ります。
次に「学校施設バリアフリー化等施設整備事業」についてです。
全ての児童生徒が安心安全な学校生活を送ることができるよう、太宰府東中学校にエレベーターの設置を進め学習環境の整備を行って参ります。
次に「学童保育所増設事業」についてです。
太宰府小学校の教室不足等に対応するため、歳出入一体改革の視点を持って民間プール等を活用した水泳授業委託によって使用しなくなった屋外プールを解体し、学校用地の有効活用を図りながら、学童保育所を整備します。
次に「学童保育所多子利用世帯助成事業」についてです。
きょうだいが同時に学童保育所に入所している世帯の経済的負担の軽減を図るため、第2子以降の利用料の助成を開始し、保護者の仕事と子育ての両立の支援を拡充するとともに、少子化対策を推進して参ります。
次に「放課後子ども教室の拡充」についてです。
令和7年度も実施校を拡充するとともに、さらに新しい公共の視点を持って地域活動サポーターの積極的な地域活動への参画を促して参ります。
その他にも、太宰府西小学校管理教室棟長寿命化改良事業、太宰府小学校長寿命化改良事業、太宰府東小学校教室棟増築事業、待機児童ゼロへの取組推進、届出保育施設運営支援、教育DX推進事業、子どもの権利条例の策定、ひとり親家庭への支援などの予算も活用して参ります。
2つ目の「給食パッケージ」には約4億円を計上しております。本市の弱みであった給食事業は、市内に新調理場を誘致した民間事業者による給食の提供により安心安全の担保、経済税収効果の向上や維持保存費用の抑制など複数のメリットがある強みとなりました。加えて給食費補助も行い、子どもまんなか施策の中核に位置付けます。
具体的にはまず、「小・中学校給食費の助成」についてです。
物価高騰が続くなかでも令和の都だざいふの宝である子どもたちが安心して栄養バランスのとれた食事を摂られるとともに子育て世代の負担を軽減し手取りを増やすため、引き続き前年度小・中学校給食費の3割助成を行います。併せて、国・県による給食無償化への呼び水にもして参ります。実際に、昨日の自公維合意で2026年度まずは小学校給食無償化の方針が示されたところです。
次に「中学校給食の実施」についてです。
小学校と連携しながら、物資の安定供給や衛生管理の徹底、アレルギー対応等、生徒に安心安全な給食の提供を行うとともに、活発な食育活動を実施し、年間を通して安心安全な給食の提供ができるよう取り組んで参ります。
次に「小学校給食の実施」についてです。
中学校と連携しながら、児童の心身の健全な発達のため、栄養バランスのとれた豊かな食事を提供し健康の増進、体位の向上を図ります。また、チャレンジクッキングだざいふ、友好都市・姉妹都市記念給食など児童の食への興味関心を高める活動の充実を図って参ります。
3つ目の「世界に羽ばたく人材育成パッケージ」には約3千万円を計上しております。令和の都だざいふから世界に羽ばたく人材を更に育成するべく、子どもたちが意欲を持って自主的にチャレンジする風土を整えます。
具体的にはまず、「学生まちづくり課題解決プロジェクト・子ども学生未来会議」についてです。
小学校から大学までの児童生徒・学生から学校現場や本市の課題解決につながる提案を受け、子ども学生未来会議の場などで議論し、予算を付けてまちづくりに実際に反映する取組を通じ、子どもや学生のまちづくりへの関心を高め、令和の都だざいふから世界に羽ばたく人材の育成を図って参ります。
次に「世界に羽ばたく人材育成表彰・子ども学生美術展」についてです。
令和の都だざいふらしい次代を担う若い才能を顕彰し育成する取組として推し進め、次代を担う若者の目標とされる表彰及び美術展に進化させて参ります。
次に「九州国立博物館ツアーズ」についてです。
市立小・中学校の児童生徒に本市が誇る九州国立博物館の特別展を観覧する機会を設け、世界中の様々な文化に触れながら学習することで、より豊かな教養と感性を身につけグローバルな視点をもった子どもを育て、世界に羽ばたく人材育成を推進するとともに、九州国立博物館との更なる連携を図って参ります。
次に「高大連携の強化」についてです。
学問のまちだざいふの強みである4高校・5大学短大との連携を太宰府キャンパスネットワーク会議などを通じてさらに密にし、学生の飛躍と本市と交流人口関係人口の相互発展などにつなげて参ります。
その他にも、学力向上への取組推進、全国大会出場子ども・学生等への支援、文化芸術振興事業、文化芸術奨励制度、友好都市・姉妹都市学校との連携などの予算も活用して参ります。
4つ目の「ひきこもり・不登校等対策パッケージ」には約1億円を計上しております。子どもたちの不登校やひきこもりの高齢化などが更に社会問題化するなか、不登校の子どもたちへの更なる支援や全世代的にいきることをサポートし、居場所と出番をつくることがますます重要だと考えます。
具体的にはまず、「不登校児童生徒への給食費助成」についてです。
令和の都だざいふの宝である子どもたちが等しく安心して栄養バランスのとれた食事を摂ることができるよう、不登校児童生徒に対しても小・中学校給食費の助成と同等の支援を行って参ります。
次に「メタバースを活用した不登校支援事業」についてです。
不登校児童生徒の支援として、メタバースを活用した新たな居場所を提供して参ります。また、既存の支援事業とつながりを持たせたバーチャルとリアルのハイブリットな支援を実施し、児童生徒の自立につなげて参ります。
次に「不登校児童生徒支援の推進」についてです。
令和6年度から開始した本市ならではの不登校児童生徒支援として、全ての小・中学校にサポートティーチャー(ST)の配置及びサポートルームの設置並びに全ての中学校ブロックにスクールソーシャルワーカー(SSW)を配置します。
その他にも、子どもの居場所づくり事業、地域の居場所づくり推進事業、孤独・孤立対策の推進、自殺対策事業などの予算も活用して参ります。
5つ目の「安心の産前・産後ケアパッケージ」には約1億円を計上しております。子どもたちを令和の都だざいふの宝としてまんなかに位置づけるにおいて、産前・産後ケアは非常に重要なテーマです。こうした考えのもと新規事業や従来事業の拡充を思い切って行います。
具体的にはまず、「1か月児健康診査事業」についてです。
新たに生後6週に達しない乳児の健診費用助成を開始します。経済的負担を軽減するとともに乳児の疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止して参ります。また、乳児の健康状態を早期に把握することで、妊婦等への包括相談支援を効果的に実施し、養育者の育児不安の軽減を図って参ります。
次に「妊婦歯科健康診査事業」についてです。
母体の歯周病感染は、低出生体重児誕生のリスクになるとともに、妊娠期の歯科口腔管理は産婦と乳児のその後の健康増進に大きく影響することから、妊婦の歯科健診費用助成を新たに開始し、妊娠期の口腔管理能力を向上することで、妊婦及び乳児の口腔疾患予防と低出生体重児の発生を予防して参ります。
その他にも、産婦健康診査事業、産後ケア施設整備費補助事業、産後ケア事業の拡充、妊婦等包括相談支援及び妊婦支援給付金の一体的実施、こども家庭センターの充実、初回産科受診料の支援、多胎妊娠妊婦の健康診査支援、新生児聴覚検査などの予算も活用して参ります。
次は3項目め 3つ目の柱であります「市民と交流人口・関係人口の相互発展」についてです。
令和の都だざいふとしてさらなる飛躍を期すとともに、住まう人も訪れる人もともに慶び合えるまちとして、観光客参拝客からの経済税収効果を飛躍的に高め、市民メリットを体感できる仕組みを創ることを目指し、約16億円を計上しております。
その中でもまず「令和の都だざいふパッケージ」を設定し、約2億円を計上しております。元号令和発祥の地として、西の都に留まらぬ令和の都だざいふの魅力を更に高めていく取組がますます重要だと考えます。
具体的にはまず、「令和国際文化会議」についてです。
令和の都だざいふにふさわしい取組の中核として、天平の世の先進的な国際シンポジウムとされる梅花の宴を現代によみがえらせる国際的文化的会議を開催します。
次に「梅花の宴再現」についてです。
令和の都だざいふの誇りとしてかねてより梅花の宴の再現を行ってきましたが、令和2年度から全国の関連自治体を巡り開催してきた「令和の万葉大茶会」の集大成として、「大阪・関西万博」で開催する「令和の万葉大茶会2025年あすか万博大会」において「梅花の宴」を行い、令和万葉、元号令和の発祥の由縁となった本市を世界に発信して参ります。
次に「特別史跡大宰府跡整備基本設計」についてです。
令和の都だざいふのまちづくりの中核として令和6年度に策定した特別史跡大宰府跡整備基本計画に基づき、整備基本設計の策定を進めて参ります。史跡環境の維持向上、史跡としての更なる発展を目指し、史跡の価値の保存と古代大宰府が感じられる心地よい空間の保全・継承を第一としながら、官民連携による先進的多用途活用に資する環境整備のための設計を実施して参ります。
その他にも、「令和の都だざいふ」周遊促進に向けた観光拠点施設の官民連携事業化検討業務、指定文化財保存整備の推進、市民遺産の育成支援、歴史的街なみの保全などの予算も活用して参ります。
2つ目の「交流人口・関係人口による経済税収効果パッケージ」には約9億円を計上しております。ふるさと納税制度はまさしく交流人口・関係人口による経済税収効果向上の象徴と言え、こうした果実を市民に積極的に還元していくことが重要です。
具体的にはまず、「ふるさと納税の推進」についてです。
ふるさと納税を市民と交流人口・関係人口の相互発展の中核に位置付け、更なる競争力のある返礼品の拡充、積極的な営業活動等による寄附額増を目指し、より有効な市民への還元に取り組んで参ります。また、梅プロジェクトにとどまらない地場産品の更なる充実や地域の資源を生かした域内経済循環の仕組みについて検討し、ふるさと納税との連動へとつなげて参ります。
次に「市街地の活性化」についてです。
交流人口・関係人口による経済税収効果を高めるべく、五条駅前をはじめとする公共施設の再編について調査を重ねるとともに、現在の都市計画マスタープランと策定中の立地適正化計画及び関連計画との整合・連携や都市計画に対する市民意向等の実態把握を行い、ニューだざいふ的な観点で今後の都市計画マスタープラン等のあり方について検討して参ります。
次に「令和の都だざいふ「梅」プロジェクトの推進」についてです。
太宰府梅園構想のもと、史跡地を中心に更なる梅の植栽を行うとともに、梅の栽培管理体制について検討を進めて参ります。また、市内外の人々の知識や行動力の集結によって、梅資源を核とした産業の創出だけでなく、住まう人も訪れる人も楽しむことができる「真の梅のまち」を目指して参ります。
次に「ユニバーサルツーリズムの推進」についてです。
令和の都だざいふらしい観光として年齢や障がいの有無などに関係なくすべての人が安心して観光を楽しめるユニバーサルツーリズムを推進するため、ユーザー目線での情報も確認することができるユニバーサル地図/ナビを導入し、情報発信を行うとともに、移動に対する不安から本市を訪れることをあきらめていた人にも安心して本市を訪れ、観光を楽しんでいただける取組を推進して参ります。
次に「誰もが楽しめる観光回遊ルートの充実」についてです。
令和の都だざいふらしいナイトエコノミーやスイーツ・グルメの開発など太宰府天満宮周辺の観光客を市内の史跡文化財や観光施設に誘客する仕組みを構築し、多地点回遊による滞在時間増加や観光消費を促して参ります。
その他にも、史跡の先進的多用途活用、先端技術を用いた文化財の活用、日本一の猛暑のまちを生かした観光施策展開、西鉄沿線活性化協議会共同プロモーションなどの予算も活用して参ります。
3つ目の「オーバーツーリズム対策パッケージ」には約3億円を計上しております。本市を代表する積年の課題として観光公害、いわゆるオーバーツーリズムの問題があげられます。他市に先駆けて開始した歴史と文化の環境税導入をはじめこれまでも積極的に取り組んで来ましたが、ごみのポイ捨て問題などについて参道周辺店舗などと更なる連携が必要です。
具体的にはまず、「オーバーツーリズム対策事業」についてです。
観光客参拝客の受け入れと市民生活の質の確保を両立しながら、持続可能な住まう人も訪れる人もともに慶び合えるまちづくりを実現するため、新たなオーバーツーリズム対策の一環として、参道周辺店舗に対するゴミ袋の配布や参道周辺の清掃強化に取り組んで参ります。
次に「公共施設等市外者料金設定」についてです。
令和6年度に導入した太宰府史跡水辺公園への通年での市外者料金設定により増収効果が見込まれるところです。公共施設等の利用に係る受益と負担の適正化の観点から観光客参拝客をはじめ市外の利用者に応分の負担を求め、市民と交流人口・関係人口の相互発展が図られるよう公共施設等の市外者料金の設定についてさらに検討を進めて参ります。
次に「交通情報案内システムの充実」についてです。
本市独自の交通情報案内システムについて、駐車場満空情報を自動判定することができる駐車場を増やし、正確でリアルタイムな情報を観光客参拝客に配信することで、より観光参拝の分散化と公共交通への利用転換を促し、本市積年の課題である渋滞の緩和に向け、更に注力して参ります。また、市民の利用促進にも取り組んで参ります。
次に「歴文税の活用」についてです。
歴史と文化の環境税は、社会先進的な課題解決を図るために観光客など一時有料駐車場の利用者に負担いただく本市独自の法定外普通税です。本税を財源として歴史的文化遺産や観光資源等の整備活用、観光客のおもてなし施策、渋滞緩和対策などの事業に重点的に取り組んで参ります。
その他にも、観光・参拝危機管理マニュアルの策定、市民も観光客もメリットを体感できる美化活動の推進などの予算も活用して参ります。
4つ目の「道路改良パッケージ」には約1億円を計上しております。市民と交流人口・関係人口の相互発展において、道路状況は非常に重要なテーマであり、継続して事業に取り組んでいくことが重要です。
具体的にはまず、「国分坂本地区道路改良」についてです。
宅地開発等による人口増などから渋滞等の混雑が発生している国分坂本地区において、坂本2丁目交差点における交差点改良設計を実施し、混雑緩和に向けた方策の検討を進めて参ります。
次に「水城小裏西側交差点改良」についてです。
水城小学校西側に位置する交差点は変則五差路となっており、児童等の通学時に車との接触の可能性があるなど危険性が高い状況となっていることから、安全な交差点への改良に取り組んで参ります。
その他にも、県と緊密に連携しつつ筑紫野古賀線の整備促進、観世音寺二日市線の整備促進、舗装個別施設計画に基づく舗装工事などの予算も活用して参ります。
次は4項目め 一つ目の底流であります「新しい公共をテーマとした仕組みづくり」についてです。
市と自治会、教育や子育て、まちづくり、防犯や防災、医療や福祉団体等の多様な主体が参画し、対話と協働を進めることで、連携しながら社会課題の解決を図る仕組みを創ることを目指し、約4億円を計上しております。
その中でもまず「新しい公共の仕組みづくりパッケージ」を設定し、約2億円を計上しております。多様な主体と連携・協働を図るとともに、多様な主体を育てる取組も大切です。
具体的にはまず、「新しい公共座談会の実施」についてです。
今日抱えている社会課題は多様化複雑化し、従来のように自治体のみで機動的に対応することが困難になってきております。そのため、自治会、教育や子育て、街づくり、防犯や防災、医療や福祉団体等の多様な主体が参画し対話と協働を進めることで、連携しながら社会課題の解決を図って参ります。
次に「公園・公民館・公共施設の再定義、多面的な利活用の検討」についてです。
公園や公民館、公共施設などに求められる役割や意義について様々な観点から再整理を行い、公共施設の再定義や多面的活用について検討し、新しい公共の仕組みづくりにつなげて参ります。
次に「地域の居場所づくり推進事業」についてです。
新しい公共の仕組みづくりの具体的取組として、子どもから高齢者、不登校児童、ひきこもり者、障がい者など地域の方が気軽に安心して参加できるコミュニティ食堂を開催する団体に助成を行い、みんなが集える居場所づくりの取組をさらに充実して参ります。加えて、様々な関係機関、団体及びボランティア等と連携することで、全ての人の居場所や地域課題の早期解決につなげ、地域コミュニティの活性化を推進して参ります。
その他にも、地震災害対応訓練、放課後子ども教室の拡充、地域コミュニティの活性化、新しい公共の担い手支援、地域ボランティア活動支援、地域猫活動の推進、地球温暖化対策の推進、ごみ減量の推進などの予算も活用して参ります。
2つ目の「公共交通パッケージ」には約3億円を計上しております。運転士不足や燃料高騰など公共交通を取り巻く環境は厳しさを増していることから、市民の移動手段を何としても確保するという強い決意を持って持続可能な公共交通を実現する取組が重要です。
具体的にはまず、「路線バス運行の維持」についてです。
地域公共交通を取り巻く環境は、車社会化、人口減少等の影響による輸送需要の縮小に加え運転士の不足や働き方改革、経済合理化などにより厳しさを増しております。本市においても市民生活に欠くことのできないの移動手段の一つである民間の路線バスについて、将来にわたり持続可能な地域公共交通を再構築できるまでの間、運行に係る費用を補助することで路線バスの維持・存続に努めて参ります。
次に「第二種運転免許取得支援事業」についてです。
市民の就業機会の拡大や乗合バス・タクシー等の運転士を確保するため、第二種運転免許取得費用の一部を支援することで市内を運行する乗合バス・タクシー事業者の維持・確保を図り、本市にとって持続可能な公共交通の実現を目指して参ります。
次に「地域公共交通再構築検討」についてです。
コミュニティバスや路線バス等の利用実態や運転士不足の課題、問題点などを踏まえ、住民や観光客参拝客の利便性維持・向上に向けた持続可能な公共交通体系の再構築について検討を行って参ります。
その他にも、地域公共交通計画の策定、総合交通計画の改訂、コミュニティバスの運行、デマンド交通実証実験事業などの予算も活用して参ります。
次は5項目め 2つ目の底流であります「歳出入一体改革の推進」についてです。
多様化し拡大する市民ニーズに応えつつ持続可能な行財政運営を堅持するため、戦略的まちづくりや一体的情報発信、地域経済の活性化など歳出入一体改革を図ることを目指し、約19億円を計上しております。
その中でもまず「戦略的まちづくりパッケージ」を設定し、約2億円を計上しております。少子高齢化、物価高騰、人件費増など困難な課題が山積する近年、職員一人ひとりが意欲を持って情報を収集し、国や県、民間企業などと積極的に連携し、戦略的なまちづくりを行うことがますます重要です。
具体的にはまず、「課題解決先進モデルの実現」についてです。
まちづくりビジョン会議からの専門的な知見や地域に即した意見などを参考としながら、各種施策や事業についての市民の意見や評価等を把握するための市民意識調査を行い、まちづくりの指標として各種施策の展開に反映させて参ります。さらに、職員が自主的に先進地を視察し、自治体や企業、住民といった地域の主体者が連携して特色のある施策を推進するなど更なる戦略的まちづくりに努め、市政積年のもしくは社会先進的な課題解決モデルを実現して参ります。
次に「課題解決調査」についてです。
本市市政積年のもしくは社会先進的な課題である五条駅前をはじめとする公共施設の再編、西鉄太宰府駅前をはじめとする観光・史跡地案内サイン等の設置や梅林アスレチック公園はじめグランド照明の設置、地域商社の立ち上げ、多地点回遊・丸一日滞在の促進、総合窓口の設置等について、課題の抽出や手法の検討、基本方針の整理など課題解決のための調査・検討を行って参ります。
次に「人材育成・登用・働き方改革」についてです。
研修制度や人事評価制度の改善を図り、本市職員としての意識の醸成、自ら学ぶ意欲を高め、更には、就職氷河期を含む幅広い世代を対象に、優秀で多様な人材の積極的な職員採用を行い、組織の活性化に努めて参ります。また、全ての職員が安心して働ける職場づくりを目指して、育児休業の取得促進や残業の抑制などを図って参ります。
次に「すぐやる班」についてです。
市で対応可能な作業や頻発する鳥獣被害対策など市民ニーズに素早く対応するため、すぐやる班の活動を継続し推進して参ります。
その他にも、公共施設等市外者料金設定、DXの推進、窓口交付の利便性向上などの予算も活用して参ります。
2つ目の「一体的情報発信パッケージ」には約1千万円を計上しております。
市政、観光、防災などの情報を市として一体的に発信することで、宣伝効果を最大限に高め交流人口・関係人口の更なる拡大やリピーター化を実現するとともに、コストを効率化することで歳出入の一体的改革につなげます。
具体的にはまず、「シティプロモーションの推進」についてです。
本市の宣伝効果を最大限にするべく、おとものタビットを活用したプロモーションのほか西鉄福岡(天神)駅等のデジタルサイネージを活用した観光情報発信など効果的なシティプロモーションを行って参ります。また、西鉄太宰府駅へのデジタルサイネージ設置など、新たな情報発信手段についても調査研究を進めて参ります。
次に「サイン統一に向けての検討」についてです。
本市の一体的な情報発信を行うことで宣伝効果を最大限にするべく、令和の都だざいふをコンセプトとした市内の観光サイン・史跡地案内サイン等のデザイン統一に向けて、ガイドラインの改定を検討して参ります。
次に「新たな情報発信手段の検討・構築」についてです。
本市の宣伝効果を最大限にするとともに市民と交流人口・関係人口の相互発展を実現するべく、市政情報、観光情報、防災情報などの発信も含めた一体的な情報発信について検討を行って参ります。
その他にも、令和の都だざいふ応援大使の活用などの予算も活用して参ります。
3つ目の「地域経済活性化パッケージ」には約4億円を計上しております。本市にとって企業や商業施設、ホテルなどを誘致し法人税収を高めるとともに交流人口・関係人口の更なる拡大やリピーター化につなげることは積年の課題と言え、戦略的にその誘致に努めなければなりません。
具体的にはまず、「企業・商業施設等誘致推進体制の強化」についてです。
本市の企業誘致戦略に基づき、民間のコンサルティング事業者のノウハウを生かしながら、地方への進出を目指す企業との商談による企業誘致を継続するとともに、市民生活の利便性向上のための商業施設等の誘致を行い、あわせて雇用と経済税収効果の向上も図って参ります。また、地域課題の解決を目指す地域商社設立の可能性を検討して参ります。
次に「地域経済の発展・保護」についてです。
商工会と連携して地場産業育成を進めるとともに、市内での起業創業を促すため、創業時の経費に対する補助や地域課題解決を図る創業者への創業時の家賃補助などを継続して実施することで起業創業支援に取り組み、経済税収効果の向上を図って参ります。さらに、物価高騰の影響を受けるLPガス消費者や運送事業者等への補助、プレミアム付商品券の発行など地域経済の活性化に取り組んで参ります。
次に「宗教法人、学校法人、九州国立博物館等との連携強化」についてです。
福岡県、太宰府観光協会、太宰府天満宮などと連携して九州国立博物館開館20周年を記念したイベントを実施し、各団体との連携を強化するとともに本市が誇る九州国立博物館の魅力を発信して参ります。また、1957年に開園した子どもから大人まで楽しむことが出来るだざいふ遊園地との連携についても検討して参ります。さらに、新たに開校を目指す福岡国際音楽大学(仮称)も含め市内高校大学との連携をさらに進め、教育文化水準の向上や地域経済への好影響、地域コミュニティの活性化、人口減少対策や関係人口の拡大、地域ブランディングなどに取り組んで参ります。
4つ目の「歳出入一体改革パッケージ」には約13億円を計上しております。
これまでも歳出入一体改革を意識しながら先進的な事例を生み出してきましたが、更なるヒットを生み出していくことが必要です。
具体的にはまず、「民間プール等を活用した水泳授業委託」についてです。
本市がいち早く取り入れ実践してきた民間プール等を活用した水泳授業については授業環境の飛躍的向上を図ることができるとともに、経済税収効果の向上や改修費用の抑制など複数のメリットがある取組です。令和7年度は、更に実施校を増やし全小学校で実施して参ります。
次に「学校プール跡地の有効活用」です。
民間プール等を活用した水泳授業委託の取組により使用しなくなる太宰府小学校、水城小学校、学業院中学校の屋外プールについて、令和7年度に解体し学校用地の有効活用を図って参ります。
次に「ネーミングライツ制度の検討」についてです。
様々な市民ニーズに応えるための新たな財源確保、企業の社会貢献の場の提供及び施設の良好な維持管理による市民サービスの向上などが見込まれるネーミングライツ(公共施設等への愛称を付与する権利)を公共施設等に導入し、民間事業者の力を借りながら、資産の有効活用、一層の魅力向上及び地域の活性化を目指して参ります。
その他にも、「令和の都だざいふ」周遊促進に向けた観光拠点施設の官民連携事業化検討業務、中学校給食の実施、ふるさと納税の推進、公共施設LED化の推進、令和の都だざいふ「梅」プロジェクトの推進などの予算も活用して参ります。
その他の重点事項として、誰もが居場所と出番を持てる令和の都だざいふを目指し、約3億円を計上しております。
その中でもまず「氷河期世代対策はじめ社会課題解決パッケージ」を設定し、1千万円余りを計上しております。これからの大きな社会課題となりうる問題に先進的に取り組みます。
具体的にはまず、「就職氷河期世代の職員採用」についてです。
私もそのど真ん中で、30社以上の入社試験に落ち、唯一内定をもらった会社もミスマッチで一年余りで退職しましたが、就職氷河期に正規雇用の機会を逃した人が非正規雇用としての就業や就労でのつまずきに起因する引きこもり等さまざまな課題に直面しております。これらは当事者と家族だけの問題ではなく本市やわが国の将来にかかわる重要な課題であり、まずは生活や就労に困難を抱える就職氷河期世代を含めた雇用促進に努めるとともに包括的な対策も検討して参ります。
次に「結婚支援の推進」についてです。
婚姻の減少こそが我が国の少子化の根本原因との認識が広まるなか、社会先進的な課題の解決に向け希望する誰もが安心して結婚や子育ての望みを叶えていける社会へと変革するため、多様な出会いの機会づくりを検討して参ります。また、多様性を受け入れ偏見のない社会を目指す流れの中で本市独自のパートナーシップ宣誓制度導入に向けて取組を進めて参ります。
次に「孤独・孤立対策の推進」についてです。
社会的課題である孤独孤立対策として、ひきこもり状態で途切れていた社会とのつながりを回復するため、当事者やその家族が抱える課題の整理・助言、コミュニケーション能力の回復、復学や就労等に向けた活動支援などひきこもり者の社会参加に向けた支援を行って参ります。
次に「自殺対策事業」についてです。
残念ながら失われた命は二度と戻ってきません。そして残された側のつらさも癒えることはないでしょう。特に若年層の自殺の増加が社会的課題となるなか、自殺対策を「いきるサポート」と位置付け、健康や生活、家庭などの様々な悩みを抱え、こころが落ち込んでいる方などに対し、精神科医と連携して「こころの健康」に関する相談窓口を設置することで、一人ひとりに寄り添った相談体制の充実を図って参ります。
その他にも、地域の居場所づくり推進事業などの予算も活用して参ります。
2つ目の「高齢者等支援パッケージ」には2億円余りを計上しております。高齢者等に積極的な支援を行います。
具体的にはまず、「帯状疱疹予防接種事業」についてです。
帯状疱疹は、加齢、疲労、ストレスなどによる免疫力の低下等が原因で発症し重症化することもあります。また、心筋梗塞や脳卒中のリスクを増加することも知られており、本市はいち早く令和4年より助成を始めました。令和7年度からは65歳以上の定期予防接種を開始し、病気の発症や重症化を抑え健康で安心して暮らすことができるよう取り組んで参ります。
次に「窓口におけるコミュニケーション支援システムの導入」についてです。
聴覚障がい者や難聴者等が市役所窓口で円滑なコミュニケーションを取ることができるよう、音声を認識して文字をディスプレイに表示する機器を導入し、障がい者等がいつでも安心して窓口に来庁することができる環境を整備して参ります。
次に「介護のしごと魅力発信・人材確保定着事業」についてです。
介護ニーズが高まる一方で介護人材の不足が生じており、安心した介護サービスを提供するために介護のしごとの魅力を発信するとともに、介護事業所の人材確保策に対する支援を行うなど介護人材の確保・定着を図って参ります。
次に「軽度・中等度難聴者の補聴器購入助成」についてです。
難聴は、必要な音が聞こえず家族や友人とのコミュニケーションをうまくとることができずに社会的に孤立しうつ状態に陥ることもあるなど様々な社会生活に支障をきたします。特に高齢者は、聴覚機能の低下は認知症発症リスクが高まると考えられております。令和7年度より、18歳以上で身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴者に対する補聴器の購入費用の助成を行い、コミュニケーション支援及び社会参加などを促進して参ります。
その他にも、住宅等防犯対策事業、骨粗鬆症検診事業、肺がん検診事業、認知症理解の普及啓発事業、敬老事業、シルバー人材センター支援、老人福祉センター事業、高齢者運転免許証自主返納支援事業、元気づくりポイント事業、長寿クラブ活動支援、予防接種事業、地域介護予防活動支援補助金上限額の見直し、アピアランスケア推進事業などの予算も活用して参ります。
3つ目の「人権・多様性の確保パッケージ」には8千万円余りを計上しております。あらゆる市民の人権や多様性を保障します。
具体的にはまず、「人権尊重のまちづくりの推進」についてです。
全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人が尊重され、いきいきと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを引き続き推進します。
次に「女性が少ない分野のジェンダーギャップ解消事業」についてです。
理工系分野を含めた女性が少ない分野への女性の興味・関心を高め、進路・職業選択における固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)の解消を図りながら、将来を担う女性人材の裾野の拡大に取り組んで参ります。
次に「子宮頸がん・乳がん個別検診事業」についてです。
女性のライフスタイルが多様化する中で、多くの人が受診しやすい検診を実施し、選択肢を広げることでがんの早期発見・死亡率の減少を目指して参ります。
その他にも、第3次男女共同参画プランの推進、女性相談事業、男女共同参画推進センタールミナスの充実、外国人への支援、障がい者プラン策定、地域福祉計画策定、軽度・中等度難聴者の補聴器購入助成、福祉タクシー料金助成事業、医療的ケア児等在宅レスパイトケア支援事業、バリアフリー情報・施設整備事業、窓口におけるコミュニケーション支援システムの導入などの予算も活用して参ります。
以上、楠田市政二期目最終年度の集大成・総仕上げとして、第2期総合戦略の4つの構想・戦略とそれに基づく二期目公約に加え本年度新たに位置付けた市政積年のもしくは社会先進的な課題の解決に向けた5つの最重点事項(3つの柱と2つの底流)を有機的に組み合わせた「好循環を次代につなぐ集大成予算」について説明してまいりました。
時間の限りもあり、市政積年のもしくは社会先進的な課題の解決に踏み出すための最重点5項目をもとに説明して参りましたが、予算説明資料の世代・カテゴリ別予算額で分類しておりますように、あらゆる世代や立場の方々に居場所と出番があるよう満遍なく行き渡ることも意識した予算となっております。
結びになりますが、本予算案の一つにセブン銀行ATMの設置があります。2年余り前JAの事情に従いやむなくATM撤去に同意したのですが、その後の市民の利便性の低下を考えればもっとやりようがなかったものかとずっと後悔してきました。今回その復活が別の形であれ実現し、胸を撫で下ろしています。
同じようにいま、地域公共交通を始め先方事情や財政状況、人員不足などにより市民サービスが脅かされるケースが増えつつあります。西鉄という相手がある話なのでなどと言い訳していては、本当の意味で世の為人の為に持ちうる力を出し尽くしているとは言えないと自らを鼓舞しながら頑張って来ました。
市をあげてさまざまなレベルで路線の存続を求め粘り強く協議を重ねてきた結果、何とか一年は延長する方向となりましたが、今後も予断を許しません。我々公僕としての厳しい宿命ではありますが、その任にある限り相手がどんなに強大であっても、市の為市民の為に立ち向かって行かなければなりません。
そして最後は、次代を担う子どもたちの為にと思い定めています。スケボーパークにせよバスケのゴールにせよブランコにせよ、子どもたち一人ひとりからの期待を受け、力の限り頑張りぬき、信頼に応えることこそ政治家・市長として、大人として、そして人としての究極の使命、やりがいだと信じています。
つまりはこの言わば「信頼関係の好循環」こそ最も次代につなぐべきことだと考えます。もちろん今回の予算案施政方針でも限界があるかもしれませんが、私のいま持ちうる力は一定出し切ったとの思いもあります。議員各位、市民の皆さまのご理解ご協力を伏してお願い申し上げ、施政方針の結びと致します。
令和7年2月26日
太宰府市長 楠田 大蔵