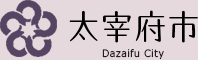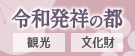本文
施政方針(令和6年第1回(3月)定例会・令和6年2月27日)
本日ここに、令和6年第1回定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては大変ご多用の中をご参集賜り、厚く御礼を申し上げます。
この定例会は、令和6年度予算案をはじめ、主要施策並びに条例案などをご審議いただくひと際重要な議会ととらえております。議案提案に先立ちまして、まずは令和6年度の市政運営に臨む私の所信を披歴し、議員各位や市民のご理解とご協力を心からお願い申し上げるものであります。
さて、本年の幕開けは大変大きな衝撃で始まりました。元日早々の能登半島地震では多くの命が失われ、今なお多くの方々が避難生活を余儀なくされております。改めてそうした方々にお悔やみとお見舞いを申し上げます。
本市としましても、職員が石川県穴水町に赴き被災地支援を行ってくれております。その働きが認められ、先日は視察に訪れた岸田首相より直々に労いを受けたと報告も受けました。今後も息長い支援に努めて参ります。
また、毎年のように豪雨被害に苛まれておりますが、現在は逆に深刻な水不足の懸念がございます。昨日副市長をトップとした太宰府市節水推進本部を設置しましたので、一層の節水を促す啓発活動を強化して参ります。
さらには、先日も火災により市民の尊い命が失われました。昨今は救急出動の増加もあり、筑紫野太宰府消防本部でも出動遅れの事例が複数起きています。新管理者としてより一層の信頼確保と使命完遂に努めて参ります。
一方、悲願でありました中学校完全給食がスタートしました。子どもたちが満面の笑みで食べる歴史的瞬間に立ち会えまさに市長そして政治家冥利に尽きるものとなりました。皆様のご理解ご協力に心より感謝申し上げます。
最新のアンケートでも保護者は8割以上、子どもたちも約6割が満足との結果が出ました。昨日みやま市で痛ましい事故が起きましたので、今後も細心の注意を図りながら進めて参ることをお誓いし、本題に入ります。
令和6年度の当初予算案は、楠田市政二期目の公約「令和の都さらに羽ばたく太宰府~課題解決先進都市を目指して~」に基づき、最終年度を迎える第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略(まちづくりビジョン)の集大成を念頭に置きながら、本市市政積年のもしくは社会先進的な課題の解決にも敢然と踏み出す「令和の都だざいふ課題解決予算」と銘打ちました。
従来の総合戦略の重点の中でも、危機管理の徹底強化、子どもまんなかの施策展開、市民と交流人口・関係人口の相互発展、新しい公共をテーマとした仕組みづくり、歳出入一体改革の推進という市政積年のもしくは社会先進的な課題の解決を最重点事項と位置付け予算化した結果、昨年度を3.8%上回り本市初の大台となる300億円を上回る予算案となりました。
こうした総額を可能としたのは、歳入面において市税は現政権による定額減税分の影響を除けば3億円余の増加が見込まれ、ふるさと納税も20億円の大台を見込むことから、併せて100億円を大きく超えるところまで大幅増加してきたことがあげられます。このため自主財源の割合も42.7%、減税の影響を除けば43.8%と、かつてと比べかなり充実してきました。
それでは、令和6年度予算案について市政積年のもしくは社会先進的な課題の解決に踏み出すための最重点事項5項目を中心に説明して参ります。また、新たな試みとして関連する複数の事業を1つのパッケージとしてまとめることで、より明確かつ分かりやすい重点メッセージとするとともに、組織縦横断的に取り組みより効果を高めていくことを目指しています。
まず1項目め「危機管理の徹底強化」についてです。
これからの時代は、常に災害や犯罪などの危機があると認識し、大規模な自然災害などから市民や観光客などの生命財産を守るための体制の整備、訓練及び情報発信などを徹底強化していくことを目指し、約3億6千万円を計上しております。
その中でもまず「地震災害をはじめとした災害対応パッケージ」を設定し、約1億円の予算を計上しています。年始の能登半島沖地震でも明らかなように、地震をはじめとした大規模な自然災害の際やはりトイレの問題が切実であり、加えて市民や観光客などの生命財産を守るための体制の整備、訓練及び情報発信などを複数の事業を通して組織縦横断的に取り組むことが大切です。
具体的には、まず、「災害対応トイレトレーラーの導入」についてです。
大規模災害が発生した場合のトイレ不足を解消するため、安全で衛生的で機能性の高い災害対応トイレトレーラーを導入し、災害発生時への備えを強化して参ります。また、全国で災害が発生した場合には、本市のトイレトレーラーを派遣して支援することを可能とします。
次に「観光案内所周辺における観光・防災情報発信用電光掲示板の設置」についてです。
気候変動等の影響により我が国の災害は、激甚化・頻発化の傾向があり、自然災害のリスクが上昇しています。このような中、災害発生時に災害・防災情報等をリアルタイムに伝え、本市を訪れた観光客や外国人、聴覚障がい者などの生命財産を守るため、観光案内所周辺に観光・防災情報発信用電光掲示板を設置し、災害発生時への備えを強化して参ります。
次に「地震災害対応訓練」についてです。
能登半島地震などの教訓から大規模地震や災害発生直後における初動対応の重要性、今後の備えを更に確かにするために地震災害対応訓練を実施します。このような訓練を積み重ねることにより、災害発生時に可能な限り被害を軽減するとともに、市民の防災意識の醸成、職員の災害対処能力の強化などを図って参ります。また、警察・消防・自衛隊などとの連携強化による防災力の向上にも引き続き取り組んで参ります。
次に「防災備蓄機能の強化」についてです。
大規模な災害が発生した場合に、乳幼児や高齢者、障がい者など様々な方が数多く避難されることが予測されるため、そのニーズに対応できるよう備蓄品を適正に管理し、計画的な購入を行って参ります。特に能登半島地震においても課題であったトイレ不足について、今回、簡易トイレの購入を計画しているところです。また、指定避難所、福祉避難所などへの備蓄品の整備も進め、更なる分散化に取り組んで参ります。
次に「一体的情報発信の検討」についてです。
現在も市からの情報を様々な手段で発信していますが、市政情報、観光情報、防災情報に加え災害時における情報の発信も含めた一体的な情報発信について検討を行って参ります。
次に「木造戸建て住宅性能向上改修等促進事業」についてです。
能登半島地震なども教訓とし、木造戸建て住宅の耐震化等を更に促進するために、本市に存在する木造戸建て住宅に対して耐震化等に関する補助金を増額し、地震に強く安心安全なまちづくりを目指して参ります。
次に「ブロック塀等撤去促進事業」についてです。
地震時におけるブロック塀等の倒壊による被害防止や通学路、避難路等の安全性を確保するために、道路に面する特に危険なブロック塀等の撤去工事に関する補助金を増額し、災害から命を守る対策を進めて参ります。
以上の事業を「地震災害をはじめとした災害対応パッケージ」として連動して取り組んで参ります。
その他の事業について説明して参ります。まず「ため池の防災対策推進」についてです。
ため池の堤体の劣化状況や耐震等に関する調査において、劣化や耐震性能の不足が確認されたため池の護岸及び堤体の改修工事等を計画的に実施して参ります。また、堤防が決壊した場合を想定したハザードマップを市民に広く周知し、災害発生時の迅速な行動へとつなげ防災減災意識の向上に努めて参ります。
次に「消防団活動支援事業」についてです。
地域に密着し、市民の安心安全を守るという重要な役割を担う消防団員について、団員数が減少している状況を踏まえ、消防団員の年額報酬及び費用弁償を改定し、地域防災力向上のため、消防団の維持・確保に努めるとともに危機管理の強化を図って参ります。
次に「通学路交通安全対策の推進」についてです。
関係機関合同による通学路の点検結果に基づき、自転車利用が多い通学路の対策工事などを行い、登下校時における児童生徒の安全の確保に取り組んで参ります。
次に「地域見守りカメラの増設」についてです。
本市では、犯罪等の予防を目的として地域見守りカメラを設置していますが、通学路危険箇所要望等を踏まえて、新たな箇所に地域見守りカメラを設置し、安心安全なまちづくりを推進して参ります。
次に「飲酒運転撲滅運動の推進」についてです。
令和6年度も市民を対象とした飲酒運転撲滅講演会などを継続して、社会全体で飲酒運転をさせない環境づくりの必要性を改めて確認し、飲酒運転は絶対しない・させない・許さない・見逃さない環境づくりを推進して参ります。
次に「点字ブロックの整備促進」についてです。
令和発祥の地大宰府政庁跡の玄関口となる観世音寺土地区画整理事業61号線(通称、朱雀大通り)の点字ブロック設置工事を実施します。その後についても計画的に整備を進め、あらゆる人が気兼ねなく安心して訪れることができるまちづくりに取り組んで参ります。
次は2項目め「子どもまんなかの施策展開」についてです。
子どもを令和の都だざいふの宝としてまんなかに位置付け、いきることをサポートし、すくすくのびのびと成長できるよう、更なる居場所や出番づくりなど子ども施策を推進していくことを目指し、18億円余りを計上しております。
その中でもまず「給食パッケージ」を設定し、4億円余りを計上しております。悲願の中学校完全給食を1月10日からスタートし、子どもたちの育ちへの切れ目ないサポートは整って来ましたが、令和の都だざいふの宝としてまんなかに位置付けるには更なる後押しが必要と考えます。
具体的には、まず、「小・中学校給食費の助成」についてです。
子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的に、1億円余りを計上して小・中学校給食費の3割を助成します。これにより、物価高などの影響が続くなかでも令和の都だざいふの宝である子どもたちが安心して栄養バランスのとれた食事を摂ることができるよう支援して参ります。また併せて、国県による給食無償化への呼び水にもして参ります。
次に「中学校給食の実施」についてです。
本市の悲願であった全員喫食による中学校完全給食について、令和6年1月から開始いたしました。引き続き小学校と連携しながら、小・中学校9年間を通じた食育を推進するとともに、物資の安定供給や衛生管理の徹底など、各学校の運用を軌道に乗せ、安心安全な給食の提供ができるよう継続して取り組んで参ります。
次に「小学校給食の実施」についてです。
中学校完全給食の実施に合わせ、中学校と連携しながら小・中学校を通じた食育を推進するとともに、引き続きチャレンジクッキングや、友好都市・姉妹都市記念給食など、児童の食への興味関心を高める活動の充実を図って参ります。
以上の事業を「給食パッケージ」として連動して取り組んで参ります。
2つ目の「ひきこもり・不登校等対策パッケージ」にも1億円余りを計上しております。長いコロナ禍の影響もあり子どもたちの不登校やひきこもりの高齢化などが更に社会問題化するなか、全世代的にいきることをサポートし、居場所と出番をつくることがますます重要だと考えます。
具体的にはまず、「地域の居場所づくり推進事業」についてです。
地域の居場所づくりの新たな取組として、子どもから高齢者、不登校児童、ひきこもり者、障がい者など地域の方が気軽に安心して参加できるコミュニティ食堂を開催する団体に助成を行う制度を開始し、みんなが集える居場所づくりに取り組んで参ります。さらに、コミュニティ食堂の開催に併せて市が実施する事業の一部を地域の身近な地区公民館等で実施し、様々な関係機関や団体と連携することで、全ての人の居場所や地域課題の早期解決につなげ、地域コミュニティの活性化を推進して参ります。
次に「不登校児童生徒支援の推進」についてです。
小・中学校の不登校児童生徒はコロナ禍以降、全国的に急激に増加しており、本市ならではの不登校児童生徒の支援に更に力を入れて取り組んで参ります。不登校児童生徒の支援を行うサポートティーチャー(ST)を増員し、全ての小・中学校にサポートルームを設置します。また、スクールソーシャルワーカー(SSW)を増員し、全ての中学校ブロックに配置します。不登校児童生徒の対応をはじめ在宅学習やフリースクール利用者の対応、子どもたちが安心して過ごせる居場所の確保に取り組んで参ります。
次に「子どもの居場所づくり事業」についてです。
子育て支援の取組として令和5年度に開設いたしました家庭や学校に居場所がない子どもの第3の居場所を継続して運営し、不登校の子どもや、家庭や学校生活に困難を抱える学齢期以降の子どもたちの安心安全な居場所づくりを行うとともに、進路等の相談支援、食事の提供等を行い、適切に関係機関につなげていくなど、地域全体で子どもを育てる社会を目指して参ります。
次に「孤独・孤立対策の推進」についてです。
ひきこもりの長期化・高年齢化、親の高齢化などが進む中、孤独・孤立対策を進めるため、地域の支援者などを対象としたひきこもりへの理解促進の研修会を実施するとともに、関係機関と連携して相談会を実施して参ります。また、関係機関に対しアンケートを実施することで、家庭内にいるひきこもり者の実態把握などに努めて参ります。
次に「自殺対策事業」についてです。
まず自殺対策を「いきるサポート」と位置付け、健康や生活、家庭などの様々な悩みを抱え、こころが落ち込んでいる方などに対し、精神科医と連携して「こころの健康」に関する相談窓口を設置することで、一人ひとりに寄り添った相談体制の充実を図って参ります。また、自殺の危険を示すサインに気付き、声かけや見守りなどの対応を行い必要な支援につなぐゲートキーパーを養成する研修を行い、支援体制の充実を図って参ります。
次に「全世代交流フリースペースの活用推進」についてです。
令和4年12月にいきいき情報センター1階にオープンした全世代交流フリースペースは、既に子ども学生の自習スペースとして大いに利用されており、高齢者向けeスポーツ体験会では子ども学生と高齢者の世代間の交流が実現するなど、全世代の皆様に親しまれる場所として好評をいただいています。引き続き全世代の交流ができる場所として更に定着するようフリースペースの有効活用を図って参ります。
以上の事業を「ひきこもり・不登校等対策パッケージ」として連動して取り組んで参ります。
3つ目の「世界に羽ばたく人材育成パッケージ」には4千万円余りを計上しております。待望の大谷グローブが小学校に届くなど子どもたちの夢は大きく広がります。令和の都だざいふから世界に羽ばたく人材を更に育成するべく、予算額やメニューを格段に充実させました。今後も令和の都だざいふ応援大使のお力もお借りしながら、サポートを続けます。
具体的にはまず、「学生まちづくり課題解決プロジェクト」についてです。
小学校から大学までの児童生徒・学生から本市の課題解決につながる提案を受け、子ども学生未来会議の場などで議論し、まちづくりに実際に反映する新たなプロジェクトを立ち上げます。この取組を通じ、子どもや学生のまちづくりへの関心を高め、令和の都だざいふから世界に羽ばたく人材の育成を図って参ります。
次に「九州国立博物館ツアーズ」についてです。
市立小・中学校の児童生徒に本市が誇る九州国立博物館の特別展を観覧する機会を新たに設けます。世界中の様々な文化に触れながら学習することで、グローバルな視点をもった子どもを育て、世界に羽ばたく人材育成を推進するとともに、九州国立博物館とのさらなる連携を図って参ります。
次に「学力向上への取組推進」についてです。
子どもの学力育成を目指して、小学校から中学校につながる本市独自の学習の取組として「マスターノートだざいふ」を作成し、日常的に児童生徒が復習に活用することで、学習したことの定着を図り、基礎的学力の向上に取り組んで参ります。
次に「スケートボードパーク等の整備」についてです。
2021年に開催された東京オリンピックで注目を集めているスケートボードですが、国内では施設の数が少ない状況にあります。今後さらに人気が高まり、施設の需要が予測されることから、松川体育館一帯を修繕し、スケートボードパーク等を設置して有効活用し、安心安全に楽しむことができる環境を整備することで、オリンピックを目指す若者や世界に羽ばたく人材の育成を推進して参ります。
次に「子ども学生美術展・世界に羽ばたく人材育成表彰」についてです。
市制施行40周年記念事業の一環としてスタートしたこの取組を、令和の都だざいふらしい次代を担う若い才能を顕彰し育成する取組として令和6年度も推し進め、若い皆さんの目標とされる美術展及び表彰に進化させて参ります。
その他にも、全国大会に出場する子ども・学生等への支援や高大連携の強化、友好都市・姉妹都市学校との連携予算なども活用して参ります。
以上の事業を「世界に羽ばたく人材育成パッケージ」として連動して取り組んで参ります。
4つ目の「安心の産前・産後ケアパッケージ」には約1億円を計上しております。子どもたちを令和の都だざいふの宝としてまんなかに位置付けるにおいて、産前・産後のケアは非常に重要なテーマです。こうした考えのもと新規事業や従来事業の拡充を思い切って行います。
具体的にはまず、「産婦健康診査事業」についてです。
産後うつ病の予防や新生児への虐待予防等を図るため、出産日から8週に満たない産婦に対し、自己負担健診料に対する助成を行う制度を令和6年度から開始し、安心して子育てすることができる環境の充実に取り組んで参ります。
次に「産後ケア施設整備費補助事業」についてです。
妊産婦が市内で安心して子育てを行うことができる環境を整えるため、市内に新たに産後ケア施設を開設する事業者に対し、設備に必要な費用の一部を助成する制度を令和6年度から開始し、全ての妊産婦が安心して健やかな育児ができる環境整備を図って参ります。
次に「産後ケア事業の拡充」についてです。
現在実施している「産後ケア事業」について、助産師が利用者宅を訪問し産後ケアを行う居宅訪問(アウトリーチ)型と利用者が助産院に赴き、産後ケアを受ける通所(デイサービス)型に加え、利用者が産婦人科等に宿泊して産後ケアを受ける短期入所(ショートステイ)型を令和6年度から開始し、より充実した内容へ拡充を行います。
次に「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施」についてです。
妊娠期から出産・子育て期にわたる切れ目のない支援として、様々なニーズに即して必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実及び出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図るための経済的支援を一体的に実施して参ります。さらに、子育て支援アプリの更なる機能充実を図り、利便性向上に取り組んで参ります。
次に「こども家庭センターの充実」についてです。
児童福祉に関する「子ども家庭総合支援拠点」の機能と、母子保健に関する「子育て世代包括支援センター」の機能を統合した「こども家庭センター」を令和6年2月に開設いたしました。令和6年度は、現在実施している「子育て短期支援事業」について、児童の保護者が疾病などにより児童を養育することが一時的に困難になった場合に、児童養護施設等に預けることができる児童の対象年齢を拡充するなど、事業の充実を図って参ります。
その他にも、初回産科受診料の支援や多胎妊娠妊婦の健康診査支援、子育て世帯訪問支援、新生児聴覚検査予算などを活用して参ります。
以上の事業を「安心の産前・産後ケアパッケージ」として連動して取り組んで参ります。
その他の事業について説明して参ります。まず、「子どもの権利条例の策定」についてです。
本市の子どもたちが安心して健やかに育つことができるように、児童の権利に関する条約に規定する子どもの権利を保障する観点から、子どもの権利条例の制定を進めて参ります。
次に「子ども医療費助成の拡充」についてです。
子育てにかかる経済的負担軽減策のひとつとして、子ども医療費の助成をあらゆる世代で充実させるとともに、新たに高校生世代まで拡充し、子どもの保健の向上と福祉の増進を図って参ります。
次に「学童保育所増設事業」についてです。
児童数の増加等により、学童保育所の教室が不足していることから、太宰府東小学校と太宰府西小学校に増設整備し、児童の健全育成及び保護者が安心して子育てと仕事の両立を図ることができる環境を整えて参ります。
次に「教育DX推進事業」についてです。
児童生徒の学力や日常的な心身の健康状態など、多様な情報のデータ化・分析を行うために校務支援システムを導入し、教育DXの取組を推進して参ります。この取組により、統合的なデータを参照することで児童生徒一人ひとりに応じたきめ細やかな指導の充実、学校経営判断の迅速化や適正化、更には教職員の働き方改革につなげて参ります。
次に「太宰府小学校長寿命化改良事業」についてです。
太宰府小学校の教室棟と屋内運動場について、建物の耐久性を高めるとともに、多様な学習形態への対応が可能となるよう環境性能の向上や施設の改修を進めて参ります。また、屋内運動場につきましては、避難所にも指定されていることから、利用者が安心安全に利用することができるよう空調設備を整備して参ります。
次に「学校施設バリアフリー化等施設整備事業」についてです。
全ての児童生徒が安心安全な学校生活を送ることができるように、太宰府東小学校にエレベーターの設置を進め、学習環境の整備を行います。また、屋内運動場についても、誰もが安心安全で快適に利用することができるようトイレの洋式化を行うとともに多目的トイレの整備も実施して参ります。
次に「放課後子ども教室の拡充」についてです。
放課後の子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを行い、多様な体験活動ができるように、3つの小学校において地域コーディネーターを中心に地域人材や市内大学生の協力のもと実施しています。令和6年度は実施校を拡充するとともに、地域住民や大学生等からなる地域活動サポーターの積極的な参画を促して参ります。
次に「文化芸術振興事業」についてです。
様々な人が文化芸術に関心を持つきっかけをつくり身近で親しみやすい文化芸術に触れる機会を提供するため、民間等の支援を受けてプロの演奏家によるコンサートをプラム・カルコア太宰府で実施いたします。また、応援大使を活用した企画も計画し、令和の都だざいふの魅力を広く発信して参ります。
その他にも、本年度達成した待機児童ゼロを引き続き実現するための取組や保育所へのICT導入推進、届出保育施設への運営支援、水城小学校管理棟他改築工事、太宰府西小学校管理教室棟長寿命化、学業院中学校整備計画の策定、史跡水辺公園屋外プール改修などの事業を着実に進めて参ります。
次は3項目め「市民と交流人口・関係人口の相互発展」についてです。
住まう人も訪れる人もともに慶び合えるまちとして、交流人口・関係人口からの経済税収効果を飛躍的に高め、市民メリットを体感できる仕組みを創ることを目指し、約13億5千万円を計上しております。
その中でもまず「交流人口・関係人口による経済税収効果パッケージ」を設定し、12億円余りを計上しております。本市のネームバリューを活かしシティープロモーションなどを積極的に行うことで、就任時4千万円であった寄附額が本年度18億円、45倍増に達しそうな勢いのふるさと納税はまさしく交流人口・関係人口による経済税収効果向上の象徴と言え、こうした果実を市民に積極的に還元して行くことが重要です。
具体的にはまず「令和改元5年記念」についてです。
新元号令和のご縁をいただいてから5年を迎えたことを記念し、「令和の都だざいふ」の魅力を改めて市民や本市を訪れる観光客の皆様にお伝えすることを目的に、「令和文化会議」の令和6年度版などの「令和改元5年記念事業」を行います。また、令和、万葉に関する研究・情報発信に取り組んでいくために「(仮称)令和万葉館」の設置についても、調査研究を行って参ります。
次に「観光回遊ルートの拡充」についてです。
外国人観光客のニーズが高い、日本の歴史や文化、自然、生活様式といった地域資源を生かし、地域のアクティブシニアをおもてなし人材とするインバウンド向け体験メニューを産官学連携により造成して参ります。
また、太宰府天満宮周辺の観光客を、大宰府政庁跡をはじめとする史跡文化財や観光施設に誘客する仕組みを構築し、多地点回遊による観光消費を促して参ります。さらに、宿泊やナイトタイムなど様々な時間帯に向けたコンテンツを発掘し、地域の事業者と連携した丸一日滞在向け観光メニューの造成を行って参ります。
次に「「ユニバーサルツーリズム」にかかるモニターツアーの実施」についてです。
年齢や性別、国籍、障がいの有無などに関係なく観光を楽しめる「ユニバーサルツーリズム」の理念を本市観光にも積極的に取り入れるため、観光地域における実地検証による課題の抽出及び本市のユニバーサルツアー実証実験を実施して参ります。
次に「ふるさと納税の推進」についてです。
令和6年度につきましても競争力のある返礼品の拡充、積極的な営業活動等により、寄附額20億円の大台を達成するとともに、より有効な市民への還元に取り組んで参ります。
次に「まほろば号改革」についてです。
まほろば号は、平成10年の運行開始以降、路線の拡大と運賃の値下げを行って参りましたが、昨今の物価や燃料費の高騰、乗務員不足等により経営環境は著しく厳しさを増していることから、ダイヤの改定を実施して参ります。一方、市民の移動手段を確保するという観点も踏まえつつ、交流人口・関係人口との相互発展を目指し、今後のまほろば号の持続可能な運行のため、路線や時期などによって負担を変更する料金体系の見直しを検討して参ります。
その他にも、史跡の先進的多用途活用や日本遺産の広域連携推進、先端技術を用いた文化財の活用などの予算を活用して参ります。
以上の事業を「交流人口・関係人口による経済税収効果パッケージ」として連動して取り組んで参ります。
次なる「オーバーツーリズム対策パッケージ」には約8千6百万円を計上しております。本市を代表する積年の課題として観光公害、いわゆるオーバーツーリズムの問題があげられます。他市に先駆けて開始した歴史と文化の環境税導入を始めこれまでも積極的に取り組んで来ましたが、国県と更なる連携を図るべく観光庁のオーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業への申請も進めております。
具体的にはまず「交通情報案内システムの充実」についてです。
本市の課題である渋滞の緩和を図るために導入した交通情報案内システムについて、令和5年度から実証を行っている駐車場満空情報自動判定を実装して機能を充実させ、観光客の駐車場利用の分散化と公共交通の利用を促します。また、市民が交通情報案内システムを利用することで渋滞の回避につながるよう利用促進に取り組んで参ります。
次に「マルチモーダルサービス導入実証事業」についてです。
複数の交通手段を最適に組み合わせ、検索・予約・決済等を一括で行うサービスであるマース(MaaS)を導入することで、通院・買い物や観光等の目的地への移動ニーズに対応し、利便性の高い生活や観光の実現、地域活性化に取り組むとともに、住まう人と訪れる人の公共交通の利用を促進することで渋滞の緩和を図って参ります。
次に「オーバーツーリズム対策事業」についてです。
本市における観光需要は急速に回復し賑わいを取り戻している一方、観光客が集中することにより様々な弊害がおきる、いわゆるオーバーツーリズムが課題となっています。観光客の受け入れと市民生活の質の確保を両立しつつ、持続可能な住まう人も訪れる人もともに慶び合えるまちづくりを実現するため、年末年始等の観光客が多数来訪する時期に臨時駐車場、臨時トイレの設置や交通誘導員の配置、外国人観光客が多数来訪した際の対応などのオーバーツーリズム対策を歴史と文化の環境税を活用して実施して参ります。
次に「市民も観光客もメリットを体感できる美化活動の推進」についてです。
本市を訪れる観光客の大幅な増加は本市経済にメリットをもたらす一方、市民生活や自然環境に悪影響を与える側面もあります。観光客だけでなく市民も利用する史跡地の草刈、トイレ清掃、幹線道路周辺の清掃、樹木管理などの環境整備を、歴史と文化の環境税を活用した市民と観光客双方がメリットを体感できる取組として実施して参ります。
次に「地域公共交通計画の策定」についてです。
持続可能な都市構造への転換と、利便性の高い公共交通で結ばれたコンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりを進めるため、地域公共交通計画を策定し、公共交通の利便性向上に向けた路線や運賃の最適化について検討を行って参ります。また、関係事業者等との連携を進め、地域に必要な移動手段の確保に新しい公共の視点も交えて取り組んで参ります。
次に「総合交通計画の改訂」についてです。
アフターコロナによる移動需要が回復傾向にある一方、人々の行動変容や輸送に関わる運転士の労働環境など、交通分野を取り巻く環境の変化が見込まれています。こうした社会情勢の動向を踏まえながら渋滞の緩和や安全な交通環境の実現に向け、総合交通計画の改訂と自転車活用推進計画の策定について引き続き検討を重ねて参ります。
また、公共施設の使用料やまほろば号の運賃など利用者からの料金と公費負担の適正化の観点を踏まえ、市民と交流人口・関係人口の料金設定に差を設け、市民メリットを体感できる仕組みの検討を進めて参ります。
以上の事業を「オーバーツーリズム対策パッケージ」として連動して取り組んで参ります。
その他の事業について説明して参ります。まず、「令和発祥の都太宰府「梅」プロジェクトの推進」についてです。
「梅」プロジェクトにつきましては、太宰府梅園構想のもと、史跡地を中心に更なる梅の植栽を行うとともに、産業規模の拡大に向けた梅の安定供給の手法について検討を進めて参ります。また、令和の都だざいふの中核事業として「真の梅のまち」を目指し、市内外の事業者等とも連携した梅に関するイベントを実施するほか、情報発信にも注力し、市一丸となったプロモーションに取り組んで参ります。さらに、「梅」プロジェクトの発展と「梅のまち」のブランドイメージの確立のために、市民を含む民間による自発的な取り組みの推進について検討を進めて参ります。
次に「太宰府館の活用方法にかかる民間活力導入手法検討事業」についてです。
平成16年10月の開館以来、地域活性化複合施設として地域住民と観光客に親しまれ、利用されてきた太宰府館について、官民連携による民間活力の導入も含めた有効な活用手法の検討を行って参ります。
次に「西鉄沿線活性化協議会共同プロモーション」についてです。
西日本鉄道株式会社と沿線自治体とで構成する協議会において、地域資源を活用した観光コンテンツの造成や共同PRを通じた観光交流人口の増加や地域活性化を目指して参ります。また、国内外への観光プロモーションを行うためにFMラジオを使用した情報発信のほか、訪日外国人向けウェブマガジン等を使った情報発信を継続的に行って参ります。
次に「太宰府館・大宰府展示館・水城館・文化ふれあい館の連携統合」についてです。
4館共通の周遊マップの作成や4館とその周辺観光地を巡るスタンプラリーの実施など4館の認知度を高めるとともに、一層の回遊性向上を図る取組を実施して参ります。また、現在の4館の位置づけ・機能整理を行うとともに、4館が周遊観光の拠点としてより有機的に機能する手法について、地域・民間事業者と連携し検討を進めて参ります。
次に「中心市街地の活性化」についてです。
今後迎える人口減少に備え、持続可能な都市構造への転換を図り「コンパクトなまちづくり」を実現するため、立地適正化計画の策定を進め、鉄道駅周辺の中心市街地の活性化等に向けた具体的な取組の検討を行って参ります。
次に「国分坂本地区道路改良」についてです。
新たな宅地開発による人口増の影響が見込まれる坂本2丁目交差点及び国分寺交差点における交差点改良設計を実施し、混雑緩和に向けた方策の検討を進めて参ります。
その他にも、筑紫野古賀線や観世音寺二日市線の着実な整備、歴史的街なみの保全や指定文化財保存整備の推進予算などの予算を活用して参ります。
次は4項目め「新しい公共をテーマとした仕組みづくり」についてです。
自治会、関係機関、各分野の団体などと防災や福祉、教育など様々なニーズや課題を持ち寄り、対話を重ね、役割を明確にし、課題解決を図る仕組みづくりを目指し、1億5千万円余りを計上しております。
そして、この項目では「新しい公共の仕組みづくりパッケージ」を設定し、7千万円余りを計上しております。
具体的にはまず、「(仮称)新しい公共座談会の実施」についてです。
今日抱えている社会課題は多様化複雑化し、従来のように自治体のみで機動的に対応することが困難になってきています。そのため、自治会、教育や子育て、街づくり、防犯や防災、医療や福祉、各種団体等の多様な主体が参画し、対等な立場で対話と協働を進めることで、お互いの役割を明確にし、連携しながらそれぞれの役割を果たして社会課題の解決を図って参ります。
次に「地震災害対応訓練」についてです。
地震災害対応訓練などを通し、職員や警察・消防・自衛隊などの関係機関、市民との連携や役割分担などを明確化し、防災意識の醸成や災害対処能力の強化などを図って参ります。
次に「地域の居場所づくり推進事業」についてです。
地域の居場所づくり推進事業などを地区公民館等で実施することで、子どもから高齢者、不登校児童、ひきこもり者、障がい者などの居場所づくりを行うとともに、様々な関係機関や団体と連携することで、地域課題の早期解決や地域コミュニティの活性化などを推進して参ります。
次に「放課後子ども教室の拡充」についてです。
放課後子ども教室などの実施により、新たな子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを行うとともに、地域コーディネーターを中心に地域人材や市内大学生などの協力のもと多様な体験活動ができるように実施することで、地域活動サポーターの積極的な地域活動への参画を促して参ります。
次に「地域コミュニティの活性化」についてです。
少子高齢化や地域のつながりが希薄化する一方、災害の頻発など地域の助け合いの必要性は以前にも増して高まっています。新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことに伴い、地域活動の再開が進み地域コミュニティ活動の再活性化がみられ、子どもや高齢者、行政、市民活動団体など多様な主体が交流、連携できるよう、地域のリーダー的人材の育成や区自治会への支援など地域コミュニティの活性化に向けて積極的に支援して参ります。
また、公園や公民館、公共施設に求められる役割や意義について様々な観点から再整理を行い、多面的利活用や地区公民館施設整備補助のあり方などについて検討を行って参ります。
以上の事業を「新しい公共の仕組みづくりパッケージ」として連動して取り組んで参ります。
その他の事業について説明して参ります。まず、「地球温暖化対策の推進」についてです。
ゼロカーボンシティの実現に向け、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス、戸建住宅用再生可能エネルギー発電等設備、次世代自動車の導入を促進するため、補助の拡充を行って参ります。
次に「ごみ減量の推進」についてです。
令和5年度から「一人ひとりごみ減量プロジェクト」と銘打ち、令和6年度までに1人1日当たりもえるごみの排出量600グラム達成に取り組んでいます。令和6年度は、この取組を更に推進させるため、ダンボールコンポストの市民モニター制度を創設し、市民モニターから寄せられた感想や意見を市民に還元することで、ダンボールコンポストの更なる普及促進を行い、ごみの減量に取り組んで参ります。
次に「子宮頸がん・乳がん個別検診事業」についてです。
現在実施している集団検診に加え、個別医療機関で受診することができる個別検診を令和6年度から実施して参ります。女性のライフスタイルが多様化する中で、選択肢の幅を広げ多くの人が受診しやすい検診を実施することで、がんを早期発見し、がんによる死亡率の減少を目指して参ります。
次は5項目め「歳出入一体改革の推進」についてです。
多様化し拡大する市民ニーズに応えつつ持続可能な行財政運営を堅持するため、複数の事業を通して組織横断的に取り組むことで、歳出入一体改革を図ることを目指し、13億円余りを計上しております。
この項目では、「歳出入一体改革パッケージ」を設定し、12億円余りを計上しております。
具体的にはまず、「民間プール等を活用した水泳授業委託」についてです。
平成31年3月議会で初めて提案し、実践してきた民間プール等を活用した水泳授業については、本市がいち早く取り入れた取組で、授業環境の飛躍的向上を図ることができるとともに、経済税収効果の向上や改修費用の抑制など複数のメリットがある取組です。令和6年度は、更に実施校を増やし効率的で効果的な授業を実施して参ります。
次に「中学校給食の実施」についてです。
民間事業者による市内新調理場誘致が実現したことで、食べ盛りの中学生に等しく栄養価を確保するとともに、安心安全の担保、経済税収効果の向上や維持保存費用の抑制など複数のメリットがある取組です。
次に「太宰府館の活用方法にかかる民間活力導入手法検討事業」についてです。
平成16年10月の開館以来、地域活性化複合施設として地域住民と観光客に親しまれ、利用されてきた太宰府館について、官民連携による民間活力の導入も含めた有効な活用手法の検討を行って参ります。
次に「ふるさと納税の推進」についてです。
本市の自主財源の15%以上を占める見込みまで上昇してきた寄附額はもちろん、新たな返礼品の開発や取引などによる経済税収効果の向上など複数のメリットがある取組です。
次に「令和発祥の都太宰府「梅」プロジェクトの推進」についてです。
新たな地場みやげ産業として経済税収効果の向上を図ることができるとともに、元号令和の発祥となった旅人の梅の木の植栽や実を使った新製品発表などによるシティープロモーションの強化など複数のメリットがある取組です。
その他にも、市内照明(街路灯、防犯灯、公園灯)一斉LED化により、リース方式を活用した市内照明の一斉LED化を進めて参ります。令和6年度に工事に着手し、令和7年度からリース事業を開始することにより電気料金約50%削減、CO2排出量約70%削減の効果が見込まれ、電気料金削減額を事業費の支払いに充てることで一般財源の負担を増やさずに一斉LED化することが可能となります。また、明るく故障が少ないLEDに変更することで、安心安全のまちづくりの更なる充実を図って参ります。
以上の事業を「歳出入一体改革パッケージ」として連動して取り組んで参ります。
その他の事業について説明して参ります。まず、「企業誘致推進体制の強化」についてです。
本市の企業誘致戦略に基づき、地方への進出を目指す企業との商談を行い、民間のコンサルティング事業者のノウハウを生かした伴走支援を行うことで、確実な企業誘致につなげ、経済税収効果の向上を図って参ります。
次に「起業創業支援・地場産業育成の推進」についてです。
商工会と連携して地場産業育成を進めるとともに、市内において地域課題の解決を図る創業者に対して、スタートアップ時の家賃補助制度を創設し、起業創業支援に取り組み、経済税収効果の向上を図って参ります。
次に「戦略的まちづくりの推進」についてです。
まちづくりビジョン会議からの専門的な知見や地域に即した意見を参考としながら市政運営を行い、令和6年度に期限を迎えるまちづくりビジョン改定について、国のデジタル田園都市国家構想総合戦略等も勘案しながら議論を進め、さらなる戦略的まちづくりに努めて参ります。また、各種施策や事業についての市民の認知度、意向等をより的確に把握するための市民意識調査を行い、まちづくりの指標として各種施策の展開に反映させて参ります。
次に「DXの推進」についてです。
高い専門的知識と経験を持つ外部のデジタル人材を活用し、市民の利便性向上を念頭に「人にやさしいデジタル化」を目指した、本市にとって真に必要なデジタル技術導入についての検討を進め、より効率的な市政運営に努めて参ります。
次に「(仮称)すぐやる班」についてです。
現在、市民等から相談・情報提供を受けた場合に、市で対応可能な作業については、まちぐるみ整備班等で対応していますが、このまちぐるみ整備班を含めて(仮称)すぐやる班に再編し、頻発する鳥獣被害等の市民ニーズに、より迅速かつ的確に対応できる体制を強化して参ります。
以上、二期目の公約に基づき、市民本位の捉え方や本市積年のもしくは社会共通の課題の解決を意識した「令和の都だざいふ課題解決予算」について、重点項目を中心にご説明して参りました。
時間の限りもあり、あくまでも課題解決事項に特化して説明して参りましたが、予算説明資料の世代・カテゴリ別予算額で分類しておりますように、あらゆる世代や立場の方々に満遍なく行き渡ることも意識した予算であります。
また、水城小学校の建て替えなどがひと段落したことにより教育費という費目単位においては減少するかたちとなっておりますが、その他の費目については全ての予算が前年と比して増加となる積極予算案とする事が出来ました。
何よりも予算規模が11億円余、3.8%の増額となる過去最大300億円超の大台となったことで、就任後初めて現場の予算要求をほぼ通すことが可能となり、市民ニーズに応えると共に職員意欲の向上にも繋がると期待しております。
結びに改めて申し上げますが、1月28日で2期目就任折り返しを迎えました。この間もコロナ対策や市制40周年記念事業、本市悲願の中学校完全給食などの実行に向け、私の持ちうる力は出し尽くして来たと自負しております。
市税やふるさと納税も着実に増加を重ね、併せて100億円の大台を超えるところまで拡大して来ました。史跡地や宗教法人、学校法人の多さなどから歳入構造に困難を抱える本市の本質的課題も一定の解決を見せて来ました。
直近の市民意識調査でも市政への信頼度は74%を超え、住みやすさや職員満足度も80%台で推移し、日経BP社の住みよい街2023でも念願の九州・沖縄1位を獲得するなど各種施策の効果が着実に評価されてきております。
これも全て市議会の皆様、市民の皆様、職員諸氏始め関係各位のご理解ご協力の賜物と感謝申し上げます。
私の持ちうる力にも人生にも自ずと限りはありますが、本議会で本市積年のもしくは社会共通の課題の解決に向けた未来への種まきを心掛けましたので、皆様の変わらぬご理解ご協力をお願い申し上げ、私の施政方針と致します。
ご清聴ありがとうございました。
令和6年2月27日
太宰府市長 楠田 大蔵