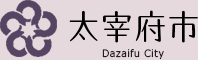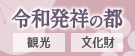本文
施政方針(令和5年第1回(3月)定例会・令和5年2月28日)
本日ここに、令和5年第1回定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては大変ご多用の中をご参集賜り、厚く御礼を申し上げます。
この定例会は、令和5年度予算案をはじめ、主要施策並びに条例案などをご審議いただくひと際重要な議会ととらえております。議案提案に先立ちまして、まずは令和5年度の市政運営に臨む私の所信を披歴し、議員各位や市民の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げるものであります。
先月1月28日で太宰府市長に就任してから丸5年の節目を迎えました。まず冒頭、これまでの間ご理解ご協力を頂きました全ての皆様に心より感謝申し上げます。未曽有の混乱からの脱却、元号令和発祥の地としての取組、予期せぬコロナ禍への対応などチャレンジングな事案が次から次へと押し寄せましたが、この間一貫して世の為人の為、市の為市民の為に私の持ちうる力は出し尽くして来たという事だけは胸を張って言えます。
お陰様で史跡地の梅をグルメやスイーツに仕立てる令和発祥の都太宰府梅プロジェクトも起爆剤にふるさと納税が就任後30倍増となる12億円を大きく突破するなど積年の課題であった歳入増も年々着実に実現し、直近の市民意識調査では市政への信頼度も7割を超え、職員の対応満足度や効率的な市政運営なども5年連続上昇するなど上昇気流に乗って参りました。今後もこの原点を胸に刻み、頑張って参ります。
さて、「令和の都さらに羽ばたく太宰府~課題解決先進都市を目指して~」を掲げた二期目の実質初年度ともなります令和4年度を振り返りますと、スタートダッシュを図るべく、コロナ禍を力強く乗り越え、令和の都として太宰府をさらに羽ばたかせるための積極的投資を行う「市制40周年未来チャレンジ予算」と銘打った、総額290億円あまり、過去最大規模の予算を組み、着実な執行に努めて参りました。
また、ビジョン会議にて「行財政改革」「新しい公共」「ニュー太宰府構想」「世界に羽ばたく人材育成」「企業誘致、起業創業支援」の5つのグループをつくり、ベスト&ブライテストたる外部委員と組織横断的にチーム編成した我々の叡智を結集して二期目公約の実現と更なる具体化を図って参りました。
また、6月には清水圭輔前副市長から原口信行現副市長に、12月には樋田京子前教育長から井上和信現教育長にそれぞれ交代し、二期目を新たにスタートした私も含め心機一転再スタートしました。前任者の意志もしっかり受け継ぎ、改めて三役一丸となって市政運営にあたっておるところです。
悲願でありました全員喫食による中学校完全給食は、一期目終盤に基金を積み立てたうえで二期目公約に掲げ、就任直後から集中的かつスピーディーに検討や取組を重ねてまいりました。その結果、市内新工場が建設され出来立てで美味しく、安全で、かつ経済税収効果も見込めるかたちで昨年11月晴れて契約締結に至り、来年1月の開始に向け引き続き全力をあげているところです。
市制施行から節目の40周年を迎えた本年度、年間を通じ市民の皆様とともに様々な取組を行って来ましたが、初春令月にあたり建国記念の日でもある今月佳き日に、三年越しの念願でありました中西進先生も直接にお迎えし、「令和の都さらにはばたくだざいふ 市制施行40周年記念式典」を行いました。
また、これを機に当時の我が国の最先端の国際シンポジウムであったとされる梅花の宴を1300年の時空を超え現代に甦らせる「令和文化会議」、古の「大宰府」も現在の「太宰府」もあわせてプロモーションいただく「令和の都だざいふ応援大使」の委嘱、次代を担う子どもたちの更なる飛躍を期す「世界に羽ばたく人材育成表彰」や「子ども学生美術展」という新たな取組もスタートしました。
この間の皆様のご理解ご協力に改めて感謝申し上げますとともに、本市の来し方と行く末について改めて思いを致し、今後の50周年100周年へのバトンを確かにつないで参ります。
そうした節目を経た令和5年度は、次なる10年に向け令和の都だざいふをさらに羽ばたかせ、長年の課題であった中学校完全給食の確実な実施、高齢者人口の増加に伴うサポートの充実、老朽化した公共施設の再編など市民ニーズに積極的に応えていくための卯年らしい飛躍の年と位置付けます。
そのためにも、成長戦略三本の矢としてふるさと納税の更なる拡大、文化財保存活用地域計画に基づく更なる史跡地の先進的多用途活用、そして子育て世代の流入拡大策や企業誘致の更なる促進を標榜し、各種基金、市債の活用も含め、より前向きに、より具体的に事業を実施して参ります。
同時に、受益と負担のバランスを常に念頭に置き、既存事業や補助金、使用料等についても前例に捉われない徹底した見直しと効率化による歳出削減に努めるとともに、重要度や緊急性、効率性等に応じ優先順位を明確に付け、限られた財源を新たなニーズや重点施策に振り向けて参ります。
そうした経営方針のもと、令和5年度の当初予算案は、私の二期目公約「令和の都さらに羽ばたく太宰府~課題解決先進都市を目指して~」に基づき、まちづくりビジョンに沿った重点項目を設定し、様々な新機軸も盛りこんだ「市民ニーズに応える令和の都だざいふ予算」と銘打ち、予算規模としては総額290億円弱、コロナワクチン関連予算を除き過去最大規模といたしております。
ちなみに平仮名「だざいふ」表記は、いにしえの「大宰府」もいまの「太宰府」もあわせてまるごと「だざいふ」の魅力をアピールして行こうとの試みです。
それでは、令和5年度予算案について、重点項目を中心にまちづくりビジョンの体系に基づきご説明申し上げます。
はじめに第1の戦略「太宰府の底力総発揮構想(成長戦略)」について、令和5年度の重点項目を説明して参ります。
まず、「令和発祥の都太宰府梅プロジェクトの更なる促進」についてご説明いたします。
「令和発祥の都太宰府「梅」プロジェクトの推進」につきましては、産官学連携で様々なグルメやスイーツなどが生まれ、ふるさと納税の飛躍的向上にも寄与する令和発祥の都太宰府梅プロジェクトをさらに推進すべく、太宰府梅園構想のもと、梅の生産量を拡大するため、史跡地内を中心に梅の植栽をさらに積極的に行い、遊休農地等の活用についても検討を進めます。
また、梅プロジェクトの将来あるべき姿について更なる具体化を図るため、民間事業者等の知見も活用し中期事業計画の策定に取り組むとともに、官学連携で行いました梅の成分分析結果を活用し、新製品開発や更なるブランド価値の向上を追求して参ります。
あわせて、市内農家が梅をはじめとする農産物を出荷する際の手数料の一部を補助することにより、特産品開発の原材料となる農産物の生産量及び出荷量の増加を図って参ります。
次に「鳥獣被害防止対策の推進」につきましては、有害鳥獣(イノシシ)による農作物被害への対策として、市内各所に箱ワナを設置し捕獲に努めておりますが、令和4年度から「有害鳥獣被害防止対策事業補助金」を創設し、農作物被害を防止するためのメッシュ柵等を購入された農家等に対し、費用の一部補助を開始したところです。こうした取組について、令和5年度も継続して実施することで農産物への被害抑制と生産の安定化に取り組んで参ります。
次に「企業誘致、起業創業支援の強化」についてご説明いたします。
「企業誘致推進体制の強化」につきましては、本市の経済税収効果を高めるための最重要課題である更なる企業誘致を達成するための新たな取組として、民間のコンサルティング企業のノウハウを活用した企業誘致戦略の策定及び具体的な施策展開へと取組を前進させて参ります。
次に「起業創業支援・地場産業育成の推進」についてです。
地場産業育成を推進し地域経済の活性化を図るため、商工会との更なる連携を進め、起業創業支援についても力を入れて参ります。
また、令和4年度から取り組んでおります「女性を中心とした創業支援の推進」についても引き続き注力し、近年増加傾向にある女性の創業を積極的に支援することで多様な業種、形態での起業の促進を図って参ります。
次に「太宰府ならではの観光文化財施策の更なる充実」についてご説明します。
まず「観光推進基本計画の改定」につきましては、観光推進基本計画策定委員会を立ち上げ、次期計画への改定を行って参ります。改定に当たっては、実施状況の評価、分析などを行った上で、新たに本市の観光において重要なコンテンツとなった「令和の都だざいふ」の要素や回遊性の向上、コロナ後の観光のあり方などを加えるなど、本市を取り巻く環境の変化に適切に対応した内容にして参ります。
次に「観光回遊ルートの整備」につきましては、現在観光客が集中している太宰府天満宮周辺から市内各所への回遊性向上を図るため、市内で活動するNPOや民間団体等との連携を進め、日本遺産古代日本の「西の都」をテーマにした新たな周遊モデルコースの開発やツアーの実施、食や体験といったコト消費など、体験型観光や滞在型観光の拡大に取り組みます。また、四王寺山、宝満山などの恵まれた自然景観を生かした観光コンテンツの開発についても取組を進めて参ります。
次に「位置情報を活用した観光回遊性の向上」についてです。
スマートフォンの位置情報から得られるデータを活用して、史跡地やイベントへの来訪者属性や回遊状況についての分析を進め、本市への誘客促進及び今後の回遊ルート開発に反映して参ります。
次に「観光客アンケート調査」につきましては、訪日外国人の太宰府観光の動向を把握するとともに、本市観光資源の認知度やニーズ等を整理するため、外国人観光客を対象とした調査を実施いたします。また、主に日本人のスマートフォンユーザーを対象とした観光アンケートを実施し、来られた経験のない方も含めたマーケティング分析を進めることで今後の観光施策に活用して参ります。
次に「観光文化財融合型ハンドブック作成」です。
本市の強みである観光施策と文化財施策を融合した令和の都だざいふならではのシティプロモーションや令和発祥の都太宰府梅プロジェクトをはじめとする地場みやげ産業などを掲載した「太宰府まるごと大図鑑(仮称)」を作成いたします。また、住まう人も訪れる人も共に慶び合える総合ネットワークの構築を図ります。このような取組により、時空を超えた大だざいふ的な観点で本市を捉えることでより経済税収効果を高め市民の皆様に還元できるまちづくりを推進して参ります。
次に「太宰府館・大宰府展示館・水城館・文化ふれあい館の連携」についてです。
より一層の回遊性向上を図るため、4館で連携した新たな取組について検討を行うと共に、それぞれの館の持つ機能や役割についても整理を行い、4館を総合して最適なパフォーマンスを発揮できるよう検討を進めて参ります。
次に「観光おもてなし美化活動の推進」についてです。
我が国を代表する国際観光都市として、よりおもてなしの心をもって観光客の皆様を迎えるため、市内観光史跡地の草刈りやトイレの維持管理、幹線道路の美化活動などに積極的に取り組み、あわせて市民の皆様も誇りに思える美しいまちづくりを推進して参ります。
次に「ニュー太宰府構想の具体化」についてご説明いたします。
「中心市街地の活性化」につきましては、まちづくりビジョン会議等の有識者の意見も参考にしながら、庁内若手職員による勉強会や鉄道事業者との勉強会等を行い、西鉄五条駅周辺をはじめとした各拠点のあり方について、市街地活性化へ向け様々な角度から検討を進めて参ります。
次に「総合交通計画の改訂」につきましては、渋滞問題の緩和や安全な交通環境の実現に向け、総合的な交通施策を示すことを目的として、計画の改訂を行って参ります。また、自転車交通の役割拡大やサイクルツーリズム等の推進を図るため、自転車活用推進計画の策定についても併せて検討を進めて参ります。
次に「地域公共交通計画の策定」です。
持続可能な都市構造の形成と、利便性の高い公共交通で結ばれたコンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりを進めるため、地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿を明らかにするためのマスタープランとして、関係事業者等との連携を進めながら必要な事業の調整を行い、地域公共交通計画の策定を進めて参ります。
次に「立地適正化計画の策定」です。
ニュー太宰府構想のビジョンのもと、コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりを進めるため、また人口減少と少子高齢化社会を迎えるに当たって、持続可能な都市構造を形成するためのマスタープランとして、さらには、災害に強いまちづくりの視点から、安全なまちづくりを推進するための防災指針の考え方も含め、立地適正化計画の策定に取り組んで参ります。
次に「世界に羽ばたく人材育成の前進」についてご説明いたします。
まず「子ども学生美術展・世界に羽ばたく人材育成表彰」です。
令和4年度に市制施行40周年を記念し「太宰府市子ども学生美術展」を初めて開催し、次代を担う子ども学生たちが、ここ令和の都太宰府市で文化芸術に慣れ親しみ創作活動を行う場を作りあげました。
また、文化、芸術、スポーツ等の分野で活躍している概ね30歳未満の才能に対し、「世界に羽ばたく人材育成表彰」を行う取組を開始しました。令和5年度につきましても、この取組を継続し更に充実させ、世界に羽ばたく人材育成を推し進めて参ります。
次に「全国大会出場の子ども学生等への支援」についてです。
各種スポーツの全国大会等へ出場する子ども学生等や、中学校部活動における上位大会出場者に対し、出場経費の一部を助成する取組の充実を図り、次代を担う子どもたちの支援に力を入れて参ります。
次に「全世代交流型移動図書館」についてです。
令和5年度に移動図書館「すくすく号」のリニューアルを行います。これを機に、利用者が多い小学生向け、図書館への来館が難しい高齢者や小さなお子様のいるご家庭向けに、読書や読み聞かせなどを楽しんでいただくための図書の充実を行うなど、運営方法の充実を図って参ります。また、全世代交流の場としての新たな展開についても検討を行い、より多くの皆様にご利用いただける取組を進めて参ります。
次に「市高大連携の強化」についてですが、現在、市内高校との包括連携協定の締結を進めており、既に連携協定を結んでおります市内大学や太宰府キャンパスネットワーク会議等を活用し、市と高校大学の連携を進め、一人一人の能力を伸ばすための教育活動の充実を図り、学問のまちとしての強みを発揮して参ります。
次は第2の戦略「太宰府型全世代居場所と出番構想(移住定住戦略)」について、令和5年度の重点項目を説明して参ります。この戦略については、ライフステージに応じ全世代に対する支援を講じる予算を編成しております。
まず「中学校完全給食を始め子育て・教育環境の更なる充実」についてご説明いたします。最初に妊娠期・出産期の支援です。
「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施」です。
妊娠期から出産・子育て期にわたる切れ目のない支援として、身近な伴走型の相談支援と経済的支援を合わせたパッケージを提供することにより、全ての妊産婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう継続的に支援して参ります。
次に「初回産科受診料の支援」についてです。
低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握するため、要件を満たす妊婦の初回の産科受診料を助成することで必要な支援につなげて参ります。
次に「多胎妊娠の妊婦健康診査支援」です。
多胎妊娠をした妊婦は特に妊娠中の定期健診が重要であり、より多くの健康診査が必要となることがあります。令和5年度から、これまでは自己負担となっていた追加の健康診査費用の一部助成を行う制度を開始し、すべての妊婦が安心して出産できる環境の充実に取り組んで参ります。
次に「産後ケア事業の拡充」です。
現在実施している「産後ケア事業」について、助産師が利用者宅を訪問し産後ケアを行う居宅訪問(アウトリーチ)型に加え、利用者が助産院に赴き、産後ケアを受ける通所(デイサービス)型を令和5年度より開始し、より充実した内容へ拡充を行います。
次に主に就学前児童家庭への支援です。
「待機児童ゼロへの取組推進」についてです。待機児童ゼロに向けた新たな保育施設の整備や定員増加の取組として、令和5年4月に定員120人の新たな認可保育園を開設いたします。また、既存保育園の増改築による30人の定員増を進めて参ります。
次に「保育所へのICT導入推進」です。
保育士の業務負担の軽減と人材の確保、離職防止を図るため、私立認可保育所における登園管理、保育計画作成、保護者連絡機能等のICTシステムの導入を推進して参ります。
次に「届出保育施設運営支援」につきましては、保育の受皿として重要な役割を担う届出保育施設に対し運営費の一部を補助することにより、通所する児童の安全や保育の質の向上、施設運営の安定化を図って参ります。
次に主に小・中学生家庭に関する支援です。
「太宰府市教育大綱の改定」についてです。
子ども・教育をめぐる環境の変化や、令和のご縁をはじめとした本市を取り巻く状況の変化を踏まえ、新たに就任した教育長、教育委員の知見も加え、令和5年度内に新たな教育大綱を策定いたします。特に学問のまちだざいふとして学力向上に力点を置き、市長部局と教育委員会がより一層連携を密にし、充実した教育施策に取り組んで参ります。
次に「学力向上への取組推進」についてです。
これまでも子どもたちの学力向上に熱意をもって取り組んできた井上新教育長のもと、改めて学問のまちとして小・中学校における学力向上への取組を強化して参ります。まずは、小学校から中学校に上がる際の復習の取組を充実させることなどから始め、更なる拡充にも取り組んで参ります。
次に「地域学校協働活動の推進」です。
学校と地域で学校教育目標や子どもの姿、地域課題等を共有し、課題解決のための実働ができる取組を推進して参ります。この取組により、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進を図り、地域人材の協力による学校支援活動や体験活動等を充実させるとともに、教師の働き方改革を推進し、教育活動の充実に資する体制整備を図って参ります。
次に「放課後子ども教室の拡充」です。
現在、放課後の子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを行い、多様な体験活動ができるように、2つの小学校において、地域コーディネーターを中心に地域人材や市内大学生の協力のもと実施しています。令和5年度は、実施校を拡充するとともに活動内容の充実を図って参ります。
次に「水城小学校管理棟他改築工事」です。
水城小学校校舎の建替に令和4年度より着手しており、仮設校舎への移転や埋蔵文化財の発掘調査など、各工程は順調に進行しています。引き続き、児童の安心安全や学習環境にも十分配慮しながら、令和6年度の完成を目指し改築工事を進めて参ります。
次に「不登校児童生徒支援の推進」です。
小・中学校の不登校児童生徒はコロナ禍を背景に全国的に増加しており、本市ならではの不登校児童生徒の支援にさらに力を入れ取り組んで参ります。市内2箇所につばさ学級を設置し、中学校4校と小学校2校の校内適応指導教室にはST(不登校対応専任教員)を配置します。また、SSW(スクールソーシャルワーカー)を3名配置し、市内大学と連携したスマイルレターを行うなど不登校をはじめとした児童生徒の問題解決のために、きめ細やかな支援を行って参ります。
次に「通級による指導の充実」です。
令和5年度から太宰府東中学校に通級指導教室を新設いたします。これにより全小・中学校に通級指導教室が設置されることになりますので、子どもの自立を目指し、学習面や生活面における困難を改善・克服するため、一人一人の状況に応じた通級指導の充実を更に図って参ります。
次に「中学校完全給食の実施」ですが、本市の悲願である令和6年1月からの全員喫食による中学校完全給食の実施に向け、令和5年度予算案には業務委託費用のほか、各中学校への配膳室工事費用など必要な経費を計上しております。引き続き、完全給食の実施に向け全力を挙げて参ります。
次に「学業院中学校整備計画の策定」です。
学業院中学校の校舎や屋内運動場など学校施設全体の整備基本計画を令和5年度に策定するとともに、教室不足や給食配膳室整備に伴い必要となる仮設校舎を建設し、老朽化対策や教育環境の更なる充実を計画的に進めて参ります。
次に子育て期全般に関する支援です。
まず「こども家庭センターの開設」です。
令和5年4月に「こども家庭庁」が発足することに関連して、いち早く令和5年度の先行開設を目指して参ります。現在、拠点となる子育て支援センターの増改築に着手しており、併せて相談支援体制の拡充や、いきいき情報センター内の「子ども発達相談室」を本施設へ移転することを計画しております。体制整備が整いましたら、児童福祉に関する「子ども家庭総合支援拠点」の機能と、母子保健に関する「子育て世代包括支援センター」の機能を統合した「こども家庭センター」を開設し、全ての妊産婦・子育て世帯・子どもに対する包括的な相談支援等の充実を図って参ります。
次に「子どもの居場所づくり・シングルマザー支援事業」についてです。
子育て支援の新たな取組として、家庭や学校に居場所のない子どもの第3の居場所となる場を市内に開設いたします。本事業はNPO法人と連携し、不登校の子どもや、家庭や学校生活に困難を抱える学齢期以降の子どもたちの居場所づくりを行うとともに、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等の相談支援、食事の提供等を行い、適切な関係機関へつなげていくなど、地域全体で子育てを行う社会を目指す取組です。
また、本施設では同NPO法人が、シングルマザー向けシェアハウスの提供及び社会復帰支援事業等も実施される予定となっており、全面的に支援して参ります。
次に「養育費確保支援事業」です。離婚後の子どもの養育費の分担について、公正証書等の作成に必要な費用、養育費保証契約を保証会社と締結する際の保証料について補助する制度を創設し、養育費に関する取り決めを促すとともに、継続した履行確保を図って参ります。
次に「造血細胞移植後の任意予防接種支援」についてです。
小児がん等の治療のため造血細胞移植を行い、移植後の予防接種の再接種が推奨される方に対し、自己負担となる予防接種費用の一部を補助する制度を新たに開始いたします。この制度により、被接種者の経済的負担軽減と疾病のまん延防止に取り組んで参ります。
この他にも、先に述べました企業誘致、起業創業支援の強化、中学校完全給食の実施等により、働き世代の雇用創出、人口増などにも努めて参ります。
次に「ハードソフト両面からの全世代交流拠点の創設」についてご説明いたします。
高齢者への支援についてもしっかりと取り組んで参りますが、まずは「通いの場等への積極的支援」です。
高齢者の健康課題等を生活圏域ごとに分析し、高齢者が集まる「通いの場」で課題の共有や健康教育を行っておりますが、対象を市内全域に拡大します。あわせて生活習慣病の管理やフレイル予防が必要な高齢者宅を専門職が訪問して保健指導を行い、必要なサービスへつなぐ取組を市内全域で実施し、「高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業」を強化して参ります。
次に「生活支援体制整備事業の推進」についてです。
高齢者の地域における困りごと・課題を支え合いで解決するための住民主体の取組を進めるため、生活支援コーディネーターが活動しています。高齢者の生活支援・介護予防に役立つサービスや情報をまとめた資源帳を作成するなど、住民ニーズに合わせた福祉ネットワークの構築を図り、更なる地域への支援を進めて参ります。
次に「長寿クラブへの支援推進」についてです。
長寿クラブは、健康寿命を延ばし介護に頼らない自立した生活を送るために、地域の仲間と一緒に健康づくりなどに励まれる市を代表する団体です。令和5年度から、地域の単位クラブへの補助金を会員数に応じて加算する方式に拡充いたします。また、長寿クラブ連合会の活動支援のための環境整備を行い、長寿クラブ活動の更なる活性化、充実を後押しして参ります。
ここまで、ライフステージに応じた支援策を説明いたしましたが、ここからは全世代共通の施策を紹介いたします。
まず「全世代交流フリースペースの活用推進」についてです。
いきいき情報センター1階に、誰でも気軽に学習や交流のできる場所として「全世代交流フリースペース」を昨年12月にオープンいたしました。既に高校生大学生の自習スペースとして大いに利用されており、キャンパスフェスタでは多くの来場者で賑わうなど、全世代の皆様に親しまれる場所として好評をいただいているところです。
今後は、学生から提案のあった図書コーナーの設置を進めるとともに、世代をこえた交流ができるイベント等を開催し、フリースペースの有効活用を図って参ります。なお、いきいき情報センターにつきましては、引き続き将来の全面的な施設整備の可能性を探って参ります。
次に「市民の森の整備活用の推進」です。
市民の森につきましては、これまでエフコープとの包括連携協定によるサイン整備を行い、昨年6月にはウォーキングイベントを開催するなど、全世代の皆様の憩いの場としてご利用いただける環境整備を行って参りました。
現在、「四王寺山(市民の森)環境整備計画」を関係団体の皆様の意見も取り入れながら策定に取り組んでおり、今後はこの計画を基に、施設や園路の改修、森林環境譲与税や福岡県展示林整備事業交付金を活用した森林の整備を行うとともに、愛称の募集を行うなど、皆様に親しんでいただける場所としての環境整備を行って参ります。
次に「公園・公民館・公共施設の再定義、多面的な利活用の検討」についてです。
社会経済状況の変化や施設の老朽化などの問題に対応するため、公園や公民館、公共施設に求められる役割や意義について様々な観点から再整理し、より柔軟かつ効率的に施設を使いこなす方策や今後の施設整備のあり方について検討を進めて参ります。
この他にも、先に述べました全世代交流型移動図書館などの取組を通して、全世代が交流しながら、つながりを持って支えあう太宰府ならではの全世代交流拠点の創設を推進して参ります。
次に「安心安全・バリアフリーの更なる推進」についてご説明いたします。
まず「市民一斉避難訓練」です。
昨年11月に本市初めての市民一斉避難訓練を行いました。今回の訓練から得られた課題などをしっかりと総括し、令和5年度にも改めて市民一斉避難訓練を実施いたします。このような取組を積み重ねることにより、実際の災害時に可能な限り被害を軽減できるように改善を図って参ります。また、関係諸団体との連携強化による防災力の向上にも引き続き取り組んで参ります。
次に「安全・安心のまちづくり推進条例の改正」についてです。
本条例は、災害や犯罪等を未然に防止し、市民が安全に安心して暮らすことができるまちづくりについて基本理念等を定めるものですが、市民一斉避難訓練から得た教訓や近年の激甚化する自然災害、多様化凶悪化する犯罪などの課題への対応を強化するため、条例改正を行い安心安全のまちづくりを推進して参ります。
次に「防災備蓄機能の強化」です。
現在とびうめアリーナ内に設置しております防災備蓄品倉庫について、リスクマネジメントの観点から、市内3か所の避難所内への分散化を行い、災害発生時への備えを強化して参ります。
次に「飲酒運転撲滅運動の推進」です。
令和4年度に市職員を対象に研修会を開催し、飲酒運転撲滅へ向けた取組の重要性を改めて再確認したところです。令和5年度はこの取組を更に進めるため、市民の皆様を対象とした講演会を開催し、社会全体で飲酒運転をさせない環境づくりを推進して参ります。
次に「地域見守りカメラの増設」です。
本市では、犯罪の抑止等を目的として地域見守りカメラを設置しておりますが、通学路危険箇所要望等を踏まえて、新たな箇所に地域見守りカメラを設置し、安心安全なまちづくりを推進して参ります。
次に「青色回転灯パトロールの推進」です。
地域防犯活動としてパトロールを行う団体等に対する青色回転灯の無償貸与事業を令和5年度より開始いたします。この取組により、地域防犯力の向上や防犯意識の高揚を図って参ります。
次に「ため池の防災対策推進」です。
市内の防災重点農業用ため池について、堤防が決壊した場合を想定したハザードマップを作成いたします。また、ため池の堤体の劣化状況や耐震等に関する調査を順次行い、ため池ごとに今後の対策を決定し防災対策を進めて参ります。
次に「通学路交通安全対策の推進」です。
関係機関合同による通学路の点検結果に基づき、見通しの悪い箇所や車がスピードを出しやすい通学路等の対策工事を行います。また、大型宅地開発やマンション建築等に伴い生じる新たな課題にも機動的かつ着実に対応することにより、児童生徒の登下校時における交通安全の確保に取り組んで参ります。
次に「側溝蓋設置工事」です。
団地内側溝蓋設置計画に基づき、側溝蓋未設置箇所に蓋を設置することにより、生活道路空間の有効活用を図り、歩行者が安全に生活道路を通行できるよう必要な工事を着実に行って参ります。
次に「公園遊具改修工事」です。
子どもたちが安心安全に遊べる環境と、より魅力的な公園施設の整備を推進するため、公園長寿命化計画に基づき、老朽化が進んだ遊具の安全性を確認し、必要な遊具のリニューアルを進めて参ります。
次に「バリアフリーの計画的な推進」です。
誰もが暮らしやすい、また国際観光都市として多くのお客様をおもてなしするまちづくりに向け、個々の施設等のバリアフリー化だけでなく、面的一体的なバリアフリー化が必要です。本市におけるバリアフリー化を計画的に推進するための方策を具体化して参ります。
次に「点字ブロックの整備促進」についてです。
市民の皆様はもちろん令和の都だざいふの玄関口としてお客様をおもてなしする観点から、令和4年度に西鉄都府楼前駅周辺の点字ブロックの整備を行い、令和5年度は、国道3号線の都府楼前駅交差点及び都府楼前駅博多方面バス停までの区間について点字ブロックの設置を実施いたします。また、補修が必要な点字ブロックに関して随時修繕を行うとともに、その後につきましても計画的に整備を進め、バリアフリー環境の整備を推進して参ります。
次に「アピアランスケア推進事業」です。
がん患者及びがん経験者のがん治療に伴う外見上の変化を補完する補整具等の購入費用を助成する制度を令和5年度から新たに開始します。対象者の心理的負担を軽減するとともに、社会参加を促進し療養生活の質の向上を図って参ります。
この他にも、街路灯のLED化などの取組を進め、安心安全・バリアフリーの更なる推進を図って参ります。
次に「多様性の確保の更なる具体化」についてご説明いたします。
まず「第3次男女共同参画プランの推進」です。
令和5年度からの5年間を計画期間とする「第3次男女共同参画プラン」に基づき、固定的な性別役割分担意識の解消など男女共同参画社会実現に向けての施策の充実に取り組んで参ります。
次に「女性相談体制の拡充」についてです。
令和4年度から主にDVに関する相談を受けてきました女性相談について、更なる相談機能の拡充を行います。就職氷河期世代の抱える問題についての相談や性的マイノリティに関する相談などについても対象を拡大することで、女性全般に関する相談に加え多様性の確保にも資する相談体制の充実を図って参ります。
次に「パートナーシップ宣誓制度の推進」です。
令和4年度に福岡県がパートナーシップ宣誓制度を開始したことを受け、本市はこの制度と連携し、令和4年10月から、県の制度に基づく宣言をされた方が一部の市の行政サービスを利用できるようにいたしました。引き続き、利用できる行政サービスの拡充に取り組んで参ります。
次に「人権啓発の推進」についてです。
「人権都市宣言に関する条例」や「部落差別の解消の推進に関する条例」などに基づく人権啓発を図るため、啓発看板を市内に設置し、本市が「人権都市宣言」のまちであることを市民及び来訪者にアピールするとともに、人権尊重のまちづくりを推進して参ります。
次に「国際交流・姉妹都市交流の推進」です。
多文化共生の推進を図るため、国際交流員の体制を拡充いたします。姉妹都市扶餘郡との交流に加え、市内小・中学校での国際交流に関する授業支援、市民向け講座の実施、国際交流協会と連携した留学生支援などに取り組んで参ります。
続いて「障がい児者や就職氷河期世代の福祉の増進」についてご説明いたします。
まず「医療的ケア児・者在宅レスパイトケア支援事業」についてです。
在宅の医療的ケア児・者の看護や介護を行う家族の負担軽減を図ることを目的に、訪問看護費用の一部を助成する制度を令和5年度より開始いたします。このような新たな取組や必要な障がい福祉サービスに係る給付、その他の支援などを通じ、障がい児・者の更なる福祉の増進を図って参ります。
次に「就職氷河期世代への支援推進」です。
生活や就労に困難を抱える就職氷河期世代に対する支援について、就労支援や社会とつながる仕組みづくりなど、本人や家族に寄り添った支援の充実に取り組んで参ります。
次に「孤独・孤立対策の推進」です。
ひきこもりの長期化・高年齢化、親の高齢化などが進む中、孤独・孤立対策を進めるため、職員を対象とした研修を行うとともに、地域の相談支援関係者との連携を深め支援体制の充実を図って参ります。今後、ひきこもりの実態に関する調査の実施についても検討を進めて参ります。
次に「制度のはざまにある人への支援推進」についてです。
公的支援の対象とならない制度のはざまにある人について、庁内の情報共有を図るとともに関係機関との連携を進め、ニーズの把握や適切な支援へとつなげて参ります。
次に「就職氷河期世代の職員採用」についてです。
本市では、これまでも就職氷河期世代を対象とした職員採用を実施しておりますが、令和5年度に実施する職員採用試験におきましても、就職氷河期世代を対象とした募集枠を設けて職員採用を行う予定としております。
この他にも、先に述べました女性相談窓口などを通じて就職氷河期世代の支援を行って参ります。
次は第3の戦略「令和発祥の都にふさわしい大太宰府構想(圏域拡大戦略)」について、令和5年度の重点項目を説明します。
まず「令和文化会議の定期的開催」についてご説明します。
当時の最先端の国際シンポジウムとされる梅花の宴を現代によみがえらせるべく令和4年度に初めて開催した「令和文化会議」の令和5年度版として、「令和の万葉大茶会」を開催いたします。
次に「史跡の先進的多用途活用の更なる強化」についてご説明いたします。
「史跡の先進的多用途活用」につきましては、令和発祥の都梅プロジェクトをはじめ令和4年度にはフードトラック社会実証実験や史跡地のトイレ改修、休憩用ベンチ設置などに取り組んでおりますが、令和5年度には、「文化財保存活用推進協議会(仮称)」を設置し、文化財保存活用地域計画の進捗管理を行うとともに、史跡の先進的多用途活用の取組を更に進めて参ります。
次に「歴史的街なみの保全」についてです。
太宰府天満宮門前町を中心としたエリアの歴史的な家屋や店舗、市内に点在する社寺建築の保存修理やその他の建造物に対する景観修景にかかる費用等について助成し、歴史的な街なみの保全を推進して参ります。
次に「指定文化財保存整備の推進」についてです。
令和4年度待望の認定を受けた太宰府市文化財保存活用地域計画に基づき、市内の指定文化財保存整備事業を実施して参ります。国重要文化財の太宰府天満宮本殿改修工事への補助を行うなど、本市固有の歴史的文化遺産を、来訪者に良好な状態で見ていただくための保存整備を推進して参ります。
次に「大宰府跡整備基本計画策定」についてです。
令和4年度から、計画策定へ向け利用実態調査や関係者の意見交換会等を行って参りました。令和5年度には、新たに「太宰府市史跡整備検討委員会」を設置し、元号令和の発祥の地である「大宰府跡整備基本計画」の策定を進めて参ります。
次に「先端技術を用いた文化財の活用」です。
史跡の先進的多用途活用の一環として、先端技術を導入した3次元データを解析・生成するシステムを活用し、文化財の調査研究、保存に活用するほか、イベント等において、文化財の3次元複製品の制作過程などに触れる機会を設け、世界に羽ばたく人材育成も念頭に若年層を主体とした活用を進めて参ります。
次に「花いっぱい運動の推進」です。
史跡の先進的多用途活用の一環として、「歴史と文化の環境税」を活用し、関係団体の協力のもと、水城跡、観世音寺、蔵司周辺にコスモスや菜の花を植え多くの皆様に楽しんでいただいております。今後は、一部の種まき作業などを行うボランティアを募り、市民等参加型の活動に発展させて参ります。
次に「太宰府市応援団の活用・拡大」についてご説明いたします。
「太宰府市応援団の活用・拡大」につきましては、先日の市制施行40周年記念式典において、宮本雄二氏、道下美里選手、高田課長さん、おとものタビットに「令和の都だざいふ応援大使」の委嘱をしたところです。これからも、機会を捉えて本市にゆかりのある著名人や将来性豊かな人材等を応援大使として委嘱し、プロモーション活動の充実拡大を行って参ります。
プラム・カルコア太宰府で実施する「文化芸術振興事業」につきましても、応援大使を活用した内容での実施を企画して参ります。応援大使につきましては、このようなイベント等への参画だけではなく、それぞれのご活動の中で折に触れ本市のプロモーションを行っていただくことを大いに期待しているところです。
次に「国・県・自治体の広域連携の前進」についてご説明いたします。
まず「筑紫野市との連携推進」についてです。
筑紫野市とは、消防組合を二市で構成するなどひと際緊密な関係にあります。平井新市長の誕生も受け、観光やまちづくりなどにおいて更なる連携推進を図って参ります。
次に「日本遺産の広域連携推進」についてです。
本来太宰府市単体で認定されていましたが敢えて大だざいふ的な観点で広域化することを選択した日本遺産「西の都」について、国県や近隣自治体との広域的多面的な連携による相乗効果の発揮を図って参ります。令和5年度は、大宰府跡ほか構成文化財のサイン整備を実施するなどの普及啓発活動に積極的に取り組んで参ります。
次に「友好都市交流の推進」です。
令和4年度に奈良市との友好都市提携20周年を迎え、私も奈良市を訪問し仲川市長との対談を行うなど交流を深めてきたところです。引き続き、友好都市である奈良市、多賀城市、中津市との友好交流を進め、関係人口、交流人口の拡大に努めて参ります。
次に「戦略的シティプロモーションの強力な推進」についてご説明します。
まず「シティプロモーションの推進」につきましては、現在、戦略的シティプロモーションのあり方について検討を進めておりますが、今後は戦略的広報の視点で、組織横断的に統一したシティプロモーションの展開を行って参ります。また、応援大使に就任した「おとものタビット」を活用したプロモーションや観光誘客活動にも更に力を入れ推進して参ります。
次に「一体的情報発信の検討」についてです。
現在、市からの情報を様々な手段で発信しておりますが、情報伝達の更なる向上を図るため、市政情報、防災情報に加え観光情報等の一体的発信について検討を行って参ります。
最後に第4の戦略「1300年の歴史に思いを致す持続可能な太宰府構想(行財政改革戦略)」について令和5年度の重点項目を説明いたします。
まず「行財政改革の更なる断行」について説明します。
中学校完全給食など必要な行政需要に適切に対応しながら、将来にわたり持続可能な行財政運営を堅持するため、歳出入一体改革を推し進めて参ります。具体的な改革として、令和5年度から太宰府東小学校の給食調理業務の民間委託への移行を行います。また、敬老事業補助金について支給対象年齢の段階的引き上げについても検討を進めます。
次に「戦略的まちづくりの推進」についてですが、総合戦略推進委員会(まちづくりビジョン会議)からの専門的な知見や地域に即した意見を参考としながら市政運営を行い、令和6年度に期限を迎えるまちづくりビジョン改定へ向けても議論を進めて参ります。また、市民の皆様の各種施策や事業についての認知度、意向などをより的確に把握するための市民意識調査を行い、まちづくりの指標として各種施策の展開に反映させて参ります。
次に「ふるさと納税の推進」です。
私の就任以来、各種媒体を通じたトップセールス、クラウドファンディング、企業版ふるさと納税の導入などの取組を行ってきた結果、令和4年度の寄附額は30倍増となる12億円を上回っております。令和5年度につきましては、戦略的シティプロモーションや魅力ある返礼品の拡充、ポータルサイトの増設等により、寄附額10億円の大台を引き続き達成するとともに、より多くの寄附をいただけるよう取り組んで参ります。
次に「入札改革の推進」についてです。
令和4年度から一部工事の入札において最低制限価格制度の運用を開始し、ダンピング対策を進めています。令和5年度からは入札参加者の負担軽減を図るため、電子入札システムの運用を開始します。また、入札に立ち会う職員数についても削減を図るなど、更なる効率化を進めて参ります。
次に「窓口機能の充実・強化を始めとする組織再編」について説明いたします。
「窓口機能の充実・強化」につきましては、にしのまどぐちの開設や証明書のコンビニ交付など積極的に取り組んで参りましたが、今月よりスタートした「引越しワンストップサービス」のほか、4月から運用開始予定の子育てや介護等に関する「行政手続きのオンライン化」など、マイナンバーカードを用いたオンライン手続等による利便性の向上を図って参ります。あわせて、マイナンバーカードの普及促進にも引き続き取り組んで参ります。
また、福祉に関する相談内容が多様化しており、制度の「はざま」にある人や複合的な支援を必要とする方が増えていることを受け、職員の相談対応スキルの向上や関係機関との連携強化を進めるとともに、「福祉の総合窓口」の設置、市役所に来なくても相談できる体制の構築についても検討を行って参ります。
「機構改革」については、令和4年度から行政事務改善委員会において課題の抽出を行っており、引き続き時代性や市民ニーズに即した全体最適化を図る機構改革を検討して参ります。
「Web口座振替申請の導入」については、税金等の納付に関する口座振替をインターネットから手続できるサービスを導入します。書類の記入や押印も不要となり、市役所や金融機関の窓口に出向く必要がなくなるものです。
この他にも、先に述べました女性相談窓口や、電子入札の導入、子ども家庭センターの開設、子どもの居場所づくり・シングルマザー支援事業などの取組を通じ、窓口機能の充実・強化を進めて参ります。
次に「新しい公共の促進」についてご説明します。
行政機能が多様化、高度化、煩雑化する中、地域コミュニティや諸団体、市民などと役割を協働、分担していく「新しい公共の促進」に向けて、NPO・ボランティア支援センターなど関係機関との連携を深めるとともに、ビジョン会議などを通じた議論を進めて参ります。
「地域コミュニティの活性化」については、少子高齢化や地域での繋がりが希薄化する一方で、コロナ禍や災害の頻発などで地域の助け合いの必要性はむしろ高まる中、まちづくりビジョン会議での新しい公共の議論なども参考にしつつ、地域コミュニティ組織の活性化を担うリーダー的人材の育成や子どもや高齢者など多様な主体が交流、連携できるよう、区自治会など地域コミュニティを積極的に支援して参ります。
この他にも先に述べました、公園・公民館・公共施設の再定義、多機能活用の検討や、放課後子ども教室の推進などを通じて新しい公共の促進を図って参ります。
次に「ゼロカーボンシティの推進」について説明いたします。
太宰府市では、2050年に温室効果ガスの排出量を実質ゼロとすることを目指し、令和3年6月に太宰府市気候非常事態ゼロカーボンシティ宣言を発出しました。現在、「地球温暖化対策実行計画区域施策編」の策定を進めており、令和5年度は第四次環境基本計画や実行計画に基づく施策を着実に実施し、長期的な脱炭素社会の実現に向けた取組を推進して参ります。
「地球温暖化対策の推進」についてですが、ゼロカーボンシティの実現に向け、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス、戸建て住宅用再生可能エネルギー発電等設備、次世代自動車の導入を促進するための補助金制度を継続して行って参ります。
次に「ごみ減量の推進」についてです。
これまで「ごみ減量72,000人プロジェクト」として、もえるごみの減量、3Rの推進に取り組んで参りました。令和3年度からは市役所でのフードドライブを開始するなど新たな試みにも取り組んできたところです。さらなるごみ減量とごみ処理費用の削減を図るため、令和5年度からは、新たに「一人ひとりのごみ減量プロジェクト」と銘打ち、力を入れて啓発活動等を推進して参ります。
次に「街路灯などのLED化推進」です。
街路灯や防犯灯、公共施設の照明のLED化を計画的に進めて参ります。ゼロカーボンシティの実現に寄与し、消費電力量及びCO2排出量の削減を図るとともに、従来よりも明るい安心安全なまちづくりを推進して参ります。
次に「DXの推進と人材育成」についてご説明いたします。
まず、「職員採用・育成の充実」につきましては、就職説明会の開催や外部説明会へのブース出展、就職情報サイトへの掲載などによる積極的な採用活動を行って参ります。令和5年度からは、これまで以上に意欲的に学生インターンの受入を行い、優秀な人材の確保に努めて参ります。また、民間等との人事交流にも引き続き取り組みます。人材育成基本方針に掲げた「世の為人の為市の為市民の為に」との基本理念のもと、職員研修、人材育成に努め、接遇や市民サービスの向上を図って参ります。
次に「テレワーク端末の利活用」についてです。
昨年度導入したテレワーク端末を、業務効率化や災害時等における行政機能の維持のための有効な手段として、更なる利活用を進めて参ります。
次に「ビジネスチャットサービス導入」です。
庁内プロジェクトチーム等におけるコミュニケーションの効率化や業務プロセスの見直しなどを図るため、ビジネスチャットサービスを導入し、組織としてのパフォーマンス向上に取り組んで参ります。
次に「交通情報案内システムの充実」についてです。
現在、本市の慢性的課題である渋滞の解消を図るため、市内の渋滞情報や駐車場の満空情報をウェブサイト上で配信しておりますが、より事業の効果を高めるため、既存のライブカメラを活用した満空情報の自動判定化等の検討を行い、更なるシステムの充実を図って参ります。
この他にも、国が進めるシステム標準化に向けて業務の棚卸しを進める中で帳票に関する業務の整理・見直しを行うことや、低廉なOAソフトを部分的に導入することで、業務の質と費用効率の両立を図って参ります。加えて、先に述べました文化財3D資料、電子入札、引越しワンストップサービス、行政手続きのオンライン化、Web口座振替申請などの導入を通じてDXの推進を図って参ります。
以上、二期目の公約に基づき、様々な新機軸も盛り込んだ「市民ニーズに応える令和の都だざいふ予算」について、まちづくりビジョンに沿った重点項目を中心に、詳細にご説明してまいりました。そして今回は、6回目にして初めて当初予算の重点予算を構想戦略別、世代カテゴリー別に分析した説明を試みました。
そのネーミング通り、令和の都さらにはばたくだざいふを標榜し、その根本たるまちづくりビジョンの構想戦略に基づいたトップダウン型予算という側面と、本市のあらゆる世代や状況に応じた市民ニーズに沿ってこつこつと積み上げたボトムアップ型予算という側面の二つの側面を持った予算で、全職員とともに創り上げた最善の予算と自負しております。
議員各位そして市民の皆様のご理解ご協力を得て成立させて頂いた暁には、令和5年度も世の為人の為市の為市民の為に持ちうる力を出し尽くして参ることをここにお誓いし、私の施政方針といたします。長時間に亘りご清聴ありがとうございました。
令和5年2月28日
太宰府市長 楠田 大蔵