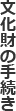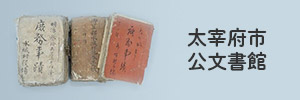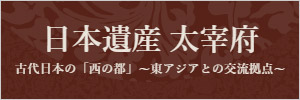本文
光明寺本堂が新たに市指定文化財になりました
光明寺は、太宰府天満宮の南に隣接する禅宗寺院です。創建は、文永10年(1273)と嘉暦元年(1326)の二説が伝わります。江戸時代には天満宮に仕える人々とその家族の菩提寺として再興され、仏像・美術品が多く制作されました。境内の庭園は重森三玲が昭和32年(1957)に作庭したもので、平成26年(2014)に県指定名勝「光明寺庭園」として指定され保存されています。
令和7年2月28日、太宰府市教育委員会は、光明寺の本堂は江戸時代の建築当初の姿をよく留めていて江戸期の方丈建築(禅宗寺院の住宅兼仏堂の建築様式)として貴重であることから、市の有形文化財(建造物)に指定しました。
なお、現在、光明寺の拝観は受け付けていません。
指定された文化財
光明寺本堂 附 大方玄関、知客寮、棟札
読み/こうみょうじほんどう つけたり たいほうげんかん しかりょう むなふだ
所在/宰府二丁目1102番地
光明寺本堂は、蟇股(蛙に似た形の建築部材)の墨書と棟札(建築の事情を記録した札)により、建築年代が安政3年(1856)と明らかです。安政3年の建築以降、数度の改修を経ているものの、柱梁等の主要な構造材と室内意匠に建築当初の部材と姿をよく留めています。江戸期の建築が少ない太宰府天満宮門前にあって、市内で唯一の江戸期の方丈建築として貴重なものです。
また、大方玄関や知客寮は本堂と一体的に構成されており、棟札は光明寺本堂の歴史的価値を明らかにする資料であるので、あわせて保護します。
光明寺本堂