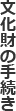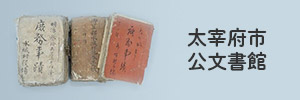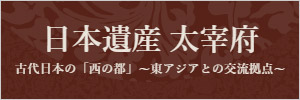本文
宝満山出土の仏像が新たに市指定文化財になりました
市の北東に位置する宝満山は、古代大宰府と密接な関係をもって成立した信仰の山です。古代では最澄などが唐(中国)に渡航するときに祈願が行われ、中世には修験道の山として発展し、近世を通じて信仰の山として発展しました。古代から近世に至る遺跡が多く残っており、日本の山岳信仰のあり方を考えるうえで重要であることから、山の一部が国の史跡に指定されています。宝満山一帯では、これまで40回を超える発掘調査が行われてきました。
令和6年2月29日、発掘調査で発見されていた仏像2点について、山岳霊場遺跡である宝満山において出土した仏教的要素を持つ遺物として重要であることから、「宝満山遺跡群出土金銅仏」として市の指定文化財(考古資料)に指定しました。
指定された文化財
銅造菩薩形立像

所在/国分四丁目9-1(太宰府市文化ふれあい館)
所蔵者/太宰府市
大きさ/総高10.5cm、像高8.9cm、重量116.4g
白鳳様式(7~8世紀)と考えられる小さな金銅仏で、九州では数少ない作例です。発見された場所からは、古代末~中世の僧坊(僧侶が居住した建物)跡が確認されており、経典と共に埋められた可能性や、僧侶が身近に置いて礼拝していた可能性が考えられます。
銅造如来形立像
 読み/どうぞうにょらいぎょうりゅうぞう
読み/どうぞうにょらいぎょうりゅうぞう
所在/国分四丁目9-1(太宰府市文化ふれあい館)
所蔵者/太宰府市
大きさ/総高11.8cm、像高9.5cm、重量242.4g
平安時代前期頃(9世紀)と考えられる小さな金銅仏で、同時代の作例は九州では希少です。発見された場所は、最澄が各地に建立した「六所宝塔」のうちの「安西塔」ではないかと考えられています。