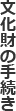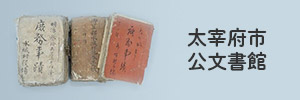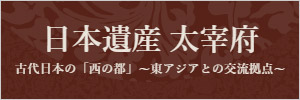本文
菅原道真と太宰府天満宮
左遷の地・大宰府
現在おおくの人が参拝に訪れる太宰府天満宮は、菅原道真(すがわらのみちざね)を神としてまつる神社です。菅原道真は平安時代の9世紀後半に学者・詩人・政治家として活躍しましたが、政争に敗れて昌泰4年(901)に大宰府に左遷(させん)されました。
大宰府は、奈良時代以来、左遷の地として使われることがありました。たとえば、藤原広嗣、玄ぼう(げんぼう。ぼうは日へんに方)、阿保親王、源高明、藤原伊周といった人々が大宰府に左遷されています。
九州全体を統括して外交の窓口でもあった大宰府の役人は、位も高く、一般的には魅力的なポストでした。しかし同時に、「地位は高くて任地は都から遠い」という特徴は、失脚した有力者をつけるのに都合の良いポストでもあったのです。そうして大宰府に左遷されてきた人々のなかで、最も有名なのが菅原道真です。
玄ぼうの墓(観世音寺5丁目)
玄ぼうは唐に留学した後に都で大きな権力を持ちましたが、失脚して観世音寺を造る役所の長官として左遷されました。
菅原道真の左遷
都では栄達を極めた菅原道真でしたが、大宰府での暮しは都とはうって変わってわびしいもので、与えられた住居の床はボロボロで屋根は雨漏りするようなありさまでした。その住居から出ることもできない境遇を「都府の楼はわずかに瓦の色をみる。観音寺はただ鐘の声をのみ聴く」(大宰府政庁の建物は遠くから瓦の色を見るだけで、観世音寺は鐘の音を聴くだけだ)と漢詩に詠んでいます。現在、大宰府政庁跡のことを「都府楼跡(とふろうあと)」とも呼ぶのは、この詩に由来します。
道真は失意のうちに2年間を過ごし、延喜3年(903)に亡くなりました。埋葬のためになきがらを運んでいたところ、車を引く牛が動かなくなったので、ここに留まりたいという道真の遺志だと考えてそこに墓を建てたと伝わります。

天拝山(筑紫野市)で天に無実を訴える菅原道真
(出典:国立博物館所蔵品統合検索システム<外部リンク>「北野天神縁起絵巻」(14世紀、九州国立博物館所蔵)
菅原道真の没後
道真の死後、都で落雷や突然死が起こりました。当時の人々は道真のたたりだとおそれ、道真を神として祭ることでなだめようとします。こうして、道真は「天満大自在天神」(天神さま)として信仰されることになり、墓のうえに安楽寺天満宮(現在の太宰府天満宮)がつくられました。その後、大宰府の役人として赴任した貴族たちによって建物や土地が寄進され、最盛期には40か所以上の荘園を持つ大寺院として発展します。
戦国時代には度々の戦乱に巻きこまれて荒廃しましたが、安土桃山時代から江戸時代に復興されました。平和になった江戸時代には庶民が全国の名所を旅行するようになり、太宰府天満宮は「さいふまいり」の名所として多くの人が参拝に訪れました。
菅原道真は文筆に優れていたことから学問や文化芸術の神として、また雨を降らせる雷神であることから農耕の神としても尊敬され、現在に至るまで篤く信仰されています。

豊臣政権下で小早川隆景が再建した太宰府天満宮の本殿(重要文化財)
文化財保存のため令和8年まで改修工事中